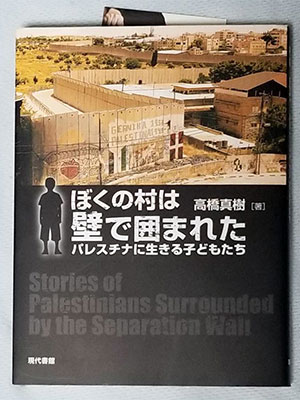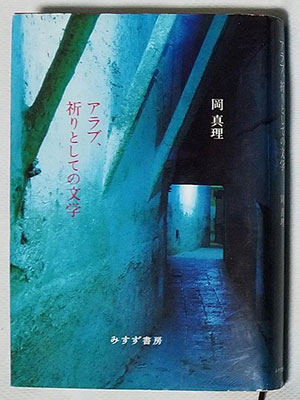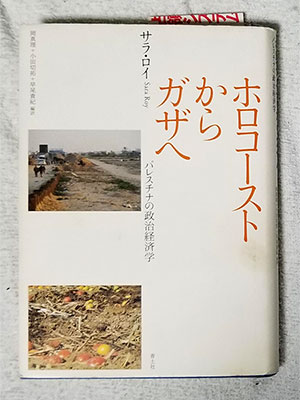入口 >トップメニュー >戦争と平和 >現ページ
3.世界各地の紛争・Ⅰ
(2002年2月25日記載)
世界には、数多くの紛争がある。国や民族の数だけ紛争があるとは言わないが、私たちが日常のニュースで知っている紛争はほんの一握りに過ぎない。平和だと思われているこの日本にも、北方四島や竹島などの領土問題がある。紛争には、①領土の所有をめぐる紛争、②貧富の差(富の分配の不公平)から起こる紛争、③民族の違いによる紛争、④宗教の違いによる紛争…等々があるが、実際はこれらの問題が単体で存在するのではなく、それぞれが相互に絡み合って起こる。
一度紛争が起こってしまうと、それを沈静・正常化させるのは困難である。相互に被害が拡大してしまうと、憎しみが憎しみを生み怨嗟が増大を続ける。紛争は延々と続くか、さもなくば力に勝る側が一方的な破壊や大量殺戮を行って紛争の根源自体を亡くす…というのが、過去歴史に見られる方向である。その紛争を止めるのはもはや当事者間では不可能で、第三者の介入が必要である。その目的を達成するための国連結成ではあるが、各国の思惑がぶつかり実際に国連軍が組織されることは難しいのだ(例外的に、旧ソ連が国連決議をボイコットした時に結成されたことがある)。湾岸戦争時の、アメリカを中心とした多国籍軍も実は国連軍ではない。このように、いかに第三者が紛争に介入するのが困難かが分かるであろう。カンボジアや東チモールのように、国連が介入してくれた紛争は幸せな方である。現在も世界中にある多くの紛争は、未だに無益な犠牲者を出しながら続けられているのだ。
私たちは、まず世界でどのような紛争があり、何がその原因なのかを知る必要がある。どの紛争にもそれぞれ大義名分があるから、一方の論理だけに耳を傾けていると、真実を見失うかもしれない。なるべく多くの情報に耳を傾け、多角的に紛争をとらえていく必要があろう。世界で問題となっている様々な紛争を考えてみたいが、今回は世界で最も注目を浴び続けている紛争、イスラエル・パレスチナ問題の歴史を探ろう。
・イスラエル・パレスチナ問題
国際紛争問題としては、最もニュースに登場するものの一つ。アラブ対イスラエルという中東紛争問題の震源地ともなっている。
地中海沿岸からサウジアラビア周辺、そしてアフリカの一部まで、アラブと一口にくくられてしまうが、、この地域には様々な民族や言語が存在し、複雑な歴史の背景がある。国境間の紛争、部族間同士の紛争、ナショナリズムと旧体制の衝突など、中東それ自体で問題は数多い。しかし、直接的なバレスチナ問題の発端は、19世紀後半からヨーロッパ(特に東欧および中欧)に興ったシオニズム運動と、ユダヤ人のパレスチナ入植開始である。シオニズムは、言い換えれば「ユダヤ民族主義」であり、紀元70年に追われた祖国パレスチナに戻ろうという運動であった。
何故このようなシオニズムが登場したかと言うと、帝政ロシアにおいて東欧ユダヤ人の虐殺を容認していて、彼らをこの迫害と離散から救うために当時の東欧の社会主義学者達がシオニズムを理論化し、パレスチナ入植促進委員会が設立され最初の入植が行われたのである。そして、シオニズムが明確な姿をとったのは、1896年ユダヤ建国の父と言われるオーストリアのジャーナリスト、テオドール・ヘルツルが「ユダヤ人国家」を著し、翌年スイスで第一回シオニスト会議が開催されてからである。ここで、公にパレスチナに「ユダヤ人のために公法によって保証される郷土(ホーム)を創設する」ことが宣言された。この時から、アラブとイスラエルの対立が始まった。しかしこの計画に同情的であったのは、唯一イギリスのみであった。イギリスは、中東権益に深い関わりを持っていて、1840年のダマスカスにおけるユダヤ教徒迫害が、シオニズムへの関心に拍車をかけた。
しかし、イギリスは初めから入植地をパレスチナに考えていたわけではない。当初イギリスは、ユダヤ人の入植地はキプロスを考慮し、次いでシナイ半島北部を考えていた(もちろんエジプトの反対に遭い頓挫)。その後、イギリスは1903年に東アフリカのウガンダの"無人の"高地を提案。しかし、この案は第六回シオニスト会議で混乱を極め、第七回シオニスト会議で「ユダヤの郷土はパレスチナ以外のいずれの土地をも対象としない」ことが決定された。
さて、時代は第一次世界大戦に突入。イギリス帝国は、アラビアのロレンスで有名な"砂漠の反乱"を起こさせることに成功。この反乱の代償として、イギリスは「アラブ地域の独立」を約束した…その独立地域にはパレスチナも含まれている。その一方で、ユダヤ人富豪ロスチャイルド達の働きかけもあり、イギリス帝国は「パレスチナにユダヤ人の民族的郷土建設することに好意をもってのぞみ、その目的達成を容易ならしめるため、最善を尽くすこと」も後から約束した(バルフォア宣言)。正に二重外交である。この時点で、今日のアラブ・イスラエル問題が始まったのである。(ちなみに、この矛盾し混乱した二重外交に留まらず、イギリスはフランスと密約を結び、トルコ領土の大半をイギリス、フランス、ロシアにおいて分割することをも決めていた)。
歴史上破廉恥極まりない"バルフォア宣言"は、第一次大戦後に着々と実行されていった。第一次大戦後、パレスチナはイギリスの委任統治となったが、バルフォア宣言に基づいて統治されることが決定された。19世紀初頭にはパレスチナにユダヤ人は2%しかいなかったが、第一次世界大戦後は10%を超える。1933年以降、ナチスの迫害が開始されると移民の数は激増の一途を辿った。しかし、当然現地パレスチナには多数のアラブ人達が住んでいるので、イギリスの委任統治に激しい抵抗が起こるようになった。ユダヤとアラブ双方の利害はますます激しくなり、イギリスは自らの委任統治の矛盾を認めるようになり、1939年にイギリスはアラブ側にくみする白書を公表するに至った。これは、シオニストにとって裏切り行為となり、シオニストによる反英テロ活動が横行することとなった。
第二次大戦後、1947年2月にイギリスはパレスチナの統治能力を喪失したことを認め、この問題を国連に移管した。国連特別総会は、同年4月にパレスチナ問題を調査するための特別委員会(UNSCOP)の設置と、同委員会による現地調査派遣を決定した。この委員会には、大国を除く11カ国から構成された。5月に現地調査が行われ、8月末に報告書が提出されたが、多数案と少数案が併記された。多数案(カナダ等7カ国案)は「アラブ国家とユダヤ国家の分割案で、聖地エルサレムとベツレヘムは国連による永久信託統治する」というもので、少数案(インド等3カ国案)は「エルサレムを首都とするアラブ人とユダヤ人の連邦国家」であった。オーストラリアは、両案に反対した。多数案は、必要な3分の2の賛成を得られなかった。ここから、シオニストとアメリカによる猛烈な多数派工作が展開されることとなった。
アメリカ国内には、多くのユダヤ人社会が存在し、選挙母胎としての圧力をかけていた。そして、財界の実力者にユダヤ人が多いと言うのも事実であった。ルーズベルトの後を継いだトルーマン大統領は、早くからユダヤ人国家の創設に賛成していた。トルーマン曰く「ユダヤ人は票になるが、アラブ人は票にならない」のである。国連総会におけるシオニストと強国アメリカによる多数派工作は、熾烈を極めた。工作の対象となったのは、ハイチ、リベリア、フィリピン、中国、エチオピア、ギリシャの六カ国。最後まで分割案に反対し通したのはギリシャだけで、残りは棄権と賛成にまわった。運命の1947年11月29日、国連総会はパレスチナ分割案を賛成33、反対13、棄権10をもって可決した。かくして、シオニストは即日イスラエル国家の設立を宣言し、アメリカは直ちにこれを承認し、三日後ソビエトもこれに倣い、イスエラルは建国されたのである。
このイスラエル建国が不当であったことは、改めて言うまでもない。現地アラブ住民の主権を侵害し、外国からの移民にパレスチナの大部分を割譲し、現地アラブ住民の正当な自決権の行使を否定した。この不当性は、分割案で示されたイスラエル国家とアラブ国家の人口と面積比や土地所有の割合などに照らせば、極めて明白だった。イスラエル国家に割り当てられた面積は、全パレスチナの57%を占めていたが、人口はパレスチナ人口192万人のわずか31%…約61万人を占めるにすぎなかった。その61万人のうち、当初からパレスチナに住んでいたのはせいぜい十分の一ほどであった。また、この国連の分割案で承認されたイスラエル国家自身でさえ、そこに居住するユダヤ人は490,020人なのに対して、同国に居住するアラブ人は509,780人を数えユダヤ人が少数側だったのである。更に土地所有を見ると、1945年時点でユダヤ人の所有する土地は僅か5.66%に過ぎなかった。国連分割案ではこの「わずか6%ほどの土地所有者であるユダヤ人にバレスチナ全土のほぼ3分の2が与えられた」のである。正に、「軒下を貸して母屋を取られる」状況であった。
もちろん、この歴史上希に見る不当なイスラエル建国を、アラブ諸国が黙ってみているわけがなかった。1948年5月14日、イギリス軍の撤退が完了すると同時に、周辺アラブ諸国、エジプト、ヨルダン、シリア、レバノンは、イスラエルの殲滅を目指してパレスチナに攻め込んだ。パレスチナ戦争(第一回中東戦争)の勃発である。緒戦ではアラブに有利に進んだこの戦争も、最終的にアラブは大きく敗退した。この戦争の結果、イスラエルの領域は逆に拡張し、なんとパレスチナの80%にのぼった。この戦争と、ユダヤ機関のテロ活動の結果、多くのアラブ人が、イスラエル領から追い出された(ちなみに、後のイスラエル首相メナハム・ベギンは、アラブの老若男女254人が虐殺された小村デイル・ヤデイル・ヤシーン事件のシオニスト武装集団イルグンの一部隊長であった)。かつて東欧やドイツでユダヤ人が受けた迫害や虐殺を、テロ活動でアラブ人に対して容赦なく行い、アラブ人はパレスチナを去らざるを得なかった。そしてパレスチナ戦争によってパレスチナから追い出されたアラブ人は、75万人から100万人にのぼると言われる。国連の中にパレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)が創設されたが、登録されたパレスチナ難民の数は96万人に達した。こうしてイスラエル建国はアラブ・イスラエル問題を定着させ、パレスチナ難民という新たな問題を発生させたのである。
その後、この地域では3回に渡る大規模な戦争が発生した。第二回目の1956年のスエズ運河のエジプト国有に伴う戦争は、国際世論の盛り上がりと米ソの圧力で、エジプトの外交的勝利に終わった。第三回目の1967年の戦争は圧倒的な電撃作戦を行ったイスラエルの勝利で終わり、新たな占領地を得、同時に新たな難民を生んだ。この頃から、暗にイスラエルの存在を認めることに同意した穏健派アラブ諸国と、イスラエルの建国を認めないパレスチナ解放機構(PLO/パレスチナ人の運動を統合するために1964年に結成された組織)らの解放勢力との溝も広がっていった。1973年の第四次中東戦争は、アラブ諸国(エジプトとシリア)が曲がりになりにもイスラエルと互角に戦った初めての戦争だった。そして、初めて石油輸出を武器とした画期的な戦略が用いられた。そして、この戦争でエジプト側は、1967年の国連理事会決議(※イスラエルの全占領地からの撤退)の全面履行開始を要請した。しかし、決議の解釈の曖昧さで、双方が譲れないものがあった。
その後、アメリカの強力な介入でエジプトとイスラエルの直接和平の道が開かれた。1978年9月17日に両国はカーター大統領の立会いのもとに合意し、これは「キャンプ・デービッドの合意」と名づけられた。しかしエジプト・イスラエル問題は、ほとんどパレスチナとは関係が薄い紛争だったからこそ成し得た和平であり、イスラエル・アラブ対立の中東問題の本質の解決とはほど遠いものだった。「キャンプ・デービッド」の合意においては、ヨルダン川西岸、ガザ地区の最終領土の帰属、聖地エルサレムの処遇、パレスチナ人の民族自決権、パレスチナ人国家の樹立等については、全く触れられていず、パレスチナ解放機構についてはその存在すら完全に無視されている。この合意は、PLOはもとより穏健派アラブ諸国にとっても、到底受け入れられないものだった。アラブ首脳会議で、アラブ諸国は「キャンプ・デービッドの合意」に反対する決議を行い、エジプトに調印しないように呼びかけたが、エジプトはこれに調印。以後、エジプトはアラブ諸国から断交されることとなった。
…さて、ここまでイスラエル・パレスチナ紛争の歴史をごく簡潔に見てきたが、もちろんこれは詳細を省いたあくまで略史であり、また現在に至るまでも様々な事件が起こっている。今もイスラエルとパレスチナの問題の本質は何ら変わることなく、否むしろ双方に被害が出る度に、怨嗟の念が強くなっている。イスラエルとアラブの紛争は、ここ百年の間の比較的新しい問題である。この紛争は、かつてのイギリス帝国の権勢拡大を目指したエゴによって生まれ、ユダヤ票に後押しされたアメリカの強硬かつ不当な手段で完成したことが明らかである。結果、パレスチナに暮らしていた大勢のアラブの人々が故郷を追われて難民となり、アラブ諸国の人々がイスラエルやアメリカを恨む構図が完成した。
またアメリカのダブルスタンダードが、このアラブ諸国の怒りの炎に油を注いでいる。湾岸戦争におけるイラクへの武力行使は、「イラクはクェートから即時撤退すべし」という国連決議を根拠としていた。ところが、同じく国連決議で「イスラエルはその占領地から撤退すべし」というものが出ていても、こちらは20年もアメリカは放置している。同様に、「イスラエルは追放パレスチナ人を帰還させること」という国連決議をイスラエルは無視し続けているが、これもまた何の制裁も与えられていない。明らかな、ダブルスタンダードである…。
もちろん、テロは絶対になくさねばいけない。しかしイスラエルがアメリカ製の最新鋭の武器と高度な軍事訓練を背景に、小国ながらも圧倒的な軍事的優位を保つ一方で、土地も住む家も奪われかつ武力では圧倒的に劣るパレスチナの人々の"思い"は、どこにぶつけたら良いのか。イスラエルの背後に、アメリカがいる。アメリカは、国連で議決権を有する大国である。将来に望みのない貧しいパレスチナのアラブの人々は、女性ですら喜んで自爆テロを志願すると言う…しかしパレスチナ側がテロを起こすと、イスラエルの武力報復は5倍となって返ってくると言われる。銃を持たない子供たちは、銃を持った兵士に対して今日も石を投げ続ける。
もちろん、テロは絶対無くさねばならない。もし、アメリカが"世界の警察"を自認し"テロ"を撲滅するのであれば、この不当に故郷を追われたパレスチナの人々にしっかりと目を向け、形式だけでない・不平等でない和平に尽力すべきである。また、建国以前から"シオニズム"というユダヤの民族主義をベースに成り立っているイスラエルの人々は、かつて自分たちが受けた迫害を思い起こし、パレスチナとの怨嗟の増大合戦に終止符をうつべきだ。日本を初めとする国際社会の国々も、根本的な和平に向けて決して力を惜しんではならない。対岸の火事ではないはずだ。
次回は、イスラエル・パレスチナ紛争以外の、様々な紛争を見ていきたい。
新品価格
¥821から
(2014/11/17 09:10時点)
新品価格
¥2,052から
(2014/11/17 16:51時点)
池上彰が読む「イスラム」世界知らないと恥をかく世界の大問題 学べる図解版第4弾
中古価格
¥1,337から
(2014/11/17 16:52時点)
中古価格
¥34から
(2014/11/17 16:55時点)
2017年8月8日追記:「パレスチナ問題(高橋和夫著/放送大学教育振興会)」を読んで
このページの記事を調べて書いたのが、2002年2月。それから15年半もの月日が経過した。15年で変化したものもあれば、変わらないものもある。昨年2016年3月に発行されたばかりの放送大学の高橋和夫教授が書かれた「パレスチナ問題」を読んだので、これを基に最近のパレスチナ情勢を概観してみたい。
新品価格
¥3,024から
(2017/8/8 14:32時点)
15年も経つと、調査・研究が進んで新たなことが分かったり、政治的な状況もかなり変化してくる。今回読んだ本にも以前には無かった新しい学説も登場している。例えば、シュロモー・サンドの「ユダヤの起源」もそんな一つ。ヨーロッパのユダヤ人は、パレスチナ出身者ではなく改宗した人々で彼らが各地で迫害されイスラエル建国の中心の人々となった人々であり、イスラエルの建国でその支配下・占領下でパレスチナに生活している人々が、(イスラム教やキリストに改宗した)本来のユダヤ教徒である、と言う説である。ただし、この論争は最近のもので、何も決着が得られていない。15年も経過すると、色々なことが変わってくる、疑問が呈されると言う実例である。
このように変化するものもあるが、変わっていないこともある。故郷を追われたパレスチナの人々は相変わらず難民であり、故郷に戻ることができず、イスラエルの占領下ないし影響の下で苦しんでいると言う事実がある。こんかい読んだこの「パレスチナ問題」は、僕が以前調べた内容と異なるものでもなければ、歴史的事実が異なるものでもない。しかしながら、この本はそれ以後の歴史についての記述があり、またパレスチナ側の視点一辺倒でなく、それぞれの関係国の政治的背景やお国の事情も丁寧に取り上げている。全内容をまとめる気はないので(※興味のある人は本の方をじっくりと全部読んでください)、関係各国の政治的思惑や事情だけを超簡潔にまとめる。
①エジプト
上記の2002年時の本文でも書いたが、第二次中東戦争(軍事的敗北)で、米ソの支援で外交的な勝利(政治的勝利)を収めたナセル大統領だったが、第三次中東戦争(六日間戦争)でイスラエルの奇襲で300機ものエジプト空軍機を失うと言う大敗北をきっして(シリアとヨルダンの空軍も撃滅)、ナセリズムは死んだ。ナセル大統領の死後、その後を継いだのがサダト大統領である。 第四次中東戦争で曲がりなりにもイスラエルと互角に戦ったが、その後アメリカの介入でエジプトとイスラエルが「キャンプデービッドの合意」をしてしまった。ナセルの大義は「アラブ第一主義」だったが、サダトの主張は「エジプト第一主義」であった。この行為により、アラブの名手だったエジプトはアラブ諸国に断交された。エジプトは孤立し、アラブ世界の援助が激減し、代わりにアメリカの援助が急増した。このエジプトが抜けたことにより、中東での軍事バランスが失われイスラエル一国の圧倒的な軍事力のみが特出することとなった。エジプト抜きでは、アラブ側は戦争と言う選択肢を行使することは不可能だった。代わりに、イスラエルはエジプトを警戒する必要が無くなり、兵力(武力)を他の国境に回すことができるようになったのである。2010年に民主化運動の「アラブの春」が始まり、2011年にエジプト(とチュニジア)の独裁政権は倒れた。エジプトでデモが大規模になっても、出動した警察や軍は発泡せず、体制が倒れた。
②シリア
シリアからの内戦は、世界中(特にヨーロッパ)の関心事となっている。大量の難民が、自国に流れてくるのだから。シリアで、いったい何が起こっているのだろうか?
シリアを語るには、アサド大統領を抜きにしては語れない。彼は、イスラムでの1割程度の貧しい少数派アラウィ―の出身者である。希望する医学部に進む資金はなく、士官学校に進みパイロットとなる。訓練を受けるためにエジプトのカイロに渡るが、その時にナセルのアラブ民族主義が燃え上がるのに触れた。その後の詳細は省くが、紆余曲折の末、彼はシリアの大統領となる。アサドは彼の軍事委員会のライバルを粛正し、秘密警察により国民を監視し徹底的な弾圧を行った。スンニー派が蜂起したハマ市は鎮圧されたのみならず都市部の街そのものがブルドーザーで平坦にされた。死者と収監された政治犯の数は、1万5千人に及ぶ。彼は国民の人気や指示を得て大統領になったわけでないので、少数派出身の大統領を維持するために恐怖政治を行った。アサドの死後はその息子が継いだが、支配体制は変わらなかった。シリアにも「アラブの春」の波が到来したが、エジプト軍は撃たなかったが、シリア軍は民衆に発砲し政権は倒れなかった。民衆が武装蜂起を始めた。こうして、シリアは2011年に「シリア内戦」に発展した。2014年に入ると、反政府勢力の一部が「イスラム国(IS)」成立を宣言した。詳細は省くが、IS運動が指示された背景には、アメリカ軍がイラク戦争時にスンニー派の若者を治安要員として雇ったが、アメリカ軍撤退後にシーア派の首相が彼らの大半を解雇してしまったことも背景にある。その不満の受け皿が、ISである。もう一つの要因が、内戦の相手である反アサド陣営が一枚岩でないことである。実はISの資金源である「石油の密輸出」の相手がシリア政府なのである。なので、シリア軍はISを本気で叩く気はなかった。ISはイラクの混乱とシリアの内戦で生まれたと言える。イスラエルにとっては、先が読めない状況である。交渉の前提となる安定した政権が、現在シリアに無いからである。
③ヨルダン
イスラエルとの戦争に完敗したアラブ諸国は、ナセルに変わる新しい顔を求めていた。そこにパレスチナ・ゲリラであり、指導者のヤセル・アラファトが登場した。前述したように、たった6日間でエジプト、シリア、ヨルダンを壊滅させたイスラエル軍を、この「ファタハ」と言うパレスチナ・ゲリラは潰走させたのだ。実情はゲリラ側が3倍以上の犠牲者を出していたのだが、イスラエル軍を敗走させたと言う事実は、アラファトの人気を押し上げた。ゲリラへの志願者が、ファタハに殺到した。後に、アラファトはPLO(パレスチナ解放機構)の議長に就任した。PLOは様々な組織の集合体だが、彼が議長となったのはファタハが最大派閥で集金能力が最も高かったからである。
パレスチナ・ゲリラはイスラエルに対する攻撃拠点が実用だが、エジプトとシリアは自国の使用を許さなかった。強国イスラエルとの全面戦争を避けたかったからである。しかし、国力の弱いヨルダンとレバノンでは、ゲリラは自由に活動した。そもそもヨルダンの国民の半数以上は、難民となったパレスチナ人である。政府もゲリラに遠慮した政策を取らざるを得なかった。が、イスラエルは報復として、ヨルダン国内のゲリラの軍事基地を攻撃し始めた。ゲリラ組織PFLPの指導者がヨルダン王政を打倒も掲げてから、ついにヨルダンのフセイン国王もパレスチナ・ゲリラに対して戦争を開始した。劣勢にたったゲリラを応援するためにシリア軍がヨルダンに侵攻したが、アメリカ軍が空母部隊を派遣し、イスラエル軍がシリアと交戦する構えを見せてシリア軍は撤退した。ヨルダン正規軍になすすべもなく、ゲリラはヨルダンを撤退しレバノンに移動した。
④レバノン
レバノン。これだけニュースに登場する割には、日本人には今一つピンと来ない国かもしれない。かつては、オスマントルコ帝国の領土だったが、第一次世界大戦後にシリアと共にフランスの支配下に入る。元々シリアと結びつきの強い国だったが、それぞれ分離した形で独立。「生きた宗教の博物館」と言われるように、キリスト教、イスラム教の様々な宗派が混在した社会構造。歴史的に、迫害された少数の者たちが、レバノンの山岳地帯に住み着いてきた経緯があるので。
この混在した多種の宗派のバランスが大きく崩れる事態が訪れる。ヨルダンから追い出されたPLOのゲリラたちが乗り込んできたのあでる。レバノン政府はPLOを歓迎した訳ではないが、PLOを排除する力はとても無い。PLOは、レバノンで独立国家の様に振る舞った。そこに、シリアのアサド大統領が介入してきた。レバノンに自分の影響力が及ばない政権が誕生するのを嫌ったためだ。アサドは、PLOとイスラム教徒軍の勝利を阻んで、少数派のキリスト教徒に味方したがキリスト教徒に勝利を与える気など毛頭なかった。
レバノン全域を手中に収められなかったが、PLOはシリアを脅かさない程度に自由に動き回り、レバノン南部を制圧してファハタ・ランドを築き上げた。ここから、イスラエルを攻撃するために出動した。当然、イスラエルの報復が始まった。レバノン南部のシーア派にとって、イスラエル軍を連れて来るPLOは厄介な存在だった。イスラエル軍は国境を超えて北上し、破竹の勢いでファハタ・ランドのゲリラを一蹴しベイルート郊外に迫った。シーア派は、イスラエル軍を歓迎した。アラブ国家の首都が砲撃を受けても、アラブ諸国はどこも動かなかった。このギリギリのラインでアメリカによる調停が成立して、アラファト以下1万4千名のゲリラはチュニジアの首都チュニスに向かった。ヨルダン⇒レバノン⇒チュニジアと言う、再再再亡命である。PLO退去に当たり、イスラエルは非戦闘員の安全を保証したが、パレスチナ人の難民キャンプのサブラとシャティラで800余名の住民が虐殺された。実際に手を下したのは、イスラエルと協力関係にあったキリスト教徒の軍だったが、イスラエル軍支配下で起こった虐殺である。イスラエルは、レバノンのキリスト教勢力と条約を結んでレバノン内戦をイスラエルの力で抑え込もうとしたが、シーア派の反発を招き、自爆の殉教攻撃が始まった。この自爆攻撃で最終的に518名の死者が出た時点で、イスラエルのペギン首相は辞任した。
⑤ロシア(旧ソ連)
旧ソ連(ロシア)も中東情勢とは縁が切っても切れない。イスラエルを脅かすほどエジプト軍が強くなることが懸念されて、アメリカやイギリスやフランスからの軍事援助を受けられなかった時、ソ連はエジプトに兵器を輸出した。ソ連にとっての中東進出の足掛かりである。
ゴルバチョフが登場しペレストロイカにより東西冷戦が終結すると、パレスチナ問題に別の大きな影を投げ掛けた。言論の自由の規制が進むと、経済混乱と共にロシア民族主義が高まり、反ユダヤ感情が表面化し、ユダヤ人をソ連から締め出す力として働いた。ソ連政府は、ユダヤ人に関して自由な出国を認めた。ユダヤ人の多くは、イスラエルを目指さずアメリカンドリームのアメリカを目指した。イスラエルは、このメカニズムに変更を試みた。親イスラエルのロビー活動で法律の修正を狙い、結果移民法が改正されてアメリカへの移住が困難になった。ソ連からのユダヤ人の流れは、イスラエルへと変わった。2010年までに、100万人のユダヤ人がイスラエルに移住した。増大するユダヤ人の脅威…具体的には占領地の入植や水源の略奪…に、インティファーダ(民衆蜂起)につながっていく。ゴルバチョフの国内改革が、パレスチナに直接の大きな影響を与えたのである。
⑥アメリカ
パレスチナ問題で間違いなく最も大きな影響力を持っているのがアメリカである。そもそも、アメリカの先端の兵器が無ければ、イスラエルの圧倒的な軍事的優位は有り得なかった。実は、アメリカの中東政策とイスラエル政策は大きく矛盾してきた。冷戦期のアメリカの政策には、3つの目標があった。ソ連の中東進出の阻止、石油の確保、イスラエルの安全保障の3つである。しかしこれは矛盾していた。イスラエルに肩入れするアメリカは、イスラエルと対立する石油産出国のアラブには評判が悪かったからである。アラブ側との親密化が求められたのに、イスラエルとの関係がそれを妨げた。では何故、そのような矛盾したイスラエル政策を取らざるを得なかったのだろうか?
2002年の本文でも述べたように、アメリカに住むユダヤ人票の力が大きな力となっているからである。この事は、イスラエル建国のための多数派工作の背景でも述べた。実は、アメリカに住むユダヤ人の数は3億の総人口の2%にも満たない。なぜ2%の彼らの影響力が、そこまで大きいのか?
まず、投票率の低さからユダヤ人の票は4%の重みをもっていること。下院議員の比率は約6%で、上院議員では11%にもなる。わずか2%のユダヤ人がこれだけの政治力を持っているのである。
第二に、これはユダヤ人の教育水準の高さに起因していると言う事。ジャーナリスト、評論家、研究者、大学教員などを多く輩出し、経済的な成功を収めている者も多い。"ニューヨーク・タイムズ"や"ワシントン・ポスト"などのメジャー新聞も、ユダヤ人が所有している。そして、ユダヤ系市民たちは、その経済力をイスラエルのために使っているのである。クリントン元大統領やオバマ前大統領も、早々にユダヤ人指示と政治資金を受ける。代々民主党議員はユダヤ票の指示を得ている。ビル・クリントンが最初の大統領選挙で集めた政治資金のうち個人献金の4割がユダヤ市民からのものであった。相手を攻撃するテレビ広告をどれだけ買えるのかが勝負の分かれ目なのであり、ユダヤ資金は選挙戦早々に恩を売っておくのである。少数の熱烈なイスラエル支持者が、アメリカの中東政策を引っ張れるのである。
では、ユダヤ票にバックアップされた民主党でなく、共和党政権になった場合はどうなのだろう?実は、共和党の支援者には保守的なキリスト教原理主義勢力がついている。彼らもまたイスラエル支持勢力なのである。ブッシュ大統領(息子の方)は、このキリスト教原理主義勢力の指示を受けて大統領に当選している。民主党、共和党、いずれにしても、イスラエル支持なのである。
では、アメリカにイスラエルに批判的な勢力はないのであろうか?この本では、「Jストリ-ト」と言う団体が2008年に発足したと書かれている。ユダヤ人のロビー活動団体なのだが、旧来のユダヤ人組織と違うのは、無批判にイスラエルの肯定するのではなく、イスラエルの支持を示す一方でイスラエルの政策に批判的である。パレスチナ問題を平和的に収拾するため、ガザ地区とヨルダン川西岸でのパレスチナ国家樹立を主張している。まだ既存のユダヤ・ロビー組織よりも規模も資金力も小さいのだが、この組織がどう育っていくのかが重要な鍵を握っているかもしれない。
⑦イスラエル
正にパレスチナ問題の核心、中心地、1丁目1番地がこのイスラエルな訳だが、イスラエルの首相や大物政治家は一部の例外を除き、基本、軍功を立てたバリバリの元軍人である。故ラビン首相は1967年の戦争時の参謀総長。独眼のダヤン将軍は、亡くなるまでイスラエル政界の大物。リクード党の党首のシャロンは、1973年の戦争時に戦局を逆転させた英雄で後の首相。彼らは労働党であり、常に内閣を組織してきた。アメリカのジミー・カーターはそれまでの"最終的な和平の着地点が分からない"「ステップ・バイ・ステップ方式」の代わりに「包括的和平案」を提案した。ところがイスラエルの労働党が大敗して、ベギン率いるリクードに政権が変わった。1973年の第四次中東戦争でイスラエル兵側に多数の死傷者が出たためで、政府に対するイスラエル国民の不満と危機感の結果である。ベギンの率いるリクルードの考えは、「ユダヤもサマリアもガザも神の賜物であり、放棄する権利はない」というものだった。PLOは認めない。パレスチナ国家は許さない。占領地のユダヤ化への加速。妥協する余地はまったくなかった。これは、カーター政権の和平構想の死を意味した。実は、こうした背景の中で行われたのが(エジプトの所で述べた)"キャンプデービッドの合意"だったのである。この合意に「パレスチナ人の自治についての交渉」が含まれていたのであるが「交渉をする」と言っているだけで、最初からパレスチナに自治を与える気などさらさらないのは明白である。そしてエジプトは、孤立してしまったのである。エジプトがアラブから孤立した結果、ベギンは他の占領地に対して圧倒的な軍事力を示すことができるようになった。そして(レバノンで記述したように)、実際にベギン政権はその力を行使してレバノン戦争に突入して破竹の勢いで侵攻したのである。ベギンの後、リクードのシャミル、労働党のペレス、再びシャミルと続き、ラビンやシャロンへと続く。ラビンやシャロンについては、パレスチナのところで後述する。現首相のネタニヤフに触れておくと(現在第3次政権)、彼の公約は、「ゴラン高原から撤退しない」「パレスチナ占領地での入植は止めない」「パレスチナ国家は認めない」「エルサレムは永遠にユダヤ国家の首都であるので交渉の対象としない」のないない尽くしである。和平の交渉の余地など無いのである。
⑧パレスチナ
イスラエルのラビン首相とPLOのアラファト議長は、1993年にノルウェーで「オスロ合意」を交わした。
アラファトは、湾岸戦争により資金源が断たれてしまった。イラクのフセインと言う負け馬にかけてしまった結果、アラブの君主達の怒りを買ってしまったことが原因である。ゲリラ家族への遺族年金も払えなくなった。アラファトは新たな資金源、国際社会からの大規模な援助が必要だった。アラファトは、早急に和平を求めた。
一方のラビンは、第一次中東戦争で軍功を挙げ、また参謀総長を務めた英雄である。その彼の戦争を戦った経験、銃弾をくぐった重みが無かったら、PLOとの合意など不可能だったかもしれない。ラビンの苦悩と変遷をイスラエル国民が共有していたから可能だった。ラビンは、パレスチナで投石などの反対運動が起こった際、石を投げる手をへし折るように命令を軍に出した男である。しかし抵抗運動は続き、男を逮捕しても子供が石を投げ続けた。力では、パレスチナを押さえることができないと言うことをラビンは学び、それが和平交渉へと突き動かした。
オスロ合意の内容は、イスラエルとPLOの相互承認、ガザ地区とエリコでのパレスチナ人による自治の開始である。しかし国境線の最終的な確定などは全て将来の交渉に委ねられた。しかし、イスラエルは合意はするが、結果は約束しない。キャンプ・デービット以来のやり方である。交渉するとは言っているが、結果は何も約束されていなかった。1995年にラビンは暗殺された。
2000年7月にはクリントン大統領の仲介で、イスラエルのバラク首相とPLOもアラファト議長の間で首脳会談が開かれたが、交渉は決裂した。この和平決裂が怒りとなって、ハマースなどの急進派が勢力を広げた。社会のイスラム化は、中東各地に広がった。パレスチナ人は再びインティファーダに訴えた。シャロン将軍が首相に就任すると、パレスチナ自治区を再占領してインティファーダを押さえ込んだ。こうした状況で、2004年にアラファトは亡くなった。
オスロ合意から20年以上経つが、何も解決されていない。イスラエルが占領した地には、多くの入植地が作られてしまっている。エルサレムの帰属問題も解決されていない。貴重な水(水源)の問題も残されたままである。そして何よりも、故郷を追われ、未だに故郷に帰ることができず難民としてパレスチナに生活していると言う事実である。
以下は、私の個人的な思いである。
極力公平に考えようとしても無理である。世界中に自国主義の右傾化の波が押し寄せていて、熱狂的で偏狭な愛国主義が各国を襲っている、そういう時代であることを差し引いて100歩譲っても、このイスラエルのパレスチナに対する仕打ちの歴史は酷いと言わざるを得ない。到底イスラエルが"是"であると肯定できない。故郷を追い出され故郷の土を踏めないパレスチナの人々の長年の思いは、どこにぶつければ良いのか。イスラエルには、慈悲の文字すらないのか?
イスラエル建国には、超大国アメリカが背後で陰日向に力を振るった。しかし、この追い詰められた弱きパレスチナの人々を救う大国がないばかりか、同胞であったはずのアラブ諸国も手をさし伸ばさず傍観しているのが現実である。秘密作戦で数々の勲章を受けイスラエル軍の参謀総長となり後にイスラエルの首相となったバラクですら「自分がパレスチナ人だったらテロリストになるだろう」と言ってしまうくらいに、パレスチナ占領地の状況は悪い。そんな状況が、もう長年続いているのである。最後に、パレスチナの歌手アマール・ハサンの言葉で、この追記を締める。
「占領は石を投げる子供を怖がりません。占領が恐れるのは科学者です。知識人です。パレスチナの人々の人間性を反映するし、メッセージを発するからです。子供たちを教育しましょう。子供たちの心に人間性の種を蒔きましょう」。
2018年5月22日追記:「僕の村は壁で囲まれた・パレスティナに生きる子どもたち(高橋真樹著/現代書館)」を読んで
新品価格
¥1,620から
(2018/5/22 20:11時点)
上記の文章で細かく書いているので、ここではイスラエルとパレスティナの歴史は省略するが、一言で簡潔に説明すると「自分の国に他国からぞろぞろと人が大勢やって来て、『ここは俺たちの国だ』と勝手に建国して、圧倒的な武力で元々住んでいた人を殺したり追い出した」と言うことです。それは70年前に起こったことですが、半世紀以上に渡ってその鬼畜とも言える非人道的な行いがパレスティナに住む人々に行われています。
家は勝手にブルドーザーで壊され、新たに家を建てることも認められず、理由も分からず子どもが逮捕されて連れて行かれ拘留され何か月も何年も帰ってこない。居住地の周りには壁が立てられ、検問所から出ることも難しい。以下、本書から一部言葉を借ります。
これらは、重大な人権侵害であり、国際法違反です。イスラエルと言う国家がパレスティナに行ってきたことは、「ホロコースト」や「アパルトヘイト」と同じ人類史上の大犯罪行為です。ナチスドイツが行ったホロコーストの真相が明らかになった時、世界の人々は「こんなにひどいことが起こっているなんて知らなかった」と考えました。けれども現在パレスティナで起きていることは、知る努力さえすれば誰でもわかる事です。
2019年2月20日追記:「アラブ、祈りとしての文学(岡真理著/みすず書房)」を読んで
新品価格
¥3,240から
(2019/3/31 17:07時点)
文学は、戦争や弾圧に対して何ができるのか?
今頭に銃口を突きつけられている人に対して、打ち込まれてくるミサイルに対して、飢餓で今まさに命を失おうとしている子供に対して、文学は何ら阻止する力を持っていません。この問いは、音楽や絵画などアート全般に同様なことが言えます。
しかし、もし誰かが書かなかったらば、記録しなかったならば、惨劇を引き起こした者たちの大義名分や彼らの正義だけが歴史に残り、多くの惨劇の被害者たちの歴史は、当事者たちの命や記憶と共に消え去ってしまうのです。
パレスチナの地に、イスラエルの国家を建国する案は、当初、国連での多数決に必要な2/3を得られなかったのですが、ユダヤ票に後押しされたアメリカの熾烈な多数派工作により、1947年11月の総会で、パレスチナ分割決議案が可決され、ユダヤ人シオニストは即日イスラエル国家設立を宣言した。
このイスラエル建国は、現地のパレスチナ住民の主権を侵害した不当なものであったことは言うまでもない。しかも、当時パレスチナのユダヤ人人口は31%で、かつ当時6%しか土地を所有していなかったユダヤ人に割り当てられた面積は50%以上を締めていたのである。
そしてイスラエルは「民族浄化」を開始し、1948年に80万人ものパレスチナ人が難民となった。国連総会は、イスラエル建国によって難民となったパレスチナ人の即時帰還の権利を確認したが、イスラエルは難民の帰還を阻止するために500以上の村を破壊し、帰還の権利を否認し続けている。
虐殺によって失われた多くの命、追われた故郷、破壊された家や果樹、奪われた土地や畑、損なわれた人間としての尊厳。これを、誰かが書かなければ、イスラエル側のシオニスト史観による一方的な歴史しか残らないのだ。
この本は、アラブ人作家らのそれぞれ作品を本質を突きながら、丁寧に解説してくれます。
2019年3月30日追記:「ホロコーストからガザへ(パレスチナの政治経済学)」(サラ・ロイ著/青土社)を読んで
新品価格
¥2,808から
(2019/3/31 17:06時点)
著者のサラ・ロイはユダヤ人で、政治経済学が専門のハーバード大学の中東研究所の上級職員。彼女の親族や家族はナチスのホロコーストで100人以上が亡くなり彼女の父は、15万人が殺害されたポーランド内の絶滅収容所を生き延びた僅か4人のうちの一人。戦後、彼女の母は多様性と寛容な社会での人生を求めてアメリカに渡ったが、彼女の叔母は自らの安全を求めてユダヤ人だけの国家に邁進するイスラエルに渡った。
サラはユダヤ人でありながら、彼女の詳細な研究はイスラエルのパレスチナ(とりわけガザ)に対する過酷な占領政策を、特にオスロ合意以降の「和平」と言う言葉とは程遠い現実を、世界に伝えます。
サラが、パレスチナの現地調査で目にしたものは、かつてユダヤ人がホロコーストで経験したのと同じような人間性を否定&破壊する恐ろしいものでした。
彼女が現地で最初に見たのは、イスラエル兵が現地の孫を連れた老人を怒鳴りつけて、ロバの尻にキスさせると言うものでした。老人は拒絶しますが、兵士は怒鳴り続けると、孫がヒステリックに泣き始め、老人はロバの尻にキスしました。兵士たちは、大笑いしながら去っていきました。
ある時は、パレスチナの青年が、イスラエルの兵士に命令されて、4つんばいにさせられて犬のように吠えさせられていました。ある時は、妊婦が兵士たちにお腹を蹴られまくるという光景でした。ユダヤ人であるサラも、恐怖でただそれを見ているしかなかったそうです。人間の尊厳をここまで否定するこのような行為が、日常的に行われているのです。
今に至るまで、イスラエルは、パレスチナの土地を奪い、家や畑を破壊し、壁で地域を分断し、水も電気も燃料も仕事も奪い、子どもを誘拐し、武器を持たぬ一般人をまるでゲームのように狙撃し続けているのです。
ホロコーストを経験したユダヤ人が、なぜこんな非道なことを続けられるのか?極右なイスラエルの人々は、そもそもホロコーストに甘んじた弱いユダヤ人を軽蔑の眼差しで見ているのです。はっきり分かっているのは、建国以来彼らの悲願は、パレステチナの人々を殲滅して、強力なユダヤ人だけの国家を作る事なのです。これは、サラの叔母の側の「シオニスト」の立場で、サラの母側が取った「ジュダイズムの寛容」の社会とは相いれぬものなのです。イスラエルにもパレスチナの情報は入りますが、国民の多くは自分たちの国が悪魔のような所業をしていると言うような都合の悪い事は、そもそも見たくないのです。見てみぬふりか、無関心なのです。サラのような事実を伝えるユダヤ人は、イスラエルでは裏切者扱いで邪魔者なのです。(この手の事は、日本も含め極右化しつつある全世界の傾向かもしれません)。
この本の内容全ては書ききれませんが、サラのこの研究は、間違いなくパレスチナに対するイスラエルの占領政策の最も的確な研究と言えるでしょう。
2021年5月18日:→イスラエルの非人道行為に抗議します。
2023年12月25日:→ガザに平和を!
2024年5月15日追記:「現代詩手帖:パレスチナ詩アンソロジー」を読んで
イスラエルのガザ地区の民族浄化のため残虐な殲滅戦争が押し進められる中、パレスチナ人及び他国へ逃れているパレスチナの詩人達の詩を集めた特集。イスラエルに監視され、土地を奪われ、石を投げる子らは撃たれ、人として扱われず、ミサイルで多くの人が死んでいく。
銃で撃たれない、ミサイルが飛んでこない地に住む人々には決して理解が及ばない、悲しみ、嘆き、怒り、諦め、様々な思いが、詩に込められる。なぜ世界はこの残虐非道なイスラエルの行為に無関心でいられのか。パレスチナの「動物ではない人間」の声に耳を傾けよ。
2024年9月4日追記:ブエルタでのイスラエルへの抗議活動
現在、ガザで民族浄化を行い爆撃や飢餓で6万人以上を虐殺しているイスラエルへの抗議で、ブエルタに参加しているイスラエル・プレミアテックが抗議活動の的になっている。
第5ステージのチームTTでは、イスラエルのチームが進路妨害を受けた。そして11ステージでは大混乱となり、危険と判断した主催者がゴール3km手前でレース終了の決定を急遽下し、ステージ優勝者無しの異例の処置。
この抗議活動は、被害地域のパレスティナに対する心証を悪くしてしまい、対国際社会には逆効果となってしまった(汗)
UCIはロシアには毅然とした態度で臨んだのに、ジェノサイドを行っているイスラエルにはなぜか何もしない。イスラエルのチームには、このことで離脱を表明した選手もいる。 ガザとガザに住む友人を応援している1ロードレースファンとしてはとても残念です(涙)
2025年11月7日追記:イスラエル非難の輪がヨーロッパ各地のレースに広がり、イスラエルのスポンサーカナダのプレミアテックもチームから撤退を表明。
→詳細はこちら!
2025年11月20日追記:カナダ籍のプロチームであるイスラエル・プレミアテックは現地時刻の11月20日、チーム名を「NSNサイクリングチーム」に改め、スイス籍のチームとして再出発することを発表した。
詳細はこちら!