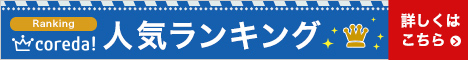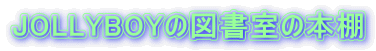入口 >トップメニュー >図書室の本棚目次 >現ページ
読書履歴 2019年1月~12月 (2019年12月24日更新)
2018年春4月から、自分の忘備録も兼ねて、読書の履歴を残すこととしました。2019年の読書履歴。
2019年12月に読んだ本
毎年12月は、なかなか本が読めないんだけど、今年もやはり読めませんでした・・・漫画すら読めず(笑)。
★百花繚乱 日本クリスチャン・ペンクラブ関東
21人のクリスチャンの自分史。色んな教派のクリスチャンが集うペンクラブ(関東)の方々が書いている。
戦争の体験、病気や挫折などの経験、愛する人々とのこの世での別れなどの悲しみや苦しみを通して、主に出会い救いの喜びを得ていく。人の一生はとうてい数ページなどでは書き記せないが、その中でも文章で語られるその人の人生が、読む者にリアルに迫ってきます。
★塩野七生「ローマ人の物語」スペシャルガイドブック 新潮社出版企画部編
けっこう分厚い、本格的な「ローマ人の物語」のガイドブックで、ローマの「創成期」から「滅亡」までの全巻を網羅している。
塩野さん、徹頭徹尾一神教が嫌いで、特にキリスト教が大嫌い。まだ歴史にキリスト教が登場するずっと以前の段階の巻から、何故かキリスト教をこき下ろす。そこ、ローマ史と関係ないやん。前にも書いたけど、塩野さんが一神教が嫌いで多神教が好きなのは、その信仰心によるものではない。一神教は神の下に人間が置かれて神を制御不可なのに対して、多神教は自分の環境や好みに合わせて神を取捨選択、つまりチョイスできる、人間のコントロール下に神をおけると言う考えが前提としてある。塩野さんは、それを寛容と考えているらしい(汗)。この本のロングインタビューの中でも、ご自身は通常は「反キリスト教」である事をしっかり自覚されていた。塩野さんの、寛容って何なんだろう?
塩野さんは、度々「寛容」と言う言葉を使うが、自分が好きな人物については、歴史上の事績について徹底的に高評価で書くが、気に食わない人物については超否定的に書く。読めば、それがはっきり分かります。まあ歴史学者ではなく小説家なのだから、仕方ないですけどね。塩野さんの、寛容って何なんだろう?
宗教、哲学、歴史的価値観、人物評価など全てにおいて寛容や公平な評価はなく、全て自己基準を絶対化した評価なのです。まず自己価値観ありきで、お気に召さない記述は排除。塩野さんの本を読み始めてから、ずっと感じていた違和感はそこです。
「十字軍の物語」、「ギリシャ人の物語」を全巻読んで、「ローマ人の物語」も文庫版の16巻(パクスロマーナ)まで読んだ。なるべく私情を排除して客観視して読んできたけど、だがしかし「十字軍の物語」から「ローマ人の物語」に至るまでこれだけ長期間に渡って、一貫してキリスト教を否定され続けると流石に読むのが辛くて、実はもう「塩野さんの本は、これ以上読まなくても良いかなぁ~」と思っています。
2019年11月に読んだ本
★百人隊長物語 JOLLIUS BOYAPHUS著/ジョリウィス・ボヤフス著
この2ヶ月間はこの執筆に集中していたので、ほとんどこの文章(※205,920文字=400字詰原稿用紙515枚分)以外の本は読めなかった。この大量の文章の読み返しや推敲を重ねて、章によっては10回以上読んだ。
7週間かけて完成させた「百人隊長物語(Story of Centurion)」。ある一点に集中して物語が進んでいくのだけど、結果的に、戦争と平和、暴力と非暴力、法と無秩序、正義と不正、真実と虚偽、富と貧困、挑戦と断念、虚栄心と真実、光と陰、謙遜と傲慢、怒りと赦し、希望と絶望、友情と裏切り、慈悲と不寛容、愛と憎しみ、慈愛と無関心を描く物語となった。
10年かけて資料を探して、読んで、構想して、物語を組み立てて、PCで執筆。通常はシナリオ(脚本)から映像を作る仕事をしているんだけど、今回はその逆。物語の構成は完成していて、頭の中に画も出来上がっていて、それを文字に起こす作業でした。まだしばし、推敲作業は続きます。
★イランvsトランプ 高橋和夫著/PLUS新書
僕の読書ではお馴染みとなった、中東研究の第一人者であり放送大学名誉教授、高橋和夫さんの本。個人的に特に目新しい内容は無いが、再びアメリカやアジアや中東の関係を概観する旅となった。
大まかに言うと、
①トランプのエネルギー政策。シェール革命によって、アメリカはコストの安いエネルギーを供給できるようになった。中東やロシアに大打撃。環境問題なんか、知ったこっちゃねえ!
②アメリカのイスラム7か国からの入国禁止措置。でもね、アメリカで発生したテロリストは、これらのイスラム諸国から来た人達じゃないの。最もテロに関わった人数の多いサウジアラビアが規制対象国ではないのは、サウジマネーがアメリカに流れているのと、トランプと周辺の会社がサウジへ投資しているから。でも、アメリカ国民の一部は、ああトランプよくやったなんて思ってる。
③トランプ、エルサエムをイスラエルの首都認定しちゃった。国内外から批判を浴びてるけど、これはアメリカ国内のユダヤ票だけによるものではなく、原理主義的キリスト教の後押しもある。アメリカとイスラエル、もうやりたい放題。
てな事を踏まえて、トランプとイランの問題の話し。アジアの端っこの日本人からすると、イラクとイランが仲悪くて戦争をしたけど、「お互い中東のイスラム教徒同士が何で喧嘩するの?」って疑問に思う。でも、元々イランはペルシャ帝国で、イラクはアラブなのね。日本時は一まとめにアラブって思ってるけど、実は歴史や民族のベースが違うの。あと、シーア派とかスンニー派の宗教戦争って勘違いされるけど、これらの国の内紛とか戦争って、実質は権力闘争なのね。
中東全般について言えば、中東諸国は脱石油立国を目指しているけど、上手くいかない。サウジアラビアは実は、サウジ王家の国。脱石油化の過程で「もう、全部無料の時代は終わり!国民も働け!」って事にしたんだけど、「政治はサウジ王家が握ったままね」って、おい!国民も起こるわな。でも、強権。ジャーナリストも暗殺。アメリカのCIAは、サウジ王家のムハンマド王子がジャーナリスト殺害の糸を引いていたと結論づけているのに、トランプは知らん顔と決め込んでいる。
外交も強権で、イランやカタールと断交。そして、イエメンへの軍事的介入。本来イスラムの守護者であるサウジ王家は、何百万ものイスラム教徒を飢えさせて餓死線上をさまよわせている。
また、莫大なサウジマネーが、イランの反体制勢力へ流れ込む。莫大なサウジマネーはアメリカにも流れ込んでおり、シンクタンクはサウジ体制への批判論文は書かないし(書けないし)、アメリカ政府の右派要職者もサウジマネーが流れる反イラン政府組織側を支持する。
でイランに話を移すと、イスラエルはイランが嫌い。イランのお金が、パレスティナのイスラム組織ハマスに流れている。イスラエルを支援するアメリカも反イランで、オバマが必至に成し遂げた核合意を、トランプは一方的に破棄。種々の経済規制で、イランに追い込みをかける。イランは、どこに頼るのか?エネルギー問題でアメリカと敵対関係にあるロシアは、自国自身が石油輸出国なので頼れない。すると接近するのは、石油輸出国ではない中国となる。結果的にアメリカは、それぞれ独自の歴史的文化的なプライドを持つ「ペルシャ」と「中国」と言う国同士の接近に、イランを追いやっている。これは、東アジアにも大きな影響を与える事となろう。
無理矢理ざっくりとまとめたが、概観するとだいたいこんな感じである。
2019年10月に読んだ本
★ユダヤ古代誌5 フラウィウス・ヨセフス著 秦 剛平 訳/ちくま学芸文庫
ユダヤ古代誌6巻(ⅩⅧ巻からⅡⅩ巻)に引き続き、5巻を読みました。。
最初から最後まで、ユダヤのヘロデ王の事績と人生を追う巻でした・・・わざわざ読まなくても良かったかも(汗)。
ヘロデ王は、名誉欲(虚栄心)に憑りつかれたような男。ローマ皇帝や諸国の王、諸外国に対しては、大判振る舞いで大金を投じ、様々な建築物や公共施設を建築・整備して名声を得ようとする。町や劇場や闘技場も次々に建設する。今でいうオリンピックのような祭典も催し、剣闘士、猛獣、高価で珍しい物を集める。ローマに対する身の処し方も見事で、アントニウスが権勢を誇っている時には大金を湯水のように使いアントニウスの信頼を得て、アントニウスがカエサルに破れた途端、カエサルに上手く取り入り過分な接待をして、かつ大金を投入して信頼を得る。ユダヤで飢饉が起こった時は、私財を投げうってエジプトから食料を買い付けユダヤ市民に供給して人民の掌握を図る。だが、それもこれも全て「己が名誉」の虚栄心ために行っていることとヨセフスは見抜いている。彼は、大王として後世に名を残したいのだ。
ローマ帝国や諸外国に大金を大判振る舞いをしているのだから国庫は空になり、どこかにツケが来る。お金は、湯水のようには沸いてこない。そのツケは、ユダヤの自国に来る。ヘロデ王は、自国民にはとても厳しい。ヘロデ王に少しでも疑われた者は厳しく処罰され、資産も没収。ヘロデの放蕩の資金に充当される。ヘロデに反抗したり、ヘロデの王座を狙うと思われた者は、証拠があろうがなかろうが次々に殺されていく。妻であれ、実の子であれ、側近であれ、例外はない。陰謀と密告で覆われた権謀術数の渦巻くヘロデ周辺は、家族ですら安息の時はなかった。虚偽の密告で訴えられても拷問に耐えきって無実を訴えたまま死んだ者もいるが、多くは拷問に耐えきれず嘘の供述で逃れようとし、その虚偽の供述は更に多くの拷問の犠牲者を生んだ。ヘロデは虚栄心と猜疑心の塊で、批判的な言葉にはすぐに怒り狂い、その残忍性で手段を選ばない非情な暴力を発揮する。ユダヤ市民の多くは、彼を嫌っていた。市民の本当の気持ちを王に言上した信頼すべきヘロデの老兵すら、投獄の上、拷問を受けた。気が付けば、彼の周りには、本当に信頼できる家族も重臣も一人もいなくなっていた。全員、死んだからである。王権を脅かすと思われた優れた能力を持つ息子たちも全員殺され、権謀術数にたけた陰謀家である者たち…妹のサロメや一部の子(アルケラオスやアンティパスやフィリッポス)ら…だけが生き残った。
死期の近づいたヘロデ王は、ユダヤ各地から多くのユダヤ人を強制的に闘技場に集めた。ヘロデは市民から嫌われていることを知っていたので、「市民が悲しみの喪に服さず喜ぶだろう」ことぐらいのことは予想していたので、闘技場に集めた数万人を全員虐殺するよう、サロメとアレクサス(アルケラオス)に言い残して遂に死んだ。ヘロデの死を悲しまないなら、強制的にユダヤ市民が悲しむように仕向けるためである。流石に陰険な策謀家であるサロメ達でも、その残虐すぎる遺言は実行せず、闘技場の市民たちをそれぞれの故郷へ帰した。
結局、アルケラオスはローマ側に王として認められず、ユダヤ王国の領地は、アルケラオスとアンティパスとフィリッポスに分割され、彼らはその領主に納まった。能力がありかつ信頼に足る多くの指導者達がヘロデ王に一掃されてしまったことが、ユダヤ国家の滅亡と言う悲劇の一因にもなってしまうのであった…(前回読んだ6巻に続く)。
。
これを読んでいると、なんか日本の総理大臣を見ているようで、悲しい。オバマ大統領の時は彼を持ち上げ、トランプ大統領に交替となると、すぐさま彼を持ち上げて至れり尽くせりの接待をする。現代のローマ帝国たるアメリカが相手だし、そこまでは分からなくもない。だがしかし、アメリカに戦闘機や穀物で1兆円(!)以上の大金を注ぎ込む。諸外国にも、あっちにこっちに何百億円、何千億円を大判振る舞い。そのお金の出所は、さてどこですか?国内では、イエスマンたるお友達を周辺に配し、関係団体には大判振る舞い。大企業や官僚は守る。諸外国に大判振る舞いの一方で、「国内の災害」には超出し渋り、「年金の財源が無い」と言っては税率を上げ、国民を更に苦しめる。国会だろうが遊説先だろうが、自分に気に食わない発言をした連中たちにはすぐさま怒って、度量の無さを公に晒す。国民の望みと関係なく、「自分の悲願を達成し後世に名を残したい」と言う虚栄心の塊のような政治活動の日々。
ヘロデの人生を読んで、「虚栄心に捕らわれた権力亡者とはいつの世もこんなものか」と思わされました。ヘロデ大王は、確かに歴史に名を残しました・・・たいへん悪い意味において(笑)。
★ローマ人の物語・パクスロマーナ 14巻~16巻(上・中巻・下巻) 塩野七生著/新潮文庫
ユリウス・カエサル亡き後、彼の意志を継いだのがオクタヴィアヌスだった。彼は、その若い実力を認められてカエサルの養子となって、遺言で後継者に指名されていたが、カエサルの暗殺と言う予想外の出来事で、公の場に適正年齢に達する前の10代で引き出されてしまった。
当時の誰もが思った。「オクタヴィアヌスって誰?」。カエサル自身が選んだ人物とは言え、誰も知らない(笑)。「何者?」。
オクタヴィアヌスにはカエサルのような天才的な頭脳もなければ、軍事に秀でている訳でもなく、体も虚弱だったが、カエサルの理想を引き継ぐだけの賢明さと意志力はあった。彼は「ローマを共和制の戻す」と宣言して元老院を喜ばせたが、実際には逆の事を行っていく。ローマの神君となった「ユリウス」の名を継ぎ、元老院から「アウグストゥス(尊厳なる者)」の尊称を受けた。それ自体には、武力や権力を想像させる意味は全くない…権力は持たなかったが、人々からの尊敬は得た。彼はまた、「プリンチェプス(第一人者)」と言う称号も得る。市民中の第一人者や指導者のような意味合いである。これも、何ら権力を伴うものではなかった。
時代や文化が違うので日本で例えると難しいのだが、「国民栄誉賞」とでも言ったら良いか。例えば、国民栄誉賞を得た王貞治氏は権力は持たないが、国民からの尊敬を受けている…そんな感じに近いだろうか?
そのような訳で、オクタヴィアヌスの正式名称は「インペラトール・ユリウス・カエサル・アウグストゥス」となった。エンペラー(皇帝)の語源であるインペラトールであるが、そもそもの意味合いは、元老院よりインペリウム(命令権)を付与された者の意味で、後にローマ軍の司令官を意味する言葉となったが、凱旋将軍はその後も任期中に限りインペラトールを名乗ることができたが、アウグストゥスもそれを名乗ることができた。なので、そもそもの意味は「皇帝」でもなんでもなく尊称名の一つに過ぎなかった。ユリウスもカエサルも引き継いだ名前でしかないし、プリンチェプスにもインペラトールもアウグストゥスも権力を待たない単なる尊称名でしかなかったが、それらを持つ意味合いをオクタヴィアヌスは知っていた。
オクタヴィアヌスが狡猾だったのは、その先である。彼は、自ら最高権力を持つ執政官を辞任したのである。共和制を信奉する元老院の貴族達は、これに感激した。彼らの目には、自分たちで執政官を選ぶことができる共和制への更なる復帰と映ったからである。オクタヴィアヌスは、ささやかで謙虚な願いとして「護民官特権」を与えられるよう願って認められた。市民の代表で市民を守る立場の護民官は平民出身でなければなれないが、オクタヴィアヌスは特権としてこれを認められた。ここに彼の周到な計算があった。護民官は、肉体の不可侵(暗殺などをされない)の権利や、政策立案の権利を持っていただけでなく、元老院に対して拒否権を持っていたのである。例え元老院が法案を立案しても、護民官はそれを拒否する権利があった。こうして、「ローマを共和制に戻す」と宣言したオクタヴィアヌスは、自らを「独裁官」や「皇帝」と名乗ること無しに、尊称名だけでなく、実質的な権力も手中に収めたのである。当時の多くの元老院は気が付かなかったが、「ローマ皇帝」の誕生である。
その後の彼の業績は長くなるので割愛するが、軍団の数も大幅に減らし、なるべく軍事に頼らずなるべく外交で物事を解決する方向に政治の舵を切り、ローマ帝国内のインフラ整備も着々と進めた。奔放で明るい性格で演説も文章も得意なカエサルとは違い、静かで真面目で(どちらかと言うと暗い)演説や文書も下手なオクタヴィアヌスだったが、公益のために律儀にコツコツ仕事を進めていった。幼少より胃腸系が病弱だったこともあり、美食とかの贅沢とは無縁の生活を送っていたためか短命ではなく、76歳まで生き静かに亡くなった。戦乱に明け暮れた時代は終わり、彼の真面目な日々の労苦によって「パクスロマーナ(ローマによる平和/安定と秩序)」がなった。カエサルの成したことは派手で天才的だが、その後のオクタヴィアヌスの業績はカエサルのように目立つことはないが、彼によってしか成し得ない偉業であった。
彼の欠点と言えば、人生半ばから軍団の最前線を視察せず「机上」の人であったことによる政策上のミスリード、それと後継者選びに「血縁」にこだわり過ぎたことであったことであろうか。カエサルの様に血縁にこだわらず、実力を見極めて後継者を指名していれば混乱も少なかったろうが、オクタヴィアヌスはそこにこだわったために、後にカリグラやネロと言った悪名高き皇帝たちが出現していくのであるが、その辺のことはきっと次巻以降で詳しく書かれているのでしょう。
★L’ESTERCITO ROMANO Ⅱ巻&Ⅲ巻 GIUSEPPE CASCARINO他著
かつてイタリア人の友人がプレゼントしてくれた、ローマ軍団についての研究の書であり辞典の再読。イタリア語が読めないので読破は時間的に無理なので、伊和・和伊辞典を駆使しながら必要な箇所だけ拾い読み。
2019年9月に読んだ本
★フラウィウス・ヨセフス伝 ミレー・アダス=ルベル著/東丸恭子訳/白水社
古代ローマやイスラエルの歴史を調べるにあたって、やはりヨセフスの著作は一度は読んでおかねばならない。ただし、ヨセフスの「ユダヤ戦記」を基にした著述などは過去何度か読んでいるので、エルサレム陥落やマサダ要塞壊滅の記事は何度か目の重複になる。
まずは、ヨセフスがどう云う歴史家であったか、その背景、記事の信憑性を知りたく、まずはこちらの伝記を読みました。
ヨセフスの個人名(本名)は知られていない。ユダヤの大祭司の家系であることは分かっているが、ヨセフスは家系名であり、フラウィウスはローマ皇帝ウェスパシアヌスの氏族名フラウィウスである(解放奴隷には氏族名が与えられた)。何故、彼がローマ皇帝の氏族名を持ち、後世まで伝えられる著作の歴史家になったのか、ざっくりまとめると次の様になります。
ローマ帝国の支配下になったユダヤ王国だが、ローマから送られた地方総督の暴虐や略奪が横行しそれが総督4代に渡って続く。66年、ついにユダヤの地で反ローマの狼煙が上がり蜂起した。叛徒達は、当時の駐留ローマ軍に勝利してしまい、ユダヤ対ローマの図式が決定的になる。ローマ帝国は、自軍の敗北をそのまま放置しておくことは絶対にない。選りすぐりの将軍と大軍団を送り込んでくることは必至。
若く治世にあふれたヨセフスは、人々から大きな期待を抱かれていた。ヨセフスは30歳と言う若さにも関わらず、エルサレム政府からガリラヤの総指揮官に任命される。その直前、ヨセフスは26歳~29歳の間にローマでの重要な使命を任命されていて、それを果たし終えたばかりなので、ローマ軍の組織力、訓練、装備、その強さをしっかり理解していた。寄せ集めのユダヤの兵士では、到底勝ち目がないことも悟っていた。まずは、ユダヤの寄せ集め兵士にローマ軍式の軍事訓練を施そうと目論むが、いかんせん時間が無い。ヨセフスには、もう一つ問題があった。ユダヤが一枚岩でなく、親ローマと反ローマに分かれていて、反ローマ勢力も何派にも分かれているのが現状で、ヨセフスはユダヤ内部での争いにも対処せねばならず、まさに各都市の説得や謀略阻止に東奔西走の日々であった。
ローマ帝国は、叩き上げの軍人総司令官ウェスパシアヌスとその子ティトゥスと大軍団をユダヤに送り、いよいよユダヤとの戦闘に進んでいく。途中の戦闘は割愛するが、67年7月20日、ヨセフスが守ったヨタパタは激戦の後に陥落する。ローマ兵は、ユダヤ人を次々に殺し、虐殺を免れたのは奴隷となる女と子どもだけだった。命令で、町は完全に破壊された。ヨセフスは町の有力者40名と共に洞窟に隠れたが、それもすぐに敵の知る所となる。ローマ軍は、通常は敵将を殺さない。ウェスパシアヌスはヨセフスの友人であるニカルノを用いて、敵の将軍であるヨセフスに投降を呼びかけるが、40人の仲間は自害を決意し、敵に投降しようとするヨセフスに剣を突きつける。しかし、ヨセフスは自分にはもっと大きな使命があると信じていたので、死ぬ気はなかった。彼は計略を用いた。くじ引きで、仲間は次々に味方同士で命を奪うが、最後にヨセフスは自害せず投降した。
その後、囚われの身となったヨセフスはウェスパシアヌスに向かって「ウェスパシアヌスはローマ皇帝になる」と予言をする。命を救われたヨセフスは、今度は外側(ローマの側)からユダヤが滅んでいくのを見る事になる。彼の視点は、ユダヤ側でなくローマ側へと変わる。
ネロ皇帝の自害後、軍に推された将軍達が次々に皇帝にのし上がるが、いぜれも政敵による暗殺や敗死、自害などで短命に終わる。ウェスパシアスは出自からいっても皇帝になるような家系ではなく、自らも叩き上げの軍人であることを認識していたが、軍団に推されて、またエジプトの後押しもあって、満を持して69年、ローマ皇帝になる。同年、ヨセフスは鎖から解かれ自由人となった。
ユダヤの都市は次々に陥落し、ついにエルサレム包囲となる。ウェスパシアヌスの子、ティトゥスが父の後を引き継ぎユダヤの平定に全力を注ぐ。ここに至ってもまだエルサレム内は、ゼーロータイやシカリオイなど3派が争って、互いに殺しあっている内乱状態だった。内輪で争っていて、どうして国が成り立つだろうか?ユダヤの過激分子には、ローマ軍のような秩序も訓練も軍規も設備もなく、勝てる要素がまったくなかった。ティトゥスに命じられて、ヨセフスはエルサレムの和平開城の説得に当たるが、彼はユダヤ全土で誰の目にも「裏切者」と写っていたので、誰一人聞き耳を持たず、罵倒されて石をぶつけられて気絶する始末だった。
エルサレムからローマ軍陣営に逃げてくる難民は、ローマ軍の外人傭兵に切り裂かれて(胃の中に隠した)金品を奪われ、次々に命を落としていった。一晩で2,000人の腹が切り裂かれた。このようない蛮行に対する指揮官ティトゥスの憤りと裏腹に、ローマ軍兵士も次第にそれも真似るようになったと言う。
その後、エルサレムの周囲7kmは、ローマ軍工兵により土塁で包囲されて誰も逃亡できないようになった。エルサレム内では飢餓が進行し、死者が多くなりすぎて、死体を次々に城壁から谷に落とすようになった。それを目撃した総司令官ティトゥスは、天に向かって両手を差し出し「これは私の仕業ではありません!」と言った。飢餓は極限まで達し、気がふれた女性が自分の乳児を食べる事態にまでなり、ティトゥスはこの時も自分の無実を神に誓った。ヨセフスは、多くの一般市民が追い詰められている地獄の様な状況でも、和平に応じようとしないエルサレムの指揮官達に怒りを向けた。ユダヤが滅ぶのはローマ帝国のせいではなく、ユダヤ人の不信仰のためであるとヨセフスは考えていた。
そして、エルサレムは激しい戦闘の後に陥落する。ローマ軍は降伏勧告に応じた敵に対しては寛容な態度で臨むが、降伏勧告を拒否して戦闘を選択した敵には容赦がない。虐殺と略奪が横行し、略奪に対する欲望が兵士たちを無慈悲な人間に変えた。虐殺し続け、略奪する対象が無くなってようやく兵士たちの手は止まった。ヨセフスの親しい友人たちの多くが死に絶え、彼の愛する美しいエルサレム神殿は徹底的に破壊された。
エルサレム陥落後は、他の要塞も次々に落ちて行き、難攻不落の天然の要塞マサダも遂に落ちてユダヤ戦役は終えた。戦い生き残ったユダヤ人の多くは奴隷となり、ある者は重労働に課され、ある者は各地の円型闘技場で獣と戦ったり拳闘試合で戦ったりして命を落としていった。
ローマ帝国は、皇帝となったウェスパシアヌスが、ネロ以降の皇帝のゴタゴタを終結させて政情を安定させ、その子ティトゥスが父の後を引き継いで皇帝となった。ヨセフスは、ウェスパシアヌスとティトゥスそれぞれの皇帝の加護の下、歴史家として著述をしていく。同胞のユダヤ人からは「裏切り者」と罵られ、ローマ人からも「不当に皇帝の庇護受ける者」と不快感を如実に示された。確かに彼の足跡を追っていくと、現代の我々の目からしても不快感を感じざるを得ない行動が多い。彼自身もそれを自覚していたのであろう…彼の晩年の著作は初期の物と比べて自己弁明が多く、歴史証言も「ユダヤ戦記」などの初期のものとなかり異なってしまい、歴史的信憑性は初期の方が高いようだ。
ただ一人生き残った者としての彼の悲しみや苦しみは、我々には知りようもない。ヨセフスが英雄となるためには、ヨタパタで勇猛果敢に戦って死ぬしかなかった。ただ一つ言えるのは、彼がそこで死んでいたら、これらの歴史の詳細は現代の我々は永遠に知る事はなかったと言う事である。
★ユダヤ古代誌6 フラウィウス・ヨセフス著 秦 剛平 訳/ちくま学芸文庫
ユダヤ古代誌は、日本では中古本でしか購入できない。僕は「本は買ってじっくり読みたい派」なんだけど、一番読みたい古代誌の18巻から20巻に相当する学芸文庫の6巻は、一番安い中古本ですら4,300円、高いものでは17,000円を超えるので購入はあきらめ、今回は図書館で借りた(汗)。通常の順序とは逆で、最後の6巻目から読み始める。
ヨセフスは、イエス・キリストが亡くなった数年後の37年生まれなので、まだ使徒やイエスの弟子たちが存命中にユダヤで若い頃を生きていたし、彼らに関わった人々なども多数存命中だった時代の人。いわば、その時代の生き証人。(18年から36年まで)カイアファスが大祭司だったこと、ポンティオス・ピラトスが(26年から36年まで)第5代総督だったことなどを、ヨセフスは証言する。ちなみに、ピラトスはサマリア人を大虐殺した事件で、サマリア評議会がシリアの知事ウォテリオスにピラトスを告発したので、ピラトスはウォテリオスの命令でローマ皇帝に釈明するためにローマへ向かった。こうして、ピラトスのユダヤでの滞在は10年で終えた。
ヘロデの家系はより詳細に書かれている。(紀元前4年に)ヘロデ王が亡くなった後、ゴタゴタの末にユダヤは3人の息子(アルケラオス、アンティパス、フィリッポス)に分割されたが、アンティパスはガリラヤの領主に任ぜられた。
領主となったアンティパスは、妻の父のアレタスの軍と戦う事になるが戦闘で敗北をきす。その戦闘に関する記述で、ヘロデ・アンティパスが善人の洗礼者ヨハンネス(=ヨハネ)を殺害したことが書かれ、アレタスとの戦いにヘロデ軍が敗れたのは、神の正義の復讐だと当時の中心的なユダヤ人々は考えていた、と述べている。ちなみに、アレタスとはアンティパスの妻の父であり、ヘロデ・アンティパスが義兄弟の妻ヘロディアに横恋慕してアレタスの娘を離縁して追い出しヘロディアと結婚する密約を結んだのだが、妻がそれを知って父アレタスに打ち明けたので戦争になったのであった。
ヘロデ王の死後、百年も経たずに、若干の例外を除きその子孫は全て断ってしまったとヨセフスは書き、ヘロデの家系とその後の子孫の経緯を詳細に書き記した。浪費家のアグリッパが(自ら蒔いた種々の)苦難から脱し、皇帝ガイオス(※悪名高きカリグラ帝のこと)のお墨付きで王としてローマからユダヤの領地に戻って来た時、ヘロディアはそれに嫉妬し、夫ヘロデに「あなたも王として認めてくれるよう」皇帝に訴えるべきだとそそのかした。ヘロデは静かな生活に満足していたし、ローマの争乱には関わりたくなく乗り気ではなかったが、ヘロディアの主張から結局逃れることはできなかった。それをみすみす見逃すアグリッパではなく、皇帝ガイオスに書簡と贈り物を送った。アグリッパの告発の結果、ヘロデは領地を取り上げられ、皇帝の怒りをかったヘロディアと共にガリアの地へ流刑となった。これがガリラヤの領主、ヘロデとヘロディアの哀れな末路である。
この巻には、イエス・キリストに関する記事もあるのだが、少なくとも記述の一部は後の時代に書き換えられたか、加筆されたと考える方が自然である。何故なら、大祭司の家系で最後までユダヤ教の教義にこだわり続けたヨセフスが、イエスを突然「クリストス=キリスト(救世主)」と書くわけがなく、記述全体の中で明らかにこの部分の違和感が特出しているからである。諸説あるが、ヨセフスの記事に、恐らく後のキリスト教徒が「救世主」や「復活」云々を書き加えたのではないかと、僕は思う。
皇帝ネロン(※やはり悪名高いネロ皇帝のこと)の時代、ユダヤの総督フェストスが亡くなった後、新たにアルピノスが送られた。その時、アルピノスが赴任する間に、サドカイ派に属する冷酷なユダヤの大祭司アナノスガが、イエスス(=イエスのこと)の弟ヤコボス(=ヤコブ)を処刑した記事も、ヨセフスは書いている。ちなみに大祭司アナノスは、その残虐な行為から3ヶ月で罷免されている。
この頃の大祭司は尊敬を受けるような人々でなく、王の政争の材料になっていて、頻繁に交替が起こっていた。ヘロデの時代からエルサレム陥落&神殿崩壊までの僅か107年の間に、大祭司の総数は28名にも上った。モーセの出エジプトからソロモンのエルサレム神殿建設までの612年間(ヨセフスは大祭司の継承からそう計算した)で13名の大祭司と比べると、当時のエルサレムがいかに異様な事態であったを理解できる。
その頃の大祭司は配下にごろつきのヤクザ者達を起き、一般の祭司が受け取るべき十分の一税を暴力で奪い取り、他に収入の道がない祭司が餓死するようにまでなっていたと言う。また、シカリオイ(=シカーリ党のこと)などの無頼漢の跋扈により、エルサレムでも略奪や誘拐や脅迫や殺人や金銭による請負暗殺などが横行していた。今でいう"反社会的勢力"の悪漢達が、何派も跋扈していくのである。ユダヤ教徒であるヨセフスですら、後のエルサレムのローマ軍による破滅は、このようなことごとく律法に反する無法者達に支配されたエルサレムが神に見捨てられて罰せられた当然の帰結であろうと結論づけている。そして、以降の記述は「ユダヤ戦記」に譲るとしている。
ユダヤ古代誌は、ユダヤに関わる歴史はもとより、他にも各ローマ皇帝のエピソードやその運命顛末を書き記していてとても興味深いし(しかもこれらの多くの記事は彼の生きた時代にリアルに起こっていた)、2000年も前の著作なのに歴史に興味のある人なら一気に読めます。ちなみに、この本の訳者解説と後書がとても長く、薄い文庫本並みの69ページもあります(笑)。
★ローマ人の物語・11巻~13巻(ユリウス・カエサル/ルビコン以降・上・中巻・下巻) 塩野七生著/新潮文庫
ユリウス・カエサル、遂に軍団と共にルビコン川を越えイタリアに渡る。「賽は投げられた」のである。ローマは、元老院及びポンペイウスとの内戦に突入した。突然のカエサル渡河により、ローマにいたポンペイウスは一旦ギリシャに移って軍備を整える。
一方のカエサルは、イタリアでの安全を確保して、ファルサルスの戦いで軍事力で上回るポンペイウス軍を、優れた戦術で破る。
ポンペイウスは逃亡したエジプトで、プトレマイオス13世の側近の計略で戦場で暗殺される。
北アフリカの元老院はも破り、元老院はの重鎮、小カトーを自害に追い込んだ。その後、荘厳な凱旋式を挙行した後、ヒスパニア(現スペイン)に逃れていた残党(ポンペイウスの遺児らの軍)をとの戦いに勝利して、内戦には終止符が打たれた。
カエサルは、ほころびだらけの機能不全の共和政の改革にようやく着手できるようになった。カエサルは、この改革のために終身独裁官の権力を手中にする。この絶対的な権力に、マルクス・ブルータスを始め、共和政主義者は危機感を抱く。
カエサルは、身の安全を保証する誓約を得た後、元老院会議に腹心も伴わずに会議に出席。その時、共和政主義者者達が隠し持っていた剣でカエサルを23ヶ所めった刺しにして暗殺した。「ブルータス、お前もか!」のブルータスとは、愛人の息子のブルータスの方でなく、カエサルが信頼していたマルクス・ブルータスの方である。
共和政主義者達は、カエサル暗殺で市民たちが自分を支持してくれるものと思っていたが、実際はその逆であった。市民たちは即座に扉を閉め、彼らを支持しなかった。暗殺に関わった者たちは、その後、カエサル軍団の軍団兵の仕返し(暗殺)を恐れて生きていくことなる。そして、彼らは皆非業の結末をそれぞれ迎えることとなるのである。
カエサルは死したが、彼の意思はオクタヴィアヌス…初代皇帝アウグストゥス…に引き継がれていくのである。
★痛快!ローマ学 塩野七生著/集英社
全部読んだけど、「ローマ人の物語」のエッセンスを詰め込んだダイジェスト本でした。「ローマ人の物語」を読んでいる人は、読む必要無し。
2019年8月に読んだ本
★古代ローマ軍団大百科 エイドリアン・ゴールズ・ワーシー著/池田裕・古畑正富・池田太郎訳/東洋書林
この大百科は、表紙の写真が派手なので、まるで「子ども用の図鑑」みたいですが、そうではありません。なんと、1万3千円もするれっきとした学術書です。エイドリアン・ゴールズ・ワーシーと言う古代ローマ軍史の専門家が書いた本です。
この本を読んだのはもう10年も前で、今回は再読です。なんで、こんな本を買ったかと言うと、ローマ軍団の百人隊長の物語を書くためです。実は、物語の骨子(あらすじ)自体は9年前に書き終えていて、今は物語の肉付けをしているところです。イタリア人の友人に、イタリアで購入したローマ軍団の学術書2冊もプレゼントしてもらったのも役立ちますし、今、読んでいるローマ人の物語も、時代の背景を探るのに役立つと思っています。
日本人のクリスチャンの私にしか書けない「百人隊長の物語」を仕上げることが、僕の人生の使命の一つなんじゃないかとすら思っています。このマイプロジェクトを開始してちょうど10年なので、時間を作って、そろそろ追い込みに入りたいと考えております。
★ローマ人の物語・9巻&10巻(ユリウス・カエサル/ルビコン以前・中巻・下巻) 塩野七生著/新潮文庫
昔「ルビコン川を渡る」と言う諺を聞いた時、「三途の川を渡る」ような意味に勘違いしていました(笑)。
10巻までは、ユリウスがガリアの地を平定するまでの話を描く。そして、次巻からいよいよユリウスが、超えてはならぬルビコン川を軍団と共に超えて、母国イタリアへと足を踏み入れる!
友人も書いていましたが、塩野さんの独善的な思想や歴史的な価値観や認識に付き合わせれるのに、少々疲れてきました。前回も書きましたが、自分が英雄視する登場人物にのみ読者の共感を導こうとする一方的な歴史的価値観の押し付け、一神教をこき下ろし多神教を持ち上げる宗教観(※厳密には宗教自体は信じていない)とか。まあ、塩野さんは歴史学者ではないので、娯楽小説として一歩引いて読んでます。
★キリスト者への問い/松谷好明著/一麦出版社
「あなたは天皇を誰と言うか?」この問いは、自分に向けられています。
本文より抜粋。「皇室神道、押しなべて神社神道は、『キリスト教やイスラム教のような排他的一神教ではなく、おおらかで寛容な宗教だ』とまことしやかに言う論者、政治家が後を絶たず、現在はそう言う人の声がますます大きくなっているように思われます。しかし、これほど歴史の事実に反することはありません。国家神道体制の国家は、「不敬罪」「治安維持法」「宗教団体法」などによって、キリスト教のみならず、ほぼすべての宗教と国民の思想の本来の姿を歪め、体制に反すると見た、大本教、天理教、ひとのみち(現PL)をはじめ多くの宗教団体、社会主義者たちを弾圧してきました。…(中略)…国民の思想・信教・良心の自由を奪ってきたと言うのが歴史の事実であり、今も現実にある可能性です」。「皇室神道は紛れもなく、特異な民族的宗教、日本的多神教です。世界の諸民族、諸国家に通ずる普遍性を全く持ちません」。抜粋、以上。
戦時中、日本のキリスト教会は、国家の思想統制に抗わうことができず「神社は宗教じゃないから参拝しなさい」とアジアの諸教会の兄弟姉妹に、強要することに協力しました。「非国民」と石を投げられるの恐れ、村八分にされるのを恐れ、特高に捕まるのを恐れ、ゼロ戦を作って奉納し、国家体制に完全に従属して、積極的に協力する大きな罪を犯しました。アジアの多くの信仰者が投獄され、命を奪われました。
今、洋の東西を問わず、右傾化・国粋主義化が進行及び蔓延していて「自分の国だけが正しい!」、「他の国々をぶっ壊せ!」とばかりのダークな空気が世界中の国々を覆っています。自分の国の体制を批判をする人々は、マスコミや政治屋や心無い市民から「非国民」と血祭りにあげられ、「死ね!」とばかりの卑劣な街宣活動やヘイトスピーチの的になり、時には本当に命の危険に晒されるのです。今、この問題を自分の問題として真剣に考えないと、手遅れになり、この国も世界も暗黒で覆われます。
2019年7月に読んだ本
7月は仕事が忙しく、あまり本は読めませんでした。
★ギリシャ人の物語3巻・新しき力/塩野七生著/新潮社
アテネはスパルタに敗北し、そのスパルタもかつての力を失っていき、ギリシャのポリス国家群は全て没落していく。
そのギリシャの北方で、新たな勢力マケドニア王国が力を持っていく。そう、あのアレキサンダー大王こと、アレクサンドロスの登場である。ギリシャの諸国家を配下においた後、少ない兵士を従えながら優れた戦略と戦術で、数倍~十倍ものペルシャの大軍を、次々に打ち破っていくアレクサンドロス。
後代のカルタゴのハンニバルや、ローマのスキピオやカエサルまで、過去「最も優れた武将」と敬意を払われることになるアレクサンドロス。
歴史でちょっと習うだけだったけど、知らない事ばかりだった。子供の頃、ギリシャの哲学者アリストテレスが先生で万物について学んでいたこと、一方でスパルタのレオニダス(300で有名なあの英雄の名前と同じだが別人)から仲間と共に武術も学ぶ。文武両道、厳しい訓練を積んでいく。この時の仲間が、アレクサンドロス死後、後継を巡って争うことになり、結果的に王国は4つに分かれることになるのだが・・・。
アレクサンドロスの死で、ギリシャ人の物語全3巻は完了。そして、塩野七生さんの生涯の全創作活動も終了。お疲れ様でした。
★ローマ人の物語・8巻(ユリウス・カエサル:ルビコン以前・上巻) 塩野七生著/新潮文庫
大国となったローマの物語は、スッラの大粛清から逃れた若き青年ユリウス・カエサルの物語に移る。この巻では、まだプレイボーイで借金だらけのユリウスについて触れるだけで、まだたいした活躍はなし。
なのだが、元老院での「カティリーナの陰謀」に関するユリウスの弁論は、その後の彼の考え方を示す弁論となる。まだ何も起こっていないカティリーナの謀略に関する弁論で、キケロや小カトーの弁論と、ユリウスの弁論は対極なものであった。
ユリウスは、ローマの過去の歴史も振り返り、ローマの寛容がローマを偉大にしたのであり、感情でなく理性と法に基づいて裁くべきとした。本来、正しい事をなすべき目的で作られた法律が、権力者の恣意的な使用で段々と罪なき人々まで殺すようになる危険性を説いた。現代日本ならば、正に「テロ防止法・共謀罪」の議論と同じものであり、ユリウスはこれに反対しているのだ。
一方の小カトー側は、国家への反逆でローマ市民を危険にさらすのだから関係者全員の死刑が当然であるとした。
元老院では、キケロや小カトー側の弁論が受け入れられ、キケロはヒーローになり、一方のユリウスは人々から袋叩きに合い、殴り殺しになるところを仲間に連れだされた。ここで死んでいたら、カエサルの物語はここで終わっていた。だが生き残り、物語は次巻に続くのである。
さて、塩野さんの本を「十字軍物語」全巻、「ギリシャ人の物語」全巻を読み終わり、そして現在「ローマ人の物語」を読んでいる最中なのだが、個人的に納得できない点が二つある。
その1:歴史認識に対する公平感の欠如。
塩野さんは歴史学者ではないから仕方ないとは思うんだけど、それぞれの人物に対する入れ込み方がまったく違う。
まあ、それが、塩野さんの本を分かりやすく、かつ面白くしているのは間違いないので、仕方ない面はあるのだが。 自分が好感を持つ人物の行為は全般的にYESで、好きでない人物に関してはNoの姿勢を貫く。No側の人物がなす殺戮や非道はこき下ろすが、Yes側の人物が非道な行いや殺戮をしても、それは仕方ない事として、さらっと流して彼らを弁護する。
また資料の無い事柄については、「推測」や「憶測」で押しメン達を弁護するやり方は、何と言うかネット右翼の論法に似ているのが、ちょっと納得できない点である。
その2:宗教に関する認識
読んだどの本でも、間違いなく次の宗教観で貫かれている。多神教はGoodでYes、一神教はBadでNo、と言う一貫した姿勢である。日本の八百万の神、ギリシャやローマの多神教の神はOK、ユダヤ教やキリスト教の一神教はNo Thanksなのである。
ただし、塩野さんは多神教の信仰を信じているとか、優れているからそれを「良し」としている訳ではない。多神教宗教は、人間の都合次第でどうにでもコントロールできる、つまり「神の言葉やお告げ」などを人間の支配下におけると言う認識で「良い」としているだけである。多神教は現実的であり、人間である時の権力者がそれを利用できると。一方で、一神教ではそれができない。人間が、神の下に置かれてしまう。一神教の宗教は、理想主義的で現実的でないことを一方的に人々に押し付け、争いを拡大&硬直化させる・・・という、だいたいそんな感じで間違いないと思う。
本を読む限り、塩野さんは、ルネサンス的な「人間(中心)主義」であり、あらゆる宗教の「神有りと言う世界観」とは遠く離れているようだ。 ギリシャやローマと言った多神教の国家でも、ずっと非道な殺戮や戦争は絶え間なく続いていたのだが、それについての認識についてはどうなんでしょうね?(笑)。
思うに、争いや非道の根源は宗教に求めるよりは、不完全な人間自体にこそ、その根源を見出すべきです?
以上、7月の読書で色々感じたことでした。
2019年6月に読んだ本
6月も、本をそれなりに読めました。コミックのワンピースは、87巻から92巻まで一気読み。
★ギリシャ人の物語2巻・民主政の成熟と崩壊 塩野七生著/新潮社
巨大な力を持ったペルシャ帝国を完膚なきまでに叩いて勝利し、エーゲ海の覇者となったギリシャ。しかし、その役割を担ってきた優れたリーダー達が相次いで歴史の舞台から消えると、アテネの民主政やギリシャ世界全体に暗雲が立ち込める。広がり過ぎた覇権地域のいざこざの解消、凡なるリーダー達、扇動者に惑わされる市民、衆愚政治化していく民主政。
そして、遂にギリシャ都市国家の2大盟主たる、アテネとスパルタが成り行きで仕方なくとは言え対決することとなる。巨大な海軍力を持ったアテネと、強大な陸軍力を誇るスパルタ。実際は、両者の正規軍が直接対決することはなく泥沼の戦いに進んでいくのだが、アテネは全ての国力を投入した海軍を失う。アテネはスパルタに敗北し、築いてきた民主政、エーゲ海諸国の同盟の絆、海軍力を全て失う。だがしかし、勝ったスパルタとて、軍事だけが取り柄の戦士の国家。アテネのように、エーゲ海の国々を経済や外交でまとめ上げる裁量など皆無なのであった。こうして、繁栄の一時代を築いたギリシャのポリスは転落の一途をたどっていくのである。3巻へ続く。
★ローマ人の物語・6&7巻(勝者の混迷) 塩野七生著/新潮文庫
長く続いたカルタゴの名将ハンニバルとの戦いに終止符を打ち、地中海の大国カルタゴを破ったローマ。
このポエニ戦役後、アレクサンダー大王を輩出したマケドニアもローマは滅ぼす。その頃から、共和政のローマの歯車が狂っていく。
敗北した国を同盟国にしてきた温和な対外主義が、次第に強硬路線へと変わっていく。かつてのローマでは考えられなかったような、残虐な戦後処理や国内では政敵の抹殺さえ行われるようになる。
優れた才能とバランス感覚を持つリーダー達は、歴史の舞台から次々に消え、その後に登場するリーダーたちの時代に混迷を迎える。若き護民官ティベリウス・グラックスは元老院に挑戦して市民のための法案を次々に出すが、文字通り抹殺される。時を経て、弟のガイウス・グラックスも護民官となるが、彼もまた改革しようとして抹殺され晒し首となる。かの兄弟の未来を見据えた改革案は、この時代には一旦無に帰し、将来の復活を待つこととなる。
その後、マリウス、スッラ、クラッスス、ポンペイウスと言った武勲を立てる者らが登場するが、彼らが更にローマを混迷に突き落とす。ローマの共和政は、独裁政を許さない制度として機能していたはずだが、この後登場するリーダー達は、己の名誉欲、権力欲、時には経済力への欲望を隠さず、法を逸脱した権力や独裁者並みの権力を元老院に要求するようになる。敵対する政敵の仲間は、同じローマ人であっても、何千人も虐殺する。故人の墓すら暴く。財産は没収。仲間を虐殺されたら、相手方の仲間も虐殺すると言う報復の応酬がまかり通る。ローマ法を逸脱し、今までは考えられなかったことが平然と実行される。スッラは、独裁権を手にして非情な虐殺を伴った粛清を行い、市民側の力を弱め、かつ元老院側が強力な主体となる共和政を維持しようと図る。しかし、今までのローマの保守的な共和政システムは、崩壊寸前だった。
不公正なローマに対して属州で起こる反乱、ローマに戦いを挑むポントス王ミトリダテスの大軍団、そして自国内でも「スパルタクスの乱」が起こる。僕も昔映画で見た、カーク・ダグラス主演のあの「スパルタカス」だ。自分の国が制圧される前は貴族だったと思われる奴隷とされた剣闘士スパルタカスが、仲間と共に反乱、脱走する。たかが74人の奴隷の脱走に、ローマは3,000人に満たない軍団で十分と考えて派遣する。しかし、百戦錬磨の鍛え抜かれた74人はこの軍団に勝ってしまう。スパルタクスは、戦力上の頭脳も持ち合わせていた。この武勇を聞きつけ、彼の元にはローマに反感をもつ人々が何万人にも押しかけて、一大軍団となってしまう。ローマ軍は負け続け、ローマの大軍団もこの反乱の制圧にひどく手間取ることになるのである。
話を元に戻すが、保守派の元老院貴族達は己の保身しか考えない、武勲で成り上がったリーダー達は自分の栄誉や権力や財産しか考えない、そして各地で起こる反乱。地中海のほぼ全域を掌握した大国ローマは、混迷期を抜け出せないのであった。続く。
2019年5月に読んだ本
5月は、本をいっぱい読めました。これだけ読めたのは、電車通勤でなくなってからは初めてかも~。
5月のGWにプラスして、電車などでの宇都宮往復や仙台往復と言った長時間移動があったため。一部をピックアップして感想を書きます。
★ローマ人の物語・2巻(ローマは一日にして成らず)、3~5巻(ハンニバル戦記) 塩野七生著/新潮文庫
4冊を一気読み。ローマの共和国成立を語る「ローマは一日にして成らず」を読んだ後、1世紀に渡るポエニ戦役を語る「ハンニバル戦記」を読了~。
まだまだ弱小のローマは、シチリアを巡って地中海の大国カルタゴとの戦いに突入する。海軍を持たないローマは、海軍を創設。よちよち歩きの海軍を次第に強化していって、最終的にカルタゴに勝利する。これが第一次ポエニ戦役。
そして後年、カルタゴのハンニバルがローマ軍をことごとく破ってイタリアで暴れまわる第二次ポエニ戦役。敗戦続きのローマが、この天才武将ハンニバルから多くを学んでいく。その後のローマがあるのは、実はこのハンニバルのおかげかもしれない。
そして、長い長い戦役後にローマの勝利。その後、ハンニバルの故国カルタゴも、アレクサンダー大王を輩出したマケドニアもローマに滅ぼされていく。敗北した国を同盟国にしてきた温和な対外主義が、次第に強硬路線へと変わっていく転機となる。これを手に汗握る筆致で、読者の私を一気に読ませた・・・続く(笑)。
★ギリシャ人の物語1巻・民主政のはじまり 塩野七生著/新潮社
「ギリシャ人の物語」は、ローマ人の物語を全巻読んでから読もうと思っていたんだけど、古代ローマは何かと古代ギリシャと縁が深いので、同時進行で読むことにした。
ただ何と言うか、「ローマ人の物語」や「十字軍物語」のようなワクワク感が薄い気がする。一次資料や二次資料が少ないから仕方ないのかもしれないが、「…と思う」とか「…ということになりはしないか」と言うような、推測や想像がとても多く、かつ内容も社会や歴史の解説書っぽくて何だかなぁ~。
だが、ペルシャ戦役の辺りから、ようやく物語は熱を帯びてくる。バビロンを破り広大な国土を手に入れたペルシャ帝国のキュロス。そして後を継いだダレイオスが、小国ギリシャに目をつけ、第一次ペルシャ戦役が起こる。誰もがペルシャの圧勝と思ったが、スパルタが応援に駆けつける前にアテネがマラトンの戦い(マラソンの語源ね…)で勝ってしまう。
連戦連勝だったペルシャ帝国は、その敗戦の結果、各地の反乱を招くこととなる。そして、今度はダレイオスの後を継いだクセルクセスが、本気になって自ら何十万と言う軍団、そして千艘以上の軍船を引き連れて、再びギリシャへ攻め込んでくる。兵力は十分の一しかないギリシャは、今度こそ絶対絶命のピンチ。
この第二次ペルシャ戦役は、映画「300(スリーハンドレッド)」の舞台にもなった「テルモピューレの戦い」から始まる。少ない軍勢でペルシャの軍勢2万を倒しなんとか侵攻を食い止めていたギリシャ連合だが、戦況の不利を悟ったスパルタ王のレオニダスが、他国のギリシャ兵を撤退させ、最終的にレオニダス自らとスパルタの兵300人だけでペルシャ兵20万との死闘を繰り広げた戦いである。 その後、都市アテネを放棄したアテネは、だがしかし、あの有名な「サラミス海戦」に挑む。軍船の数で圧倒的に不利なアテネ側のギリシャ連合軍は、その巧みな戦術でペルシャ海軍を破る。この敗北を受けて、クセルクセスは本国に逃げ帰る。 ギリシャ本土に残った12万のペルシャ兵の大軍は、プラタイアの平原にて、今度は300人でなく強者スパルタ兵1万を含めたギリシャの連合軍計4万との戦いとなったが、ここでも数の上では3倍差もある圧倒的な戦力のペルシャ軍が、戦術の差で大敗を喫す。 その後、ギリシャはペルシャのエーゲ海の要所を落としていき、巨大な力を持ったペルシャ帝国の追い出しに成功し、ギリシャはエーゲ海の覇者となったのである。
オリエントの貴公子たる冷静なクセルクセスは、その後人格が破綻したそうである。だが、一方のギリシャを勝利に導いた、アテネとスパルタ優れた指導者が二人とも、政敵の策謀や英雄を認めない国の定めによって、最後はそれぞれ悲しい運命を迎えた・・・こちらも続く。
★旧約聖書(新共同訳聖書)
旧約聖書・全1,502ページの通読完了~。
新旧約聖書の通読は現在11回目で、(色んな翻訳の聖書があるんですが)新共同訳の聖書は今回で5回目。
旧約聖書って、1,000年以上の間にたくさんの著者によって書かれ、文体も歴史書だったり、詩だったり、知恵文学だったり、黙示文学だったりと幅広いんだけど、凄いのは、それだけの長期間の間に多数の人によって書かれているのに、テーマが初めから終わりまで一貫していること。冒頭の創世記にて、人の子孫が「蛇の頭を砕く」との記述から、最後のマラキ書の「(あなた方には)義の太陽が昇る」との記述までブレがない。 毎朝のデボーション時に読んでますが、明日から新約聖書に入ります。
2019年4月に読んだ本
4月に読んだ本、漫画込みでわずか6冊。時間がなかなか確保できず、あまり読めなかったけれど、ようやく「ローマ人の物語」読書開始!
★ローマ人の物語:1巻目(ローマは一日にして成らず・上巻) 塩野七生著/新潮文庫
ローマの誕生、そして王政から共和制への移行期まで。
歴史の流れの記述にぐいぐい引き込まれるのだが、細かい蘊蓄も(雑学好き人間として)面白い。一例として、カレンダーの「7月=ジュライ(July)」がユリウス(Iulius)・カエサルに由来するとか、「8月=オーガスト(August)」が、実はローマの初代皇帝アウグストゥス(Augustus)に由来するとか、そんなん色々。
この巻の終わりの方で、古代ギリシャの歴史にも触れるのだが、「トロイの木馬」で有名なトロイ戦争の話が出て来て、ブラッドピットがアキレスを演じた映画「トロイ」を思い出しながら読んだ。気分は幼少期のシュリーマン!(笑)
また、ペルシャ帝国のクセルクセス王が、30万の兵と1千隻の船を率いてギリシャに攻めて来た時、300名の兵士だけで険しい山あいの死守を決めたスパルタの勇士達の記述を、映画「300(スリーハンドレッド)」を思い出しながらワクワクして読みました。2巻も超楽しみです。
ところで現在、小説やノンフィクション、雑誌等々の「積ん読書」が、16冊・・・読破する本よりも溜まっていく本のペースの方が速いです(汗)。
2019年3月に読んだ本
3月に読んだ本、7冊。うち2冊をピックアップ。
★ホロコーストからガザへ(パレスチナの政治経済学) サラ・ロイ著/青土社
著者のサラ・ロイはユダヤ人で、政治経済学が専門のハーバード大学の中東研究所の上級職員。彼女の親族や家族はナチスのホロコーストで100人以上が亡くなり彼女の父は、15万人が殺害されたポーランド内の絶滅収容所を生き延びた僅か4人のうちの一人。戦後、彼女の母は多様性と寛容な社会での人生を求めてアメリカに渡ったが、彼女の叔母は自らの安全を求めてユダヤ人だけの国家に邁進するイスラエルに渡った。 サラはユダヤ人でありながら、彼女の詳細な研究はイスラエルのパレスチナ(とりわけガザ)に対する過酷な占領政策を、特にオスロ合意以降の「和平」と言う言葉とは程遠い現実を、世界に伝えます。
サラが、パレスチナの現地調査で目にしたものは、かつてユダヤ人がホロコーストで経験したのと同じような人間性を否定&破壊する恐ろしいものだった。
彼女が現地で最初に見たのは、イスラエル兵が現地の孫を連れた老人を怒鳴りつけて、ロバの尻にキスさせると言うものでした。老人は拒絶しますが、兵士は怒鳴り続けると、孫がヒステリックに泣き始め、老人はロバの尻にキスしました。兵士たちは、大笑いしながら去っていきました。
ある時は、パレスチナの青年が、イスラエルの兵士に命令されて、4つんばいにさせられて犬のように吠えさせられていました。ある時は、妊婦が兵士たちにお腹を蹴られまくるという光景でした。ユダヤ人であるサラも、恐怖でただそれを見ているしかなかったそうです。人間の尊厳をここまで否定するこのような行為が、日常的に行われているのです。
今に至るまで、イスラエルは、パレスチナの土地を奪い、家や畑を破壊し、壁で地域を分断し、水も電気も燃料も仕事も奪い、子どもを誘拐し、武器を持たぬ一般人をまるでゲームのように狙撃し続けているのです。
ホロコーストを経験したユダヤ人が、なぜこんな非道なことを続けられるのか?極右なイスラエルの人々は、そもそもホロコーストに甘んじた弱いユダヤ人を軽蔑の眼差しで見ているのです。はっきり分かっているのは、建国以来彼らの悲願は、パレステチナの人々を殲滅して、強力なユダヤ人だけの国家を作る事なのです。これは、サラの叔母の側の「シオニスト」の立場で、サラの母側が取った「ジュダイズムの寛容」の社会とは相いれぬものなのです。イスラエルにもパレスチナの情報は入りますが、国民の多くは自分たちの国が悪魔のような所業をしていると言うような都合の悪い事は、そもそも見たくないのです。見てみぬふりか、無関心なのです。サラのような事実を伝えるユダヤ人は、イスラエルでは裏切者扱いで邪魔者なのです。(この手の事は、日本も含め極右化しつつある全世界の傾向かもしれません)。 この本の内容全ては書ききれませんが、サラのこの研究は、間違いなくパレスチナに対するイスラエルの占領政策の最も的確な研究と言えるでしょう。
★イエスの御名で ヘンリー・ナーウェン著・後藤敏夫訳/出版社:あめんどう
ノートルダムやイエール、ハーバードと言った名だたる大学で経歴を重ねてきたヘンリーは、知能障害者のラルシュ共同体に移ります。
そこでの生活を通して、彼は自らの過去の経歴も名声も、一切役に立たないことを学びます。人が(自分が)、いかに力(能力)の誇示や人々の関心を集める欲求に影響されているかを知ります。ラルシュで大事なのは、「ヘンリーは、今日ここにいてくれるの?」と言うようなこと。
一部の人は、自らの政治的権力や経済力、武力などの力を背景に国家や人々の上に立とうとします。しかし、本当のリーダーシップとは、自らの霊性の貧しさを知り、砕かれた魂の先にあるのです。この本は、それを伝えます。
2019年2月に読んだ本
2月も、忙しい割には本が読めました。電車に乗る機会が多かったのと、週末は雨や雪が多く、かつケガもあってアウトドア運動ができなかったためです。今回は6冊のうち、3冊をピックアップします。
★世界史・下巻 ウィリアムマクニール著/中公文庫
マクニールの世界史の下巻を読み終える。ようやく、上・下巻1,000ページを読破しました。
世界史を古代から現代まで概観すると言う事は、森を見ること。私達は、日頃は日ごとのニュースに追われ、一本ごとの木のその一部しか見ていません。森全体を見る視点を失うと、一気に時代の流れに押し流されて翻弄されてしまいます。歴史は何度もそれを繰り返します。世界史は、それを教えてくれます。
★アラブ、祈りとしての文学 岡真理著/みすず書房
文学は、戦争や弾圧に対して何ができるのか? 今頭に銃口を突きつけられている人に対して、打ち込まれてくるミサイルに対して、飢餓で今まさに命を失おうとしている子供に対して、文学は何ら阻止する力を持っていません。この問いは、音楽や絵画などアート全般に同様なことが言えます。
しかし、もし誰かが書かなかったらば、記録しなかったならば、惨劇を引き起こした者たちの大義名分や彼らの正義だけが歴史に残り、多くの惨劇の被害者たちの歴史は、当事者たちの命や記憶と共に消え去ってしまうのです。
パレスチナの地に、イスラエルの国家を建国する案は、当初、国連での多数決に必要な2/3を得られなかったのですが、ユダヤ票に後押しされたアメリカの熾烈な多数派工作により、1947年11月の総会で、パレスチナ分割決議案が可決され、ユダヤ人シオニストは即日イスラエル国家設立を宣言した。 このイスラエル建国は、現地のパレスチナ住民の主権を侵害した不当なものであったことは言うまでもない。しかも、当時パレスチナのユダヤ人人口は31%で、かつ当時6%しか土地を所有していなかったユダヤ人に割り当てられた面積は50%以上を締めていたのである。
そしてイスラエルは「民族浄化」を開始し、1948年に80万人ものパレスチナ人が難民となった。国連総会は、イスラエル建国によって難民となったパレスチナ人の即時帰還の権利を確認したが、イスラエルは難民の帰還を阻止するために500以上の村を破壊し、帰還の権利を否認し続けている。
虐殺によって失われた多くの命、追われた故郷、破壊された家や果樹、奪われた土地や畑、損なわれた人間としての尊厳。これを、誰かが書かなければ、イスラエル側のシオニスト史観による一方的な歴史しか残らないのだ。
この本は、アラブ人作家らのそれぞれ作品を本質を突きながら、丁寧に解説してくれます。
★草生人:2019年新春号
今回の特集は、「草加の農業」。決して広い土地とは言い難い都市農業の在り方や模索、実践など、それぞれの事業者の視点で書かれたとても良い特集でした。
残念ながら、草生人は「一旦お休み」とのこと。たいへんしっかりした取材力、紙面構成力で、毎回楽しみにしていました。更なるパワーアップでの再始動、楽しみにしています。
ところで最近個人的に思うのだけど、草加には優れた写真家やアニメーターや脚本家、Webデザイナーや種々クリエーターやイベンター、そして草生人のような優れた雑誌など、たくさんの才能が揃っているのに、それを統括して大きな視点で活用できるシステムの欠如がもったいないなぁ、と常々思っている。個々がそれぞれデフレ単価で競い合うのではなく、総合的に連携しあって大きなパワーを発揮できるシステム、関係性。大きな視点にたった広告代理店的な(もしくはそれ以上の働きをする)事業者が、草加に必要と思う今日この頃。
2019年1月に読んだ本
昨年11月と12月は心身がヘロヘロでほとんど読めなかったけど、1月は電車に乗る機会が多かったので、意外と本が読めたかな。
1月に読んだ本の8冊のうち、3冊についての感想。
★国産&輸入車完全アルバム・2019年版 (driver)
スーパーカー世代の車好きなので、今年も「国産&輸入車アルバム」の本を買いました。2003年以来買い続けてきた「JAF出版版」が2015年に一次中断した時に、「CARトップ版」に切り替えましたが、2019年度版から突如5割近い値上げをしたので、2019年版からは「driver版」に変更。長年の無駄な車の知識が、頭に詰まっています(笑)。
ざっくり言うと、今の自動車はガソリン車以外への過渡期だね。
★埼東文学・復刊23号 埼東文化会
小説や詩歌などの書き物集団「埼東文化会」の春と秋の文芸誌。親父殿も所属して書いているので読んだが、純文学とか読まなくなって久しいな。へえ、地元のこう言うとらえ方もあったりするんだ~、地元にこう言う人がいるんだ、と言った発見がある。
★あなたの花を咲かせて いのちのことば社
放送伝道に携わる、色んなキリスト教派の牧師先生達のメッセージ集。聖書の福音を分かりやすく伝える。読みやすい。
以上、1月の簡易読書感想記でした。 2月も順調に読書できると良いな。積読書(つんどくしょ)の量が半端ないす。 ついに念願の「ローマ人の物語1巻(塩野七生著)」も購入し、積読書に追加。これを読めるのはいつの日か!?