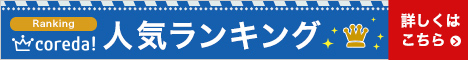入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第四十八章 四十年
ベルムによるNDP本部襲撃事件から、十年が経過した。世界を取り囲む状況は一変していた。
二十世紀、そして二十一世紀と、長期に渡って止む事無く進行した気候温暖化は、海水の水位を数メートルも押し上げ、多くの小さな島々と低地の多くの都市が海水面下に沈んだ。また中国やインド等のアジア諸国、アフリカ諸国で進んだ大規模な工業化による大気汚染は、世界各地に激しい酸性雨を降らせ、河川や湖沼の生命を死滅させ、大都市のコンクリートすら溶かした。同時に地球規模の大気汚染は各地に光化学スモッグを発生させ、巨大化し多オゾンホールからは有害な波長域の紫外線が地表に降り注いで、人体の健康にも多大な被害をもたらした。
そして、より直接的な都市への打撃は、大規模な気候変動だった。人類がかつて経験した事のない超巨大なハリケーンや竜巻が、世界各地の都市を何度となく襲い、破壊し続けた。洪水は家々を押し流し、その一方で酷い旱魃が農業地域を襲い、世界の貧しい地域の飢饉は深刻なものとなった。
人類は、自然の猛威から身を守るため、自然界と都市を隔絶する必要に迫られた。大気汚染、有害な紫外線、放射性物質、自然の暴風雨から守るため、各国は巨大なドーム都市建設の検討を始めた。
それに駄目押しをしたのが、ベルム達の増殖であった。凶暴で狡猾なベルムの群れは、東南アジアから北アジア、中央アジアに生息域を広げ、遂にはヨーロッパやアフリカにまで広がった。ベルム達は、二~三メートル程度の壁を軽々と飛び越えた。警官の拳銃はベルムに対してはほとんど役に立たず、ベルム達が出没する地域では、昼夜を問わず重武装装備した兵士達が街中を監視する半戒厳令状態となった。人々は、ベルム達から完全に隔離された安全な都市の建設を政府に求めた。
迫り来る自然の猛威と凶暴なベルムから身を守るため、まだ経済力の残っていた一部の先進国が、真っ先に巨大ドーム都市建設に着手した。
しかし、世界の経済は停滞し、未曾有の不況が続いた。国家の財政はドーム都市に注ぎ込まれ、一方で貧しい人々はドーム都市の外部で、恐怖と飢えに満ちた苦しい生活を余儀なくされた。各国政府は、暴動やデモを鎮圧するため、より全体主義的な強権政治に移行していった。民主主義は、一部の権力者と富裕層のものだけとなった。
世界は、ニュー・ダイダロス・プロジェクトどころではなくなっていた。世界が一致協力した人類最大のプロジェクトは、歴史の片隅に追いやられた。どの政府も、NDPへの予算を大幅に削減した。一時期は、世界各地に数万人規模の職員数を誇ったNDPも、今は千人の職員を確保するのも困難になっていた。ベルム達に破壊されたNDP本部の再建は、膨大な巨額の予算の捻出が不可能で、とうの昔に放棄された。何光年も先にいるエンタープライズ号は、宇宙で孤立無援の旅を続けざるを得なかった。彼等は、地球で何が起ったかを知らない。
更に十年の歳月が経過した。世界各地にドーム都市が、林立した。貧しい国々も、ようやく小規模なドーム都市建設を始めていた。ドーム都市に居住が認められなかった貧しい人々や、隣国の難民達は、地下組織を組織し、ドーム都市に対してテロ攻撃を仕掛けたり、物資輸送の車や船にゲリラ的な襲撃を繰り返した。
ベルム達は、(ドーム都市を除き)人間に変わって地球の覇者に君臨していた。北米の知能の高いベルム達も、アジアのベルムと同様に生息域を拡大した。北はカナダやアラスカ、南はメキシコ、果ては南アメリカ大陸まで、至るところにベルムの生活圏を確保した。
アジアのベルム達と違い、北米のベルム達は自ら人間を襲う事は無かった。しかし、狂信的なWASP団体の若者達が、ベルム狩りと称してライフルやショットガンを携え、各地のベルム狩りに向かった。全米ライフル協会も全国的な反ベルムキャンペーンを行い、腕に自信のあるハンター達もベルム狩りに向かった。
しかし、ベルム狩りに向かったハンターやカルトの若者達の末路は、惨憺たるものだった。無事に帰って来られた者は、ほとんどいなかった。いつしか、余程の物好きかカルト信者でもなければ、誰もベルム達に関わらないようになり、ベルムと人間の間に暗黙の棲み分けがなされるようになった。
更に十年が経過した。時はいつしか西暦二〇五〇年を超えていた。世界各国の全体主義は確固としたものになり、貧しい者や難民の人権はほとんど塵であるかのように無視された。巨大な暴風雨、洪水、旱魃…自然の猛威は、貧しい人々を襲い続けたが、援助の手は差し伸べられなかった。ユーラシア大陸のベルム達は、山林が破壊され、周囲から獲物が消えると、容赦無しに貧しい村落の家畜と人間を襲った。ドーム都市に住む人々は、自分達の安全確保と利益しか考えていなかった。
悲劇的で希望のない日々の生活は、ますます激しいテロへと人々を駆り立てた。世界で、爆破や銃撃、暴動や鎮圧で人の死なない日は一日となかった。
そして西暦二〇六五年を迎えた。その年の十一月二十日、人々に忘れ去られていたエンタープライズ号が、約四十年の時を超え帰還した。NDPのスタッフは、僅か数百名にまで減っており、その大半がボランティアの科学者だった。僅かな予算で設備を修復し、エンタープライズが帰還するほんの僅か前に交信を復活させた。
世界の至る所にベルムがいたが、世界で唯一まだベルムの被害が確認されていないオーストラリア大陸の南部で、帰還歓迎の式典が行なわれた。宇宙船が一つの星を一往復する間に、世界は大きく変わってしまった。
同じ二〇六五年の十二月半ば。一人の女性が、カナダのマッケンジー山脈のとある山を登っていた。酸性雨の被害を免れた木々や水が、まだこの周辺にはかなり残っている。しかし気温が大きく上昇したため、植物の分布状況が半世紀の間に大きく変わってしまった。針葉樹は減り、また落葉樹に変わって常緑樹が増えていた。棲息する鳥の種類も変わった。動物や昆虫の中には、絶滅したものも多い。
たった一人登山を続けていた女性は、ある気配に立ち止まった。木々の間からぞろぞろとベルム達が出てきた。総計五体のベルムがいた。
「人間よ、何しに来た」。
女性は、ベルムの姿を見ても恐れる様子はまったく無かった。
「ここは、人間達が来る場所ではない。帰るが良い」。
「いえ。グレート・ジョンに会えるまでは、帰るつもりはないわ」。
一瞬、ベルム達がざわついた。
「何故、その名を知っている?その名を、人間が知っているはずがない」。
女性は答えた。
「私は、あなた方を研究している科学者よ。先月、狂信的な人間のグループに一斉に撃たれ、死ぬ寸前だった年老いたベルムを救い出して、私が治療したのよ。彼は今、わが家で療養しているわ。彼の名は、ゲバラ。ジョンの第一世代の子どもよ。彼から、ここの事を聞いたのよ」。
ベルム達の表情は読み難いが、動揺しているのは明らかだった。
「いや、そんなはずがない。あの勇敢で偉大な英雄ゲバラが、私達の最も大事な秘密を、人間達に軽々としゃべるはずがない!」
女性は、その答えを予期していたようだった。
「それは分かっているわ。ゲバラは、決して命を無駄にするベルムでは無いけれど、人間にそんな事を話すぐらいなら、自発的に栄誉ある死を選ぶでしょうね。でも、私は他の人と違うのよ」。
ベルムが問い詰めた。
「一体、何が違うと言うのだ?」
女性は、はっきりした口調で言った。
「私は、メグ・ブラウン。グレート・ジョンの生みの親、ブラウン博士の子どもで、グレート・ジョンの人生最初の友達よ」。
そう言って、彼女はポケットから一枚の写真を取り出した。彼女の子どもの頃の写真だった。それをベルムの方に静かに差し出すと、ベルムは受け取った。
「あの伝説の、メグ・ブラウンなのか?」
女性は、静かに頷いた。
「ちょっと待ってくれ。確認する時間が欲しい」。
リーダー格のベルムは、ベルムを一人、伝令に使わした。その間、やや気まずい沈黙が支配したが、ベルム達はグレート・ジョンから伝え聞いているメグ本人がそこにいると言う事実に、喜んでいるようでもあるが、一方で猜疑心も消えないでいるようであった。人間達の罠ではないのか?…と。
十分ほどして、百名近いベルム達が、林間を足早にやって来た。先頭には、年老いたベルムがいた。若いベルムは、頭をさげて敬愛の意を示した。年老いたベルムは、女性を見るなり叫んだ。
「メグ!」
女性は言った。
「ジョンね!」
ジョンは駆け寄って、女性を潰さないように軽く抱きしめた。
若いベルム達は、それが本当に伝説の女性メグ・ブラウンだと分かり、一同頭を垂れた。ジョンは言った。
「よく来てくれた。私達の集落に、歓迎する。あなたが、私達の集落を見る世界初の人間だ」。
ベルム達一同は、喜びながらメグを取り囲み、山間の集落へと向かった。