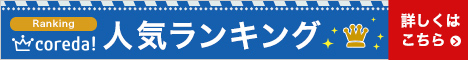入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第三十六章 洞窟内の探索
ハンター九名は、洞窟から百メートル手前の茂みの中に集結した。距離測定機能付きの双眼鏡で、キングスレーは洞窟の周囲を観察した。
「随分狭い洞窟だな…。入り口は、せいぜい一人分の広さか。」
キングスレーは、チームリーダーのロッドとロイに向き直った。
「ロッド軍曹。私のチームが、洞窟へ潜入する。君のチームは、洞窟脇の茂みで外の警戒に当たってくれ。ロイ曹長、君のチームはここで援護と周辺の警戒、ベースキャンプとの連絡に当たってくれ。」
ロッドとロイは頷いた。キングスレーは続けた。
「奴が中にいるかどうかは分からない。中にいたとしたら、奴が既にこちらの存在に気がついている可能性もある。まだ奴が洞窟の外の周辺にいる場合は、警戒して逃走するかもしれないし、攻撃してくるかもしれない。一切の予断は許さない。外の警戒も"絶対に"怠らないでくれ。では、作戦を開始する。」
キングスレーとロッドのチームは、洞窟からは死角になる茂みの中を歩き、洞窟へと近づいていった。洞窟入り口の側面に到達すると、キングスレーは停止の合図をした。ロッドのチームは、洞窟脇の茂みに身を隠した。
キングスレーのチームは、そのまま先を進んだ。新開発の名前すらまだ無い短機関銃"Xガン"を構えつつ、まずキングスレーが洞窟に踏み入った。続いて伍長のジャックが入り、最後に上等兵のジムが入った。
洞窟の入り口に近い場所は、まだ外からの光が差し込んでいたが、前進するに従い暗くなっていった。外の天気も雨雲が広がって、暗くなりつつあった。洞窟の外のロッド軍曹から連絡が入った。
「雨が降ってきました。スコールです。」
声帯振動マイクを使って、キングスレーは答えた。
「了解。」
洞窟は、緩やかに左に折れていた。音を立てぬよう、一歩一歩ゆっくりと静かに前進する。やがて、周囲は真っ暗になった。
「ナイトビジョン装着。」
キングスレーが指示を出すと、ジャックとジムが指示に従って暗視ゴーグルを装着した。
洞窟は予想以上に長く、彼等は既に百メートル以上内部に入っていた。しかも、次第に狭くなっていて、膝をつかなければ前進できなくなっていた。
キングスレーは、突然何かの"気配"を感じた。彼は、手で停止の指示を出した。後方の二名は、その場で停止して短機関銃で身構えた。しかし洞窟内はとても狭く、前方からタッツェルベルムが襲ってきた場合、キングスレーの背後から攻撃する事は不可能に思われた。
キングスレーは、前方に本能的に"何かの危険"がある事を感じて、チームの二人をそこに残したまま、ゆっくりと匍匐前進を始めた。短機関銃をいつでも発射できる体勢にして、前方を凝視した。高性能暗視ゴーグルを通して、前方で何か動くものを見たような気がした。と、その時である。ロッド軍曹が、連絡をしてきた。
「キャプテン!奴です!薮からいきなり飛び出して、洞窟へ向っています!今、洞窟へ飛び込みました!」
洞窟の外の銃声が、洞窟内にも響いた。キングスレーは、叫んだ。
「くそ、外か!奴が来るぞ、ジム!反転して備えろ!」
ジムは指示に従おうとしたが、洞窟が極度に狭く体を反転させるのにてこずった。異様な獣の叫び声と、洞窟内を突進してくる激しい足音が聴こえる。
「すぐそこまで来てるぞ、ジム!急げ!」
あっと言う間だった。タッツェルベルムの行動はすばやく、ジムが洞窟内での反転を終える前にジムの足を捕らえた。ジムが叫んだ。
「キャプテン!奴に足を捕まれました!」
キングスレーが、冷静に指示を出した。
「落ち着け、ジム!ジャッキー、奴を撃てるか!?」
ジャッキーが答えた。
「ここからでは無理です!体が反転できません!ジムを撃ってしまいます!」
しかし、大柄なタッツェルベルムも、この狭い空間ではジムを引き裂く事はできなかった。彼は、鋭い爪のある指でジムの足をつかみ、そのまま洞窟の外へと彼を引き出すため後退を始めた。ジムは抵抗を試みたが、とうていタッツェルベルムの強靭な脚力や腕力に抗う事はできなかった。
洞窟の外では、スコールの激しい雨が打ち付ける中、ロッドとロイのチームの六名全員が、短機関銃を入り口に向けて待ち構えた。タッツェルベルムは、洞窟の広い所まで戻ってくると、左手でジムの足を持って彼を吊り下げたまま洞窟の入り口へ向った。キングスレーとジャッキーも、何とか狭い洞窟内を後退し、ようやく反転できる広さのところまで来て、急いで洞窟の入り口へと向った。
洞窟の入り口へ辿り着いたタッツェルベルムは、そこに兵士達が身構えている事を重々承知しているようだった。ジムを自分の前に吊り下げて人間の盾とし、入り口付近に留まった。ジムの足からは大量の血が流れ落ち、雨によってできた水溜りに流れこんだ。ロッドが、キングスレーに連絡を取った。
「キャプテン!ジムが、奴の盾になっていて撃てません!」
キングスレーが、答えて言った。
「我々も、すぐに入り口に到着する。指示を待て!」
キングスレーとジャッキーは、タッツェルベルムから三十メートルほど手前まで来た。暗視ゴーグルを頭から外し、短機関銃をタッツェルベルムの背に向ける。
「ジャッキー、撃てるか?」
「この短機関銃の威力によります。貫通して、ジムに当たるかもしれません。」
「分かった。では、足を狙え。ロッド、ロイ、チャンスがあれば、止めを刺せ!」
「了解!」
外の二人が応答すると、キングスレーはジャッキーに言った。
「撃て!」
ジャッキーは、即座に引き金を引いた。短機関銃から銃弾が放たれ、タッツェルベルムの足の外皮を貫いた。タッツェルベルムは、悲鳴のような叫び声をあげて、豪雨の降る洞窟の外へ逃れた。しかし、相変わらずジムは盾にされていた。ロッドが命じた。
「ホーマー、ミキモト!足を撃て!」
ホーマーとミキモトは、タッツェルベルムの足を撃った。タッツェルベルムの足の肉片が飛び散り、タッツェルベルムが倒れた。すかさずジャッキーが洞窟から飛び出て、タッツェルベルムの背後に迅速に走り寄り、タッツェルベルムの頭に短機関銃を押し当てようとした。しかし、タッツェルベルムは反射的に空いているもう一方の右の手で、彼を弾き飛ばした。彼は、地面に叩きつけられた。
そのすぐ後に、キングスレーが引き金をひいて、そのタッツェルベルムの右腕を撃った。新開発の短機関銃の破壊力は凄まじく、確実にタッツェルベルムの堅い外皮を貫いた。
タッツェルベルムは悲鳴をあげて、ジムを投げ飛ばして放した。ジムは、スコールの中に投げ飛ばされた。間髪を入れず、タッツェルベルムは、最も近くで応戦していたホーマーとミキモトに突進して、彼らを突き飛ばした。二人とも、スコールで出来た水溜まりに叩きつけられた。ロッド、ロイ、トニー、ルークそしてキングスレーの5名が、スコールの豪雨にも劣らない銃弾の雨を、タッツェルベルムに浴びせ掛けた。
短時間に数百の弾丸がタッツェルベルムに命中して肉片と血が飛び散り、右腕がちぎれ、遂にタッツェルベルムはその場に崩れ落ちた。しかし、まだ動こうともがき、左手や足をばたつかせていた。キングスレーは速やかにタッツェルベルムに近づき、頭に銃を当てて引き金を引き、止めを刺した。研究所で "暴れん坊"と呼ばれていた"タッツェルベルム達のボス"の最後だった。
キングスレーは叫んだ。
「被害状況を把握しろ!」
また鉄かぶと島の再現をしてしまったのか…キングスレーは臍をかんだ。
無事だった兵士達は、怪我を負った兵士達に駆け寄った。ジムは鋭い爪で足の肉を引き裂かれ、脛の骨が露出していた。ジャッキーは、肋骨を数本折っていた。ホーマーは、あちこちを打撲し、右腕の骨が折れているらしかった。ミキモトは、やはりあちこちに打撲や切り傷を負っていて、口の中も切れていた。全員が一ヶ所に集められると、軍曹のロッドが、報告した。
「全員、命に別状はありません。」
その報告を聞いてから、キングスレーは叫んだ。いつも冷静な彼にしては、あからさまに感情を露にしていた。
「ロッド軍曹!何故、奴の洞窟への侵入を許した!?あれほど、警戒を怠らぬよう命じたではないか!」
初めてキングスレーが烈火の如く怒るのを目にして、特殊部隊出身の屈強のロッドもたじろいだ。
「スコールの音が激しくて、周囲の音がかき消されてしまいました。しかも、奴が背後の密林から飛び出た瞬発力が、予想以上だったもので…誰も対処できませんでした。」
キングスレーには、分かっていた。タッツェルベルムの能力は、それを"経験"した者でないと決して分からないのだ。頭で"理解"しただけでは、決して分からない。キングスレーは、再び冷静に戻った。
「すまない、軍曹。怒鳴るつもりは無かった。」
キングスレーは、周囲を見回した。タッツェルベルムの死体が一つと、負傷した兵士が四名。とにかく任務は、終了した。
彼は言った。
「タッツェルベルムの痕跡を残さないように、死体と肉片をすべて回収して、袋に詰めろ。」
怪我をしていない兵士達は、タッツェルベルムの痕跡を現地に一切残さないように、肉片一つに至るまで袋に詰め込んだ。DNA解析につながるような肉片一片すら残してはならない。血は、この熱帯のスコールがすべて洗い流してくれるだろう。作業がすべて終了すると、キングスレーは撤収を命じた。
「ベースキャンプへ戻る。負傷者に肩を貸してやれ!」
ベースキャンプへ戻る途中、キングスレーは何か府に落ちないものを感じていた。タッツェルベルムは死んだ。任務は終わった。しかし、何故あんなに用心深い奴が、圧倒的な不利な状況下に、敢えて身を現したのだろう?そんな愚かな奴では無いはずだ。あの洞窟で感じた"気配"は、一体何だったのだろう?極度の緊張感がもたらした"幻覚"の類だろうか?しかし、任務は確実に終わったのだ。つまらぬ事は忘れ、後は国に帰ってゆっくり休もう。そう、自分自身に言い聞かせた。
一同がベースキャンプに戻る頃には、スコールは止んでいた。
けが人の応急手当をして、すぐに現地諜報員のクチンを呼んだ。バスで駆けつけたクチンは、たいそう驚いていた。なぜなら今回の任務は1週間かそれ以上かかるか、もしくは獲物に逃げられる可能性もあると踏んでいたのに、たった一日で任務が完了してしまった。しかも、負傷した兵士が四人もいる。何があったかは、一切聴かなかった。彼らが "任務終了"というからには、"終了"なのだろう。
兵士達は、ベースキャンプを速やかに畳み、機材をバスに詰め込むと、さっさとその場を立ち去った。その日のうちにボートに乗り込み、マレーシアのカリマンタン島を後にしたのだった。