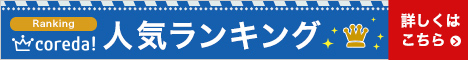入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二十九章 調査の開始
カレン・ホワイトが、ヨーク市の駅に着いたのは、午後も半ばだった。ワシントンの空港で降りてから、鉄道でボルティモアを経由してここまでやって来た。列車から降りて空を見上げると、空に雲は無く、陽が射していた。しかし時は2月で、真冬の気温は低く、冷気はダウンジャケットの下まで流れ込んで来る。
駅の改札を抜けると、一人の男がベンチから立ち上がり、ぎこちない歩き方でカレンの方に近づいて来た。ホワイトは、男に言った。
「ビンセント博士!」。
男は、マイケル・ビンセントだった。
「やあ、ホワイト博士。長旅、ご苦労さん。」
彼はそう言って、ホワイトの手荷物を手にとった。
「傷の方は、大丈夫なの?まだ、リハビリ中なんでしょ?」
と彼女が聞くと、ビンセントは答えた。
「いや、なに、病院の中を歩き回るのにも疲れてね。僕は、外の方が性にあってるよ。ただこの寒さだけはね、ちょっと・・・ハワイ生まれだから・・・。」
笑いながら、彼はぎこちない歩き方で駅の外へと向かった。歩きながら、ホワイトは言った。
「で、あとの二人はどこにいるの?大学の先生と、街の獣医さんは?」
彼は荷物を持っていない方の右手で、駅の対面にある比較的新しい喫茶店を指差した。
「向こうの喫茶店で、ずっと待ってるよ。」
その喫茶店に入ると、ビンセントは奥の席にホワイトを案内した。そこには、二人の男性が座っていた。二人は立ち上がって、ホワイトに手を差し出して握手しながら自己紹介をした。白髪の目立つ初老の男性が、生物学と遺伝学の権威、ジョージ・オーウェル博士で、若い男性の方が獣医のベン・ウィリアムスだった。
オーウェルが、ホワイトに言った。
「初めまして、ホワイト博士。貴女の事は、ビンセント博士から聞いております。たいへんな苦労をされましたね。」
彼が、鉄かぶと島の事を指し示しているのは明らかだった。ホワイトが答えた。
「それは、ビンセント博士も同じだと思います。このショックからはしばらく立ち直れそうにありませんし、正直な話し、死ぬまで忘れることはないでしょう。」
オーウェルはそれを聞いて、頷いた。
「お察しします。」
次に、ウィリアム獣医が言った。
「とりあえず私の車で、その後、ホテルまでお連れします。その後、私の医院までご案内いたしましょう。」
四名は喫茶店を出て、ウィリアムのBMWセダンに乗り込んで駅を出発した。
車の中で、ホワイトはこの街でのタッツェルベルムの調査状況の概略を聞いた。説明の最後に、運転しながらウィリアムが言った。ホワイトが特に興味を持ったのが、ブラウンの愛娘のメグがタッツェルベルムを育てて "ジョン"と名づけたくだりだった。メグは、ウィリアムやオーウェルの質問にはほとんど答えなかったらしい。軍から調査官が派遣されてきた時にも、メグは真剣に尋問には答えなかったと言うことだ。ホワイトは、ぜひメグに会ってみたいと思った。
車は市内のビジネスホテルに到着し、重要な機器類を車に残したまま、ホワイトはチェックインを済ませた。着替えの入ったバッグを部屋のロッカーに押し込み、すぐに車に戻ってきた。
「さあ、行きましょう。先生の医院に行く前に、地元の警察とブラウン博士の家に寄っていただけないかしら」。
ベン・ウィリアムは頷いて、彼のBMWを再び発進させた。
ウィリアムは、とうとうと彼の用意していた台詞をまくしたてた。単なる街の獣医でしかない彼が、世界の優れた頭脳の人々に囲まれて、国家の機密事項に携わっていると言う事実が、かれを高揚させ、一層口を饒舌にさせた。正直なところ、ホワイトはこの獣医のおしゃべりにうんざりし始めていた。彼の台詞が途切れた。
「さあ、警察に着きましたよ。」
ホワイト、ビンセント、オーウェル、ウィリアムの四人は、警察の来客室に通された。応対したのは、ベテランの巡査部長と部下の若い巡査だった。
「どうも、初めましてカレン・ホワイト博士に、マイケル・ビンセント博士ですね。オーウェル博士と、ウィリアム先生は、確か以前にお会いしましたね…。私は、巡査長のマテューです。彼は、パトリックです。」
そう言いながら、マテューはホワイトとビンセントの二人と軽く握手を交わした。
「まあ、お掛けください。」
6名は、ソファーに腰掛けた。
「所長から、皆さんに出来るだけの協力をするようにとお達しを受けています。一ヶ月以上も前にこの街を騒然とさせた、あの変てこな動物の調査を続けておられるとか?」
ホワイトが応えた。
「はい。あの動物は、ワシントン条約に触れる極めて希少な動物である可能性が高いのです。ご存知かもしれませんが、こちらのオーウェル博士はその道の専門家で、ご助言をいただくため、お忙しい中お時間を割いてもらっています。獣医のウィリアム先生には、そのお手伝いをしていただいています。」
もちろん話しは嘘であったが、それが嘘である事を知らないのは、この六名の内、この警官の二人だけだった。マテュー巡査長が、短い口ひげに触れながら言った。
「目撃者からの調書は、前にオーウェル博士とウィリアム先生にお渡ししました。」
ホワイト博士が、軽い笑みを浮かべながら言った。
「ええ、その調書はすでにファクシミリで送っていただいて拝見しております。その後、新たな目撃情報はありましたか?」
マテューは、まっすぐにホワイト博士の目を見ながら言った。
「いえ、その後はまったく目撃情報はありません。」
「そうですか…。」と、ホワイト博士。
来客室にはしばし沈黙が訪れたが、その後口を開いたのは若い警官のパトリック巡査だった。
「その動物は、一体どんな種類なのですか?目撃者の中には、犬だったと言う者もいれば、猿のようだったと言う者もいます。いくら動物に詳しくなくても、犬か、猿かぐらいは普通は区別が付くでしょう?うちのお袋だって分かりますよ、そのぐらい。犬か猿かも判別できない珍しい動物って、どんな奴なのですか?」
定型通りの返答をしようかとホワイトが考えていると、ビンセントが先に口を開いた。
「実は、私たちもその目撃情報だけでは、確定できないでいます。いずれにせよ、どこかの誰かさんがワシントン条約を破って、違法に輸入した動物が逃げたのではないかと考えています。」
ホワイトが、その発言の後を受けた。
「その通りです。何か、新しい情報があったら私の滞在しているホテルか、ウィリアム先生の所にご連絡ください。」
そう言って、訪問者一同は立ち上がった。マテューとパトリックも立ち上がって、マテューがパトリックを指し示しながら言った。
「分かりました。町の事で知りたい事があったら、このパトリックに相談して下さい。毎日パトロールをしていて、町の事は路地裏まで知っていますから。」
「ありがとうございます。」
そう言って学者と獣医の計四人は、来客室を出て、警察署を去った。
残ったマテュー巡査長は、パトリックに言った。
「嘘つき学者どもめ!何が、珍しい動物の調査だ!うちの堅物署長が、たかが動物の調査のため全面協力をするはずがないだろうが!うちは、衛生局や環境省じゃないんだ。どこの政治家か役所かは知らんが、署長に圧力がかかったにちがいない。パトリック、奴らから目を離すんじゃないぞ。逐一報告しろ!」
パトリックは答えた。
「はい、了解しました」。
警察署を出たホワイト達一行は、次に故ブラウン博士の家に向かった。もちろん、メグに会うためである。彼ら四人がブラウン家に付くと、母親のエリーが応対した。エリーは、夫のアルバートの死の報を先月受け取り、葬儀の後から今に至るまで深い悲しみにとらわれていた。実験施設での事故であるとの報告を受けたが、遺体の損傷が激しいとの事で、最後まで遺体を見ることなくブラウン博士の遺体は火葬にふされた。ホワイト博士も元の上司の死を悼み、エリー夫人に慰めの声をかけた。しかし、肝心のメグは最後まで学者達との面会を拒んだ。仕方無しに、四人はウィリアム獣医の医院に戻って、今後の対策を練る事にした。