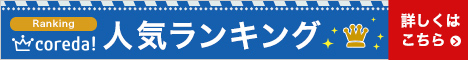入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二十八章 ジョンの生活
ショッピング・センターの廃墟にジョンがやって来てから、一ヶ月以上が経っていた。彼はここでの生活にもなれ、その生活にもリズムが出てきた。
陽が昇ってから沈むまで、彼は本を貪るように読んだ。教師や親や友人がいない彼にとって、本こそが彼の教師であり導き手であり友であった。彼は、本を通して広い世界に触れ、本を通して孤独を癒し、本を通して政治や社会や経済の複雑なシステムを理解し、本を通して芸術や娯楽に触れた。
彼が本以外で本物の社会に触れるのは、唯一夜間のみであった。彼は、下水管を通って市内のどこへでも出没することができた。真冬の真夜中は人通りがほとんど無かったが、それでも彼は細心の注意を払って路上へ出た。また、道を歩いているのを発見された時に怪しまれないように、ショッピング・センターで見つけたボロボロのズボンやジャンパーなどを着込み、汚れた靴を履き、頭は帽子とジャンパーのフードで隠した。どこから見ても、立派なホームレスである。
ジョンが街中に出て行くのには、主に二つの目的があった。一つは、メグの近況を知るためにブラウン家の近くに赴くことである。もう一つは、 "買い出し"のためである。もちろんお金はもっていないから、店から勝手に拝借してくるのである。彼は、これを"買い出し"と呼んでいた。
彼は、どんな店がどの場所にあるのか、それらの閉店時間が何時なのか、そう言う情報を、今ではほとんど知り尽くしていた。彼が "買い出し"に行く店は、二十四時間オープンでなく定時にきちんと閉まる店、防犯カメラ等が設置されていないような個人経営の小さな店、人通りが無くかつ近所に吠える犬がいない店等だった。彼はそれらの店の中から、鍵などが開けやすくて侵入しやすい店のリストを頭の中に作成した。彼の明晰な頭脳と手先の器用さは、ドアの鍵を開けるのに大きく役立った。田舎町である事が幸いしたのかもしれないが、頑丈な鍵を付けている店もあまり多くはなかった。
ジョンは狡猾だったので、一度にたくさんの商品を盗むような真似はしなかった。一度に持ち出す商品は、パック入りの食品や缶詰などをたった一、二品と、本や雑誌が一冊だけだった。時折、何本かの乾電池も拝借することがあったが、その程度だった。もちろん、現金には一切手を付けない。この点が重要で、現金を盗まないので侵入がばれないのだ。実際のところ、彼が現金を手にしたとしても、街のどこにも使える場所は無かったが。彼は、それ以外の物は持ち出さなかった。しかも同じ店には立て続けに侵入せず、最低一週間の間隔を開けた。一週間に缶詰一個か二個なくなったことに気づく店主は、まずいなかった。彼は侵入と同様、店からの退出にも気を使った。彼が侵入した事を悟られないために、入る前と同様に丁寧に鍵を掛けてからその場を去った。少なくとも、過去一度も警察や店主に見つかって追いかけられたことはない。
彼は、時折夜間に川で魚を捕ったり、小動物を狩ることもあったが、それは食べるためと言うよりは彼のレジャーに近かった。もちろん食べもするのだが、ハンティングと言う行為は、ジョンにとってこの上ない快感なのである。
買い出しやハンティングを終えると、彼はショッピング・センターの彼の隠れ家に帰り、夜の食事を楽しんだ。食事の後、乾電池を補充した携帯テレビのスイッチを入れて、深夜の番組やニュースを見るのも好きだった。その後、日が昇るまで横になって眠るのである。そして日が昇ると、また読書を始めるのだ。これが、彼の一日のサイクルだった。
この一ヶ月で変わったのは、ジョンの生活サイクルだけではなかった。体も成長を続けていた。一ヶ月の間に、ジョンの体はどんどん大きくなった。おそらく二メートル近くに達しているのではないだろうか。そして毛が抜け始め、皮膚が硬くなっていった。彼が筋肉に力を入れると、彼の皮膚はコンクリートか鉄板のように硬くなるのである。毛が完全に抜け落ちると、かつてのジョンの面影は全く無くなった。
トイレで半分割れた鏡を発見した時に、彼は鏡に映った自分の姿を見て愕然とした。空想映画やマーベル・コミックで描かれるモンスターそのものの姿だったからだ。これでは、メグが自分を見ても気が付かないかもしれない。気が付いたとしても、悲鳴を上げるかもしれない。そう思うと、彼は悲しみに沈んだ。
彼は自分が何者か知るため、たくさんの本を読んだ。しかし、彼と同じ姿の生物の記述はどこにもなかった。彼は、一体どこから来て、どこへ行くのだろう。彼は、今一人ぼっちだった。
ある夜、ジョンはいつものよう"買い出し"から帰って来た。今日の彼の収穫物は、牛肉五百グラムが入ったパックとタブロイド新聞が一冊だった。彼は超レアステーキ…要は生肉である…の夕食を開始するよりも先に、タブロイド新聞の"ウィークリー・ワールド・レコード"を開く方を優先した。それほどまでに、彼の知的好奇心は飢えていたのである。そのタブロイド版の新聞の記事は、ほとんどがどうでも良いゴシップ記事と馬鹿馬鹿しい空想記事で埋め尽くされていた。
ジョンは、ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズのようなお堅い新聞も好きだったが、こう言う芸能記事や捏造記事で埋め尽くされたような胡散臭いタブロイド新聞もまた好きだった。世間の建前とは裏腹の、人々の本音や嗜好と言うものが伺えるからだ。
ジョンが社会面、芸能面と紙面をめくっていき、外国のトピックスのページを開いた時、彼の目はそのページに釘付けになった。そのページの左端には、小さな記事がイラストと共に掲載されていた。彼は、我が目を疑った。そのイラストには、彼を模写したに違いないと思われるような姿が描かれていた。彼は、そのイラストから記事に目を移した。記事には、次のように書かれていた。
"最近、東南アジアのマレーシアの地方、サンダカン付近の村々で家畜が惨殺される被害が相次いでいる。地元の新聞記者の話しでは、虎よりは小さい、猫科の野生動物のせいではないかと言う事だ。しかし一方で、その説に反対する声も一部に上がっている。地元の住民Sさんは、唯一この加害生物を目撃した人物だ。彼は、家畜を襲ったのは今までに見たことも無いような、恐ろしい姿をした怪物だったと語っている。右のイラストは、Sさんの証言に基づいて書かれたモンスターの姿だ。しかし、モンスターは用心深いせいなのか、何故かSさん以外には目撃されていない。家畜を襲ったのは、猫科の生物なのか、Sさんの言うように未知の怪物なのか。いずれ明らかになる日が来るでしょう。"
記事は、そう閉じられていた。ジョンは、その紙面をずっと見つめていた。自分は、世界で一人ぼっちなのではない。地球の裏側に、彼と同じ姿をした仲間がいるのかもしれない。否、彼が考えているより多くの中間達がいるのかもしれない!彼の心のうちに、久しぶりに明るい希望の光が差し込んだ。彼は、そのタブロイド新聞を大事に折りたたんで、ボロボロのジャンパーのポケットの中にしまった。