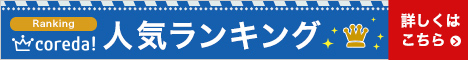入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二十五章 一夜の攻防戦
キングスレー少尉とダン一等兵が砂浜に戻った時、時刻は既に17時を過ぎていた。砂浜の一同は、広場で物凄い爆音と共に炎が上がったため、心配しながら四人を待っていた。広場からの無線連絡はなく、15分後に戻ってきたのは結局二名だけだった。キングスレーの顔は火傷で真っ赤になり、火脹れができていた。キングスレーは砂浜に下りて来ると、木陰に倒れ込んだ。キーファー一等兵が即座に歩み寄り、水筒の水を顔にかけた。そして、救命パックから薬とガーゼを取り出し、キングスレーの顔や腕の治療を始めた。
ロイ一等兵とローランド二等兵も、林の中に銃を向けながらダンの側にやって来た。研究員達も、すぐその後に彼等の所へやってきた。ダンは、状況を手短に説明した。
「なんてこった!ノートン伍長と、ロックウェル上等兵までやられたのか!」
ロビン・ウォーカーが、怒りを込めて言った。その後、カレン・ホワイト博士も小さな声で言った。
「死んだタッツェルベルムは、おそらくノッポよ。残りの二匹は、暴れん坊とチョコマカに違いないわ。」
ダンは、報告を続けた。
「奴らには、確かに何発か当たった。しかし、何事も無かったかのように走り去ったぞ。」
サム・シュルツ博士が、その疑問に答えた。
「彼らは、非常時には"キャッチ結合細胞"を萎縮させて、細胞の外側の骨片組織を硬く閉じてしまう。恐らくダメージが少なかったのだろう・・・。しかし、無傷と言うことはないと思う。そこまでは、外皮は硬くはないはずだ。」
マイケル・ビンセント博士は、それに付け加えていった。
「彼等が負傷しているなら、早めに始末をつけたほうが良い。彼等の代謝は以上に早くて、ケガの治りもとても早いから。」
陽は次第に傾き、辺りは暗くなり始めた。太陽光線の届かない林の中は、かなり暗くなっていた。キングスレーの火傷の大急処置が終わると、キングスレーも話しの輪に加わった。キングスレーの顔は、半分以上がガーゼで覆われテーピングされていた。ガーゼの合間から、目と口が見えた。火傷で顔中が痛いせいか、口を小さく動かした。
「ボートは東の桟橋にあるが、暗い島の中をこれから移動するのは危険だ。奴らは夜目が利くし、おまけにピット器官で体温まで感知できると言うからな。一方、こちらにはナイト・ビジョンは二つしかないときている。ノートンの持っていた衛星回線用の無線は吹っ飛び、本国との連絡は取れない。私の持っていた無線もぶっ壊れた。残った一台では、もはや何の役にも立たない。」
彼は、そこで疲れたのか一息ついた。
「奴らは、こちらが思っていたより利口らしい。今、島の中をうろつくのは得策ではない。朝を待ち、日が昇ってから移動しよう。」
それから、一同にしゃがむように手で合図した。一同は、その場に座った。
「残りの二体の奴らが、どういう行動を取るかはわからない。しかし、我々に罠を仕掛けるくらい頭の良い奴らだ。警戒は、怠らないようにしよう。クレイモア地雷はないが、まだP7型爆薬と信管が少し残っている。砂浜と林の境に、等間隔に爆薬をセットする。テントは、林から遠ざけ、テントと林の間にタコ壺を五つ掘る。それから、今夜は、隊員は不眠で警備をしてもらう。一夜の辛抱だ。私とローランドは北側の、ダンとロイは南側の守備だ。キーファーは、地雷爆破を受け持ってもらう。各自、66ミリ対戦車ロケットとグレネード・ランチャーは、いつでも発射できるようにしておけ。」
「了解。」
と、隊員達は頷いて言った。キングスレーは、次に研究員達の方に顔を向けた。
「研究スタッフも、テント付近の陣後を可能な限り守ってもらう。二台のスポットライトは、いつでもオンにして林を照らせるようにしておいてくれ。銃も、取り扱える人間は、いつでも撃てるようにしておいてくれ。ただし、合図があるまでは撃つな。前線の仲間に当たっては、元も子も無いからな。食事は、残念ながら暖かい料理を作っている余裕はない。全員、軍用の携帯糧食を食べてもらう。」
研究スタッフ達も、黙って頷いた。
隊員達は、即座に大型のテントと簡易トイレ用のミニ・テントを、木の下から砂浜の方へと移動した。キングスレーとキーファーが見張りにつく中、ローランドとロイが砂浜に五つの小さな塹壕を掘り、ダンがP7型爆薬を等間隔にセットした。
一同が作業を終える頃には、日は完全に沈んでしまった。一番北側の穴にダンが入り、二番目の穴にキーファーが、中央の穴にキングスレーが、次の穴にロイが、最も南側の穴にはローランドが入った。二つの暗視ゴーグルのうち一つは地雷担当のキーファーに渡し、もう一つはキングスレー自身が着けた。
太陽は沈んでしまったので林の中は真っ暗だったが、月と星の明かりによって、砂浜はある程度の明るさがあった。研究員達はテントの中で眠る気になれず、テントの外へ出て軍の糧食をかじりながら、それを水筒の水で胃の中に流し込んでいた。
砂浜に波が寄せては引いていく音だけが、周囲に響いていた。太陽が沈んでから二時間経ったが、何事も起こらなかった。夜九時を回った頃、所長のスチュアートが立ち上がった。隣に座っていたビンセントが言った。
「所長、どちらへ?」
「あれだよ。」
そう言って、彼はトイレ用のミニ・テントを指差した。ビンセントは、それ以上何も言わなかった。スチュアートはトイレで用をたした後、海岸の方へ歩いて行き、暗い海を眺めていた。スチュアートは、振り返り島の方を見た。テントやミニ塹壕の前に積み上げた砂の輪郭が、月明かりで浮き出ていた。彼は思った・・・・今夜は、何も起こらなければ良いのだが。既に十分な犠牲は払ったのだから。
スチュアートは、海岸からテントの方へ戻ろうと足を一歩踏み出した。と、その瞬間、首に何か冷たい感触がした。彼は手で、首を触ってみた。冷たい液体が、手にべっとりと付く。次の瞬間、彼は一言も発することができずに、その場に倒れた。
海岸の波打ち際で何かが倒れる音を聞き、テントの一同はそちらを振り返った。塹壕内のキングスレーも振り返り、波打ち際をナイト・ビジョンで見渡した。
「くそ!海からだ!ライトを海岸へ向けろ!ロイ、一緒に来い!後は、タコ壺で待機!」
そう言いながら、既にキングスレーはM16を構えながら塹壕を飛び出していた。少し遅れて、ロイが塹壕を飛び出した。テントの側のウォーカーとビンセントが、林に向けられていた強力なスポットライトを、それぞれ波打ち際に向けた。照らし出されたのは、立ち尽くす一体のタッツェルベルムと、その前に倒れているスチュアートの姿だった。スチュアートの首から、真っ赤な血が流れている。ウォーカーは、叫んだ。
「所長がやられた!」
キングスレーとロイが、ほぼ同時にM16の引き金を引いた。しかし、テントが近いので擲弾は発射できなかった。キングスレー達が引き金を引くや否や、タッツェルベルムは海へ飛び込んだ。キングスレーとロイは、海に向かって撃ち続ける。前線の隊員も、塹壕に留まったまま振り返って海岸の戦闘を見守った。
すると今度は突然、キーファーが叫んだ。
「中からも来たぞ!」
ダンとローランドは、林の方に振り返った。二人は暗視ゴーグルを持っていないので、林の中の様子が分からなかった。
「キーファー、どっちだ!」と叫ぶダン。
「北だ!おまえのすぐ側だ!爆破する!」
キーファーは、爆破スイッチを押した。その瞬間、林と砂浜の境で爆発が起こった。周辺を眩しい光が包み、激しい炎が上がったが、一瞬にして暗闇が戻ってきた。ダンは、叫んだ。
「キーファー、奴はどうなった!」
キーファーは答えた。
「煙で、よく見えない!スポットライトを照らせ!」
ビンセントは、海岸を照らしていたスポットライトの一つを北側の林に向けた。そこには、爆薬の煙が漂っていた。その煙が風で流されると、ダンの塹壕の真ん前に佇むタッツェルベルムの姿が映し出された。次の瞬間、ダンの首が数メートル飛んで行くのが、一同の目に映った。一番離れた南側のローランドがM16の引き金を引いたが、タッツェルベルムの動きは機敏で、すぐさま林の中へと走り出す。キーファーは間髪入れず、爆薬のスイッチを押した。もう一度、大きな爆発が起こった。
キングスレーは、ロイを海岸の警戒に残したまま、塹壕の方へ戻った。しかし、彼が塹壕へ戻った時、既にタッツェルベルムの姿はなかった。
スポットライトを海岸と林の方に照らしたまま、一時全員がテントまで撤退した。隊員達は、スチュアートとダンの遺体を他の遺体達が包まれているシートの中へと運び込んだ。
隊員達は、四方を警戒しながら会話を始めた。キングスレーが、研究スタッフ達を睨みつけて毒づいた。
「奴らが泳げるとは、誰も一言も言わなかったぞ!」
誰も答えなかった。何故なら、研究員達もタッツェルベルムの水中のデータを一切持っていなかったからである。
「困ったことになったな・・・。残りの人数で、ここを一晩死守しなきゃならん。計画の建て直しだ。」
たった一日のうちに、五人もの部下を失うとは・・・。アフリカの戦闘でもなかったことだ。奴らは、確実に一人ずつこちらの人数を減らしている。最初は、圧倒的にこちらが有利だった。不利な状況でのヒット・アンド・アウェイ戦法・・・狡猾な奴らだ。狩りをしているのはこちらでなく、もはや奴らの方かも知れない…キングスレーは、今こそ冷静になって判断すべき時だと、自分に言い聞かせた。
キングスレーは、残りの隊員と自分自身の四人を、テントの東西南北に振り分けた。北をキーファーに、東をローランドに、西をロイに任せ、自分は南の配置に付くことにした。爆破していない残り五つの爆薬は、そのままにしておいた。人数が僅か四名になってしまったので、爆破担当のキーファー以外の三名が203擲弾発射装置付きのM16を持ち、またローランドとロイが、66ミリ軽対戦車ロケットの発射を受け持った。
キングスレーは、若い隊員たちに言った。
「いいか、奴等の陽動作戦に乗るな。奴らがどこから攻めて来ようと、持ち場を離れず、警戒を怠るな!さっきのように、二匹目は一匹目の反対側から襲ってくるかもしれない。分かったか?」
隊員達は答えた。
「了解。」
それから、キングスレーはロイの方を向いて言った。
「スポットライトのバッテリーは、あとどのくらい持つ?」
ロイが答えた。
「持って、せいぜいあと二時間です。」
「よし、消せ。」
そう言うと、ウォーカーとビンセントはライトを消した。辺りは、再び静寂と月明かりとそしてタッツェルベルムの支配する世界となった。
時計は、そろそろ零時を回ろうとしていた。後、六時間もすれば夜明けである。兵士達と同様、残り四人になってしまった研究員達は、テントの脇でスポットライトの番を交替でしていた。研究員達は、二人のリーダーを同じ日に失った。ブラウン博士に続いての、スチュアート所長の死は、一同の悲しみと怖れをさらに強いものにしてしまった。長い沈黙の時が続いていたが、ビンセントがライトのスイッチに指をかけたまま、静かにポツリと言った。
「前から疑問があったのだけど、生き残れるかどうか分からないし、どうしても今聞いておきたい。」
「なんだよ、急に。何だ?」
やはりライトのスイッチに指をかけたまま、ウォーカーがそう返した。ビンセントが続けた。
「超軍事機密だから、本当はこれを言うと軍法会議ものなんだけど・・・。納得いかなくてね・・・。以前、ブラウン博士にある細胞の培養を頼まれたんだ。博士によれば、水掻きがあるタイプの水中用のタッツェルベルムらしいんだ。」
それを聞いて、ホワイトが口を挟んだ。
「そんな話、今初めて聞いたわよ。」
ビンセントが言った。
「そりゃあ、そうだろ。超軍事機密を皆が知っていたら、超機密にならないじゃないか・・・。で、この水掻きタイプの遺伝子組み替えをやったの、君なんだろ、ウォーカー?」
「それに答えたら、僕も軍法会議行きだな・・・。」
ウォーカーはしばらく黙っていたが、こう言った。
「ああ、確かにブラウン博士に頼まれて、水掻きタイプの遺伝子組み替えをやったよ。ついでだ、シュルツ。君も、一緒に軍法会議行きに加われよ。遺伝子の設計をしたのは、君なんだろ?」
二人の足元にいるシュルツは、使えもしない拳銃を握らされていた。彼は、黙って頷いた。この会話を聞いていたホワイトが言った。
「はっ!私だけ、仲間外れって訳ね。でも、聞いちゃった以上は同罪ね・・・ついでだから、軍法会議にも付き合ってあげるわ。で、ビンセント、あなたの疑問って何?」
「そう、この水掻きタイプなんだが、幼体の成長過程で水掻きが消えてしまったんだ、完全にね。ブラウン博士は、成体になる頃にまた生えてくるって言ってたけれど、そんなことってあるのかな?どう思う?ウォーカー?」
「そう言われてもな・・・。俺は、設計図通りに遺伝子を組み替えるだけだし、培養の結果までは分からんよ。俺は、ブラウン博士からもらった5番と書かれたディスクの設計図通りに、忠実に組み替えただけだ。」
今までずっと黙っていたシュルツが、顔を上げ急に口を開いた。
「今、何て言った?」
「俺は、設計図通りに遺伝子を組み替えただけだ、って言ったんだ。・・・ああ、これは別に、君の設計図に対する批判のつもりはないよ、シュルツ。」
そうウォーカーが言うと、シュルツは強く言った。
「そうじゃない。その後だ。今、5番のディスクの設計図って言ったかい?間違いない?」
ウォーカーは頷いて言った。
「ああ、間違いない。組み替えが完成するまで、毎日そのディスクを眺めていたんだから。5番だったよ。」
シュルツは、両手で頭を抱え込んだ。ブラウンとスチュアートの死に、ウォーカーの答えが追い討ちをかけてしまったかのようである。ホワイトが言った。
「どうしたっていうの、サム?」
シュルツが、頭を上げて答えた。
「水掻きタイプのディスクは、1番だ!5番のディスクは、人間の頭脳を持ったタイプのタッツェルベルムだ!」
博士達の間の空気が、一瞬凍った。
「しかも、その設計のベースに用いた脳と言うのが、ブラウン博士のものなんだよ!!」
ウォーカーが言った。
「おお、何てこったい!遂に、人間の、しかも脳みその遺伝子に手を出しちまったのか!」
シュルツが、自己弁護するように付け加えた。
「ブラウン博士は、設計だけで実際に組み替えはしないと約束したんだ。データだけ取りたいって・・・。」
ウォーカーが言った。
「みんな、ブラウン博士には絶対の信頼を置いていたからな・・・。で、その培養した幼体は処分したんだろ?」
ビンセントは、首を横に振った。
「ブラウン博士は、12月に幼体を本国へ送ってしまった。」
「何てこったい、何てこったい!あんなに凄い能力の奴に、天才の頭脳が加わったら鬼に金棒だ!帰国したら、あれを処分するようにすぐさま軍のお偉方に抗議しないと!」
ビンセントがそう言い終わらないうちに、テントから少し離れた南側に陣取ったキングスレーが言葉を遮った。
「BGM代わりに全部聞かせもらったが、その心配は生きてこの島を出てからにしてくれないか!林の中に、嫌な気配が漂っている。静かにしていてくれ!」
一同は、全員口を閉じた。
木々の向こうから、確かに何かが彼らを狙っている気配が感じられた。キングスレーは、過去の二回の彼等の行動から、彼らが同じ攻撃方法を取るとは思えなかった。一回目の食堂での罠と、二回目の海岸側からの陽動作戦。三回目は、どんな方法か?何か、彼が見落としていることはないだろうか?東西南北は、まんべんなくしっかり見張っている。海からの攻撃に対しても、抜かりはない。いくら何でも、空を飛ぶなんてのは無しにしてくれよ…。奴らは、どう出てくる?
時計は、二時を回った。あと約四時間で夜明けだ。一日中、不眠不休で行動していた隊員達だが、緊張感が眠気を上回っていた。キングスレーが言った。
「キーファー、何か見えるか?」
「いえ、何も。隊長の方は、どうですか?」
「こっちも何も見えない。ただ、嫌な気配がする。注意を怠るな!」
時計は、三時半を回った。夜明けまで、もうあと僅かである。今夜は、もう何も起こらないかもしれない。彼らも、わざわざ危険を冒してまで、これ以上攻撃するつもりはないのかもしれない。そんな安堵感が訪れ、隊員達に眠気が襲ってきた。
タッツェルベルムは、辛抱強くその時を待っていたのだろうか。突然、一体のタッツェルベルムが東南の木々の中から飛び出してきた。キングスレーは、叫んだ。
「撃て!キーファー、スイッチ!」
ほんのちょっとの遅れだった。一瞬の眠気と気の緩みが、爆破のスイッチを押すタイミングを遅らせた。タッツェルベルムが林から出てしまってから、爆発が起こった。タッツェルベルムの外皮は、爆風と背後の炎に耐えた。キングスレーはM16を撃ちながら、叫び続けた。
「北側を警戒!」
ビンセントは、スポットライトのスイッチを押した。南のキングスレーと、東のローランドが、タッツェルベルムに銃弾を浴びせ掛けた。タッツェルベルムは体中に銃弾を浴びながらも、尚もテントの方へ走ってきた。彼がローランドの数メートル手前まで来ると、実戦経験の無い若い彼は、恐怖のあまり立ち上がって後方に駆け出してしまった。しかし、タッツェルベルムの走る速度に、生身の人間が敵う訳がなかった。
「だめだ、ローランド!留まって、撃て!」
彼が、北に移動したタッツェルベルムを攻撃していると、テントのビンセントが叫んだ。
「少尉!後ろに奴が!」
なんと二匹目のタッツェルベルムも、一匹目と同じ東南から飛び出してきた。
「キーファー、ロイ、二匹とも南だ!」
キーファーは、残りの爆薬のスイッチを闇雲に押しまくった。林と砂浜の境のあちこちで、爆発が起こった。ウォーカーも、ライトを林の方に向けた。キングスレーは、グレネードを発射した。タッツェルベルムは、擲弾を素早く避けた。擲弾は、遥か後方の林の中で爆発した。一匹目のタッツェルベルムが、ローランドに追いついた。彼は、片手で軽々とローランドを前方で羽交い絞めにした。キーファーとロイは、ローランドがいるので撃てなかった。二匹目が、すぐ一匹目の背後に迫った。二匹目の奴は、一匹目とローランドを盾にするつもりかもしれない・・・そうキングスレーは思った。キングスレーが、怒鳴った。
「グレネードを発射しろ!」
「ローランドは、生きてます!撃てません!」
キーファーが応えた。ロイも、同様に撃てなかった。若い兵士の実線経験の無さが、すべて裏目に出てしまった。キングスレーは、二発目の擲弾を発射するためにランチャーに弾を込めた。しかしそれよりも早く、一匹目はローランドをつき離して、北側のキーファーの方へ駆けていった。キーファーとロイは、激しく銃弾を浴びせ掛けた。タッツェルベルムの外皮と肉片と血が、そこかしこに飛び散っていた。
二匹目のタッツェルベルムは、反対にテントの方へと駆け出し、あっという間にテントまで辿り着いた。さすがにキングスレーも、四人の博士を道連れに擲弾を発射することはできなかった。タッツェルベルムは、スポットライトの操作をしていたウォーカーとビンセントの二人をなぎ倒した。スポットライトの片方が消えた。タッツェルベルムは、二人の足元に座っていたシュルツとホワイトを睨んだ。シュルツは、銃を構える暇もなかった。タッツェルベルムはシュルツの胸をその鋭い爪で引き裂いた後、ホワイトの顔に向かって鋭い歯の並ぶ口を大きく開いた。ホワイトには、それが"暴れん坊"だと分かった。
一匹目のタッツェルベルムは、血だらけになりながらキーファーの元に辿り着き、彼を一打でその場に打ち倒した。しかし、後方からロイが絶え間なく銃弾を浴びせ掛けた。タッツェルベルムは、その場に倒れこんだ。しかしその場に膝を付きながらも、悲痛な叫び声を上げながら、林の方へ逃げ出そうとしていた。キングスレーは、グレネード・ランチャーから擲弾を放った。弾は見事に命中し、タッツェルベルムはバラバラに吹っ飛んだ。
二匹目は、テントから立ち去ろうとしていた。キングスレーは、彼に銃弾を浴びせながら叫んだ。
「ロイ!ロケット!」
ロイは北側から引き返し、66ミリ軽対戦車ロケット発射装置を拾い上げた。二匹目のタッツェルベルムは、体中にキングスレーの銃弾を浴びながらも、素早く海の中へ飛び込んだ。
「発射!」
キングスレーが叫ぶと、ロイは発射装置を構えてロケットを発射した。ロケットは海面で爆発した。二匹目を仕留めるのに、間に合ったかどうか・・・。とにかく、周囲からタッツェルベルム達の気配はなくなった。少なくとも、二匹目も相当な重傷を負ったはずだ。しばらく、奴も攻撃は無理だろう。
戦闘が終わった後の砂浜は、凄惨だった。人間の血とタッツェルベルムの血や肉片が、あちこちに飛び散っていた。生き残ったのは、キングスレーとロイと、そして何故かホワイト。ローランドは生き残っていたが、かなりの重症だった。ビンセントも肋骨を折り、内臓を破裂しているようだった。キーファーとウォーカーとシュルツは、即死だった。
生き残った人間達は、死体を遺体用のシートの中へと運んだ。昨日の朝は15人いたのに、今朝生き残ったのは僅か五名。うち二人は、重傷だった。たった三体の獣を倒すには、十分に高い代償だった。
キングスレーは、重傷の二人が一刻の猶予もないことを知り、日が完全に昇りきらないうちに移動することを決意した。キングスレーはローランドを背負い、ロイはビンセントを抱えた。ホワイトは、最低限の武器を持たされた。五名は、次第に明るくなっていく島の中を横断した。今襲われたら、一たまりもないだろう。応戦する手が、まったくなかった。しかし、最後のタッツェルベルムも重症か、もしくは死んだようで、彼らは無事に東の桟橋まで辿り着くことができた。
五人は、二層用意してあったボートのうち一層に乗り込む。解決すべき問題は山積みだが、後の事は後で考えよう・・・今は、重傷の二人を救うことが先決だ。キングスレーはそう思い、ボートのエンジンをかけた。ボートは静かに"鉄かぶと島"を離れ、日が昇りきった頃には、島からは見えなくなっていた。