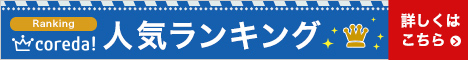入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二十四章 初めての外界
パニックを起こして家から飛び出したジョンは、訳もわからずに一キロ以上走った。全速力で二本の足で駆けた。途中、ジョンとすれ違った女性や子供達の悲鳴が聞こえたが、彼は止まらずに走り続けた。初めての外の世界だったので、彼は人目から自分を隠す方法と場所を知らなかった。おそらく十名以上の人々に、彼は見られてしまったに違いない。
ようやく冷静さを取り戻したジョンは、大きな茂みに身を隠した。しばらくその場所に潜んでいたが、小一時間ほどすると、彼は家から離れたことを少し後悔した。もしかしたら、メグとエリーがなんとかしてくれるかもしれない。ジョンは意を決して、家に戻ることにした。今度は、人目に付かないように気をつけなければならない。犬を装うため四つ足で歩き、なるべく裏通りの物陰を通りながら家へと戻る道を辿った。
家に辿り着いたジョンだったが、家の近辺に近づく事ができなかった。赤と青のライトを点滅させる車が、家の前に停車していたからである。彼は、家の窓から何度かその車を見たことがある。メグの図鑑によれば、警察のパトロールカーと言う車らしい。しかし、ジョンは警察官が何をする人たちなのか知らなかった。通りの向かいの茂みに身を隠しながら、ジョンは様子を伺った。二名の警官が、玄関でエリーと話していた。後ろには、心配そうにしているメグの姿が見えた。
ジョンの鋭い視力は、窓ガラスを通して、家の中に先ほどの獣医と学者の二人がまだいるのを見つけた。視力と同様、彼の高い聴力は警官達の話しを聞くことができた。
「奥さん、実はこの辺に猛獣がうろついているらしいのです。二本足で走っていたと言うので、飼っていたチンパンジーか何かが逃げ出したのかもしれません。何か目撃されていたり、ご存知の事はありませんか?」
そう言われて、エリーの表情が曇るのが分かった。エリーが口篭もっていると、奥から獣医のベンが出てきた。そしてエリーに代わって、警官に言った。
「私は獣医ですが、何かお役に立てるかもしれません。その動物の特徴は、どんなものですか?」
警官は答えた。
「目撃談によると、全身がこげ茶色の毛に覆われていて、体長は百五十センチ前後。口には、鋭い牙が生えているそうです。一瞬見た目は犬のような感じだそうですが、二本足で走り去ったそうです。動物の種類は、よく分からないそうです。複数の目撃者の証言はまちまちですが、犬とは断言できないようです。」
そう言われて、獣医ベンの目がきらりと光るのを茂みの中のジョンは見逃さなかった。メグは、口を閉ざしうつむいていた。警官は、続けて言った。
「もし、この辺りで見かけることがあったら、すぐご連絡ください。危険が予想されるので、戸締りはしっかりお願いします。」
その後、警官はメグとエリーの家を離れ、隣の家の玄関に向かった。メグの家の玄関のドアは閉じられた。窓を通して家の中を見ると、ベンがしゃがみこんでメグに何か言っている様子が見えた。おそらく、彼…ジョンのことを問い詰めているのだろう・・・。ジョンは、音を立てないようにしながら、静かにその場を立ち去った。
どのくらい歩いただろうか。辺りには夕闇が訪れようとしていた。冬の太陽は、早々と地平線の彼方にその姿を消そうとしている。茂みや裏通りを、人目につかないようにゆっくりと犬のように四つ足で歩いた。人の歩く音が聞こえると、その気配が消え去るまでじっと物陰から動かなかった。
やがてジョンは、家々の疎らな通りの外れまでやってきた。
通りの向こうには、川が流れている。写真ではなく、本物の川を見るのはこれが初めてだった。こんな形で、外界と接する形になるとは・・・。川の両岸は、平らな場所と藪や木々で覆われた場所に分かれていた。彼は、車が左右から来ない瞬間を見計らって、通りを横断して藪の中へ飛び込んだ。
藪の中から周囲を見渡すと、川原で釣りをする何人かの人がいた。冬用の防寒具に身を包み、釣り竿を川に向かって振り下ろしていた。しかし、日が暮れようとしていたので、徐々に釣り道具をしまい込み、一人また一人と引き上げていった。周囲が真っ暗になる頃には、川原には誰もいなくなった。ジョンは、とりあえずホッとした。これで、しばらくは見つかる心配は無いだろう。ジョンの鼻腔の両側にあるピット器官が、夜の街中の光景をしっかりと捉えていた。周囲と温度差のある川原を蠢く小動物、川原の上の通りを歩いている人間の姿、すべてをはっきりと知覚できた。しかし暗闇の中で、人間の方が彼の姿を見つけることは不可能だろう。
彼は、非常な空腹感を感じた。最後に食べたのは、朝食の缶詰のドッグ・フードだけだった。それ以来、今に至るまで何も口にしていない。彼の異常な空腹感が、彼の高い新陳代謝の代償であることを、今のジョンが知る由もなかった。しかも、真冬の冷たい気温は厳しかった。今まで屋内で暮らしてきたジョンにとっては、毛皮がある身とは言え辛かった。おまけに、この空腹である。彼は、メグの暖かい部屋を思い起こした。最近まで飲んでいたミルクの味、最近になって食べ始めたドッグフードの食感、そして何よりもメグの笑顔・・・すべてが遠い昔のように覚えた。彼は、小さな声で一声唸った。その後、身を丸めて藪の中で寝入った。
寝入ってからしばらくして、雪が舞い始めた。次第に本格的に降り始め、深夜に達する頃にはかなり積もり、ジョンもそのまま川原で寝ている訳にも行かなくなった。ジョン自身の本能は"どんなに極寒の状況でも彼は生きられる"と訴えていたが、彼自身は自分が"仮死冬眠状態"で生き延びられることなどまったく知らなかった。
川原の周囲に誰もいないことを確認すると、ジョンは藪から出た。彼は人目が避けられ、かつ風雨を避けられる場所を探した。錆付いたトラックや自動車、壊れて打ち捨てられた家具や家電の山があったが、いずれも日中は人目を避けられない。
雪の中、川原を北上し続けると、僅かに水が流れ出る下水管を見つけた。ただし、一般人が入れないように高さ二メートルほどの柵がしてあった。ジョンは柵に駆け上り、軽々と飛び越えた。
冷たい下水が流れ出る管の中を覗き込み、特段危険がないのを確認すると中へ入った。数百メートルほど進むと、下水管は枝分かれしているのに気が付いた。支流の下水はたいていは細い管になっているので、そこへは入れなかった。彼のピット器官は、前方で鼠が逃げ出すのを感知した。
もうしばらく進むと、下水の流れていない太目の支管を一本発見した。彼は、その管の中に入った。管の奥は乾いていて、彼一人が横たわれるぐらいのスペースがあった。この支管は、使われていないらしい。彼はその場所で改めて疲れた体を横たえ、そして眠った。