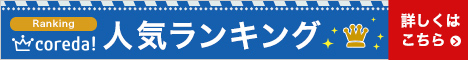入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二十三章 ハンティング
キングスレー少尉は、無線で兵士達に状況を説明し、完全武装を命じた。ホワイト博士は、ロックウェル上等兵とロイ一等兵に付き触れて西の砂浜へと向かった。彼らが砂浜に着くと、入れ替わりにキーファー一等兵とローランド二等兵が研究所に上がってきて、ビル伍長やダン一等兵と共に、建物内の三体の遺体…ブラウン博士、ピーター二等兵、クリスチャン二等兵…を、外へ運び出した。実線経験のない若い兵士達は、仲間の死体を見て少なからず動揺していた。
死体の処理が終わると、キングスレーとノートン、ダン、キーファー、ローランドの五名は、視界の比較的開けている広場に集合した。円形に広がり、全員が小銃をいつでも発射できる態勢を取っていた。体を円形陣の外に向けたまま、キングスレーが呟いた。
「厄介なことになったな。」
ノートンが、隊長に言った。
「我々も一時砂浜まで引き上げて、体勢を立て直した方が良いのでは?」
「そうだな・・・。爆薬のセットは?」
ノートンが答えた。
「後は、食堂と宿舎の一部にセットすれば、すべて完了です。15分もあれば、終わるでしょう。」
「では、それをさっさと済ませて、砂浜へ引き上げよう。爆薬をセットしている間、キーファーとローランドは、やつらがここに近づかないよう警戒していてくれ。」
彼らは速やかに爆薬を計画通りにセットすると、死体を担いで砂浜へと引き上げた。
時刻は、すでに正午を回っていた。一同は、砂浜のテント近くの木陰に集まっていた。キーファーとローランドが、小銃を島の中央に向かって構えて警戒していた。キングスレーが言った。
「本国に連絡を取る必要がある。ノートン、衛星回線は使えるか?」
ノートンは答えた。
「可能ですが・・・」
そう言って、彼は自分が肩に掛けている無線機を触った。
「しかし、ここの島に部隊を送ってもらうには、色々と問題があるのでは?」
キングスレーは、渋顔で答えた。
「分かっている。ここは民間施設と言う事になっているし、そもそも他国の排他的経済水域だ。米軍でも、堂々と部隊を派遣することはできない。取り敢えず、現況の報告をしておく必要がある。この会議の後、連絡しよう。」
「了解。」と、ノートン。
次に、キングスレーはホワイトに言った。
「さて、奴等の睡眠薬はいつまで効いている?」
ホワイトの顔には血の気が戻っていたが、ショックによる疲労の色は隠せなかった。
「餌を半分ぐらい残しているから、もう効き目はほとんど薄れていると思うわ。」
キングスレーの顔が、渋面になった。
「と言う事は、奴等は十分に戦えるわけだ・・・。」
彼は、しばらく考えてから所長のスチュアートに言った。
「所長、我々は研究者じゃないから、奴等の事を良く知っているわけじゃない。具体的に、奴等はどういう機能を持っている?」
スチュアートの顔にも、疲労の色が濃く漂っていた。長年の研究の友、ブラウンの死は耐え難いものだった。それは、他の者達も同じだった。
スチュアートが、口を開く。
「タッツェルベルムは、戦場での戦闘に特化すべく開発された生物兵器だ。視力は猛禽類並みで、しかも人間と同様に物体を立体視できる。猫と同様に夜目も聞くだけでなく、ピット器官があるので赤外線で外敵を探知できる。嗅覚は、犬並みかそれ以上。聴力も桁外れに高い。腕力や握力は、ゴリラと同様と思ってもらって間違いない。脚力も、野生の虎並み。皮膚はキャッチ結合細胞で覆われていて、いざとなると鎧のように硬くなる。頭の良さは、犬やイルカと同等かそれ以上。だいたい、これが概略だ。」
ロイが、舌打ちした。
「なんてこった。そんな凄いのか!」
「ロイ、黙ってろ。」
て、キングスレーが一喝した。
「そんな奴が三体も、この島の中をさまよっている訳か。」
キングスレーは、ノートンに向き直り言った。
「ノートン伍長、武器はどれだけある?」
ノートンは答えた。
「先週、武器庫内の兵器は、粗方本国へ送ってしまいましたので、あまり残っていません・・・。拳銃は、各自が持っているコルトのガバメントが九丁と、SIGのP226が二丁。小銃は、M16A―2が四丁と、同じくM203擲弾発射装置付きM16が三丁。MP―5短機関銃が二丁。MSG90狙撃銃が一丁。それと、66ミリ軽対戦車ロケット発射器が二門です。手榴弾は、全部で18個。暗視ゴーグルは二つだけ残してあります。無線機は、衛星回線が使えるのが一つと、小型無線機が二つです。あとは、P7型爆薬と信管も若干残っています。」
ウォーカーが、驚いて言った。
「たかが島の警備に、対戦車ロケットまであるのか!」
間髪入れずビルが、ウォーカーを睨んで言った。
「この周辺の海賊は重武装で、AK突撃銃だけでなくロシア製のRPGも持っているんだ!海賊に襲われた民間の船舶と船員が、どんな目に遭ったか聞きたいか?先週までは、ここの武器庫には50口径の重機関銃や携帯式の地対空スティンガーさえあったんだぞ。奴等を追っ払うには、そのぐらいの装備が必要なのだ。」
そう言われて、ウォーカーは黙ってしまった。
キングスレーは目を閉じて聞いていたが、ビルの報告を聞き終わると目を開いて言った。
「まあ、奴等を三体狩るには十分な火器だろう・・・。いくら優れた機能を持っていようとも、奴等にはハンティングや戦闘の経験は無い訳だからな。しかも、島の地形は我々は知り尽くしているが、奴らにとって外の世界は未体験だ。さっさと、彼らを狩り出そう。早ければ早いほど、我々に有利だ。」
兵士の中で、実戦経験があるのはキングスレーとノートンの二人だけであった。若い兵士が実戦で判断を過ったり、致命的なミスを犯すことがあるのを、キングスレーは戦場で身を持って知っていた。特に親友を突然失ってショックを受けているローランドは、ほとんど役にたたないだろう。相手が武器を持った人間ではなく単に動物だとは言え、とてつもなく危険な相手であることに変わりはない。彼は、ノートンの他に、他の者より軍隊経験の長いロックウェル上等兵と、ダン一等兵を選び出し、タッツェルベルムの狩りに行くことにした。
残りのキーファーとロイとローランドの三名は、砂浜のテント周辺を警備するために残ることとなった。
キングスレーは、研究スタッフ達に言った。
「あなた方にも、一応武器を渡しておこう。」
そう言って、コルトの45口径とSIG拳銃を彼らに差し出した。スチュアートが、手を伸ばした。
「私も一応全米ライフル協会の会員だから、銃の扱い方ぐらいは心得ている。」
そう言って、コルト拳銃を受け取った。ウォーカーも、同様に手を伸ばした。
「僕も、自宅用にスミス&ウェッソンを買った時に免許を取ったし、何度か射撃経験もある。」
そう言って、SIG拳銃を受け取った。キングスレーは、次にシュルツに銃を渡そうとした。シュルツは、首を横に振った。
「僕は、銃は使えない。自分の足を撃っちゃうよ。」
そこでキングスレーは、銃を隣のビンセントに渡そうとした。ビンセントは、
「僕も銃はいらない。彼の足を撃っちゃうよ。」
と言って、シュルツを指差した。キングスレーは最後にホワイトを見たが、とても銃を扱えるような精神状態ではなかった。キングスレーは、研究スタッフ一同に向かって言った。
「まあ、銃を使うようなことにはならないと思うが。むやみに撃つと、むしろ我々自身が危険に曝されるから、本当に危険な場合以外は使わないでくれ。」
そう言って、彼は研究員達の前を立ち去った。
キングスレーは、衛星回線で本国と連絡を取った。予想通り、排他的経済水域には各国の権利を侵害して勝手に部隊を送れないし、送るとしても偽装等の準備から派遣までには少なくとも一両日はかかるとのことだった。そして、本国の上層部は、残った隊員七名は、タッツェルベルム三体を狩り出すには十分な数だと判断した。今日一日、彼らだけで乗り切らなければならないのである。
キングスレーは、彼が選び出した三名の隊員が待つ砂浜への入り口へ戻った。
「さあ、今日ここで訓練の成果を見せてくれ。奴らを狩り出すぞ。見つけたら、撃ち殺して構わん。もともと殺す予定だったからな…。ダイヤモンド隊形を取って進む。先頭には私が立つ。ロックウェルは右に、ダンは左に。ノートンは、しんがりを努めてくれ。」
彼がそう言うと、三名の隊員が揃っていった。
「了解。」
「西と東の間を往復しながら、北から南へ捜索範囲を狭めていく。島内を、しらみつぶしにするぞ。夕方までには、全部終わらせよう。」
キングスレーと隊員達はM16の安全装置を外し、十メートルの距離をおきながら菱形隊形で、砂浜から林の中に入っていった。
島は、時折木々が風に吹かれてさざめく音を除けば、ほとんど静まり返っていた。普段は、もっと野鳥の声などで賑やかな南国の島である。今は、島全体が緊張で包まれているかのようだった。キングスレーは、道無き密林の下生えの中を一歩一歩注意しながら進んだ。これが初めての実戦経験となるロックウェルとダンは、極度に緊張していた。たかが動物を狩るだけなのに、強力な武器を持った特殊部隊兵に相対しているかのような心境だった。ただし、武器の威力と人数つまり戦闘力では圧倒的にこちらが上だったから、若干の精神的ゆとりは残されていた。
菱形隊形を取って進んだ一行は東側まで辿り着き、西側へと折り返した。再び東側へと折り返し、東端へ辿り着いた。右側の下方には、桟橋が見える。桟橋には、二艘のボートが繋留してあった。彼等の脱出用のボートである。
西と東の往復を繰り返し、三時前には、島の三分の一の探査を終えた。彼らは、砂浜で一度水を飲み、五分の休憩を取ってから再び出発した。
彼ら四人が、再び広場の外れに戻ってくると、キングスレーは隊員たちに止まるように合図した。背の高いタッツェルベルムが一体、広場を横切って研究所に入って行くのが見えた。キングスレーは、林の暗がりまで後退し、ノートンに向かって手で合図した。ノートンは、ほとんど音を立てずにキングスレーの元に来た。
「奴らのうち一匹が、研究所へ入った。他の奴が一緒かどうかは、分からない。起爆装置は、どこにある?」
ノートンは答えた。
「砂浜です。」
「爆破予定時刻は夕方だったが、予定を早めて中の奴ごと吹っ飛ばそう。私とダンでここを見張っているから、君とロックウェルで取りに行ってくれ。くれぐれも気を付けろよ・・・途中で奴らに出くわすかもしれないからな。」
そう言われると、ノートンは頷いてロックウェルの所まで後退し、彼を連れて林の奥に消えた。
次にキングスレーは、ダンに来るように合図した。ダンは、彼のすぐ後ろまでやって来た。キングスレーは言った。
「奴らの中の少なくとも一匹が、研究所の中にいる。入り口はあそこだけだから、もし奴が出てきたら擲弾をお見舞いしてやれ。奴は機敏だから、確実に一発で仕留めろよ。」
結局タッツェルベルムは、ノートン達が戻ってくるまで外に出てこなかった。
ノートンとロックウェルは、金属性の起爆装置をもって来た。ノートンは言った。
「導火線は、食堂の中にあります。引っ張り出してこなくちゃなりません。」
キングスレーは頷いた。
「そうか・・・。ではノートン。ロックゥエルを連れて、食堂に行ってくれ。我々がここで援護射撃をする。研究所にいる奴に、気が付かれないようにな。」
「了解しました。」
と、ノートンが答えた。
「M16をここに置いて、代わりにMP5を持っていけ。」
そう言うと、キングスレーは背中に掛けていた伸縮式銃床タイプのMP―5をロックウェルに渡した。ノートンも、M16を置いて背中に掛けていたMP―5に持ち替えた。銃身の長いM16では、建物内の戦闘で不利になるからだ。ノートンとロックウェルは、林の中を大きく右側へ迂回し、研究棟の反対側の宿舎棟側から食堂へと近づいて行った。通常の戦闘では、壁にぴったりと着いて移動することは、兆弾で負傷する可能性が大きく避けねばならないが、今回の相手は銃を持っていない。彼らは、宿舎の壁に沿ってゆっくりと食堂に近づき、静かに中に入った。
電源設備が既に撤去されていたので、食堂の中は暗くて、キングスレー達のいる広場の端の林からは中はよく見えなかった。
MP―5短機関銃を構えてノートンは食堂の中に入り、部屋の中をざっと見回した。異常が無いのを確認すると、続けてロックウェルに入ってくるよう合図した。ロックウェルも、短機関銃を構えたまま中に入った。ノートンが言った。
「よし・・・。研究所の奴には、気が付かれていないようだ。さっさと導火線をつなごう。見張りを頼む。」
ロックウェルは、窓際に歩いて行き、銃を外に向けて警戒に当たった。今のところ、研究所の入り口にタッツェルベルムの姿は無かった。ノートンは、起爆装置の安全装置がロックされているのを確認してから、導火線を起爆装置に繋いだ。ノートンは、MP―5を肩に掛け、導火線の巻かれたリングを左手に持ち、その導火線の繋がれた起爆装置を右手に持った。そして、ロックウェルに言った。
「よし、行くぞ。出ろ。」
ロックウェルが食堂を出て、続いてノートンが出ようとした時、食堂奥の厨房から音がした。ノートンが振り向いた。そこには、厨房からもの凄い勢いで飛び出してくる二体のタッツェルベルムの姿があった。
「くそっ!罠だ!」
と、ノートンは叫んだ。しかしノートンの両手は、導火線の束と起爆装置で塞がっていた。それらを手放して、肩に掛けた短機関銃に持ち換える間もなく、タッツェルベルムの一体が彼を思い切り突き飛ばし、壁に叩きつけた。ロックウェルは振り向いて、即座に状況を理解して応戦しようとしたが、彼とタッツェルベルムの間にノートンがいたので撃つ事ができなかった。もう一体が、ノートンを飛び越えて、ロックウェルを襲った。あまりの速さに彼は引き金を引くことすらできずに、一瞬で首の骨を折られた。
キングスレーも即座に応戦しようとしたが、やはり射撃の線上にノートンとロックウェルがいたので、引き金を引くことができなかった。二体のタッツェルベルムは、目的を達すると、食堂から走り去るために駆け出した。ただちにキングスレーとダンは、二体に向かって容赦なく弾丸を浴びせた。何発かは彼らに命中したようだったが、二体とも何事もなかったように走り続ける。しかし、食堂の中と外に、ロックウェルとノートンが残っているため、擲弾を発射することはできなかった。
タッツェルベルムの走る速度はチーターのように速く、あっという間に木々の中へ消え去った。
壁に叩きつけられたノートンは、再び導火線の束と起爆装置を手に持ち、膝を付きながら這うようにして食堂の外へ出てきた。横たわるロックウェルを見て、彼が死んでいるのを悟った。何故なら、彼の首が180度ねじれて後ろを向いていたからだ。そう言うノートンの口からも、大量の血が滴っていた。肋骨の半分以上折れているらしく、息ができない。内臓の多くも、破裂しているようだった。もう助からない。彼は、自分の死が間近なのを悟った。
次の瞬間、研究所の入り口からも、囮役だった背の高いタッツェルベルムも飛び出してきた。目的を達したので、逃げるつもりなのだろう。ノートンは決意した。殺された仲間達の仇は、今ここで取ってやる。彼は、起爆装置の安全装置を外した。
キングスレーは、茂みから出て叫んだ。
「ノートン、よせ!」
駆け出そうとするキングスレーを見て、ノートンは首を横に振った。彼は、起爆装置のスイッチを押した。
もの凄い爆発音と共に、研究棟、食堂とその付帯設備、宿舎棟が吹き飛び、周囲を炎で包んだ。P7型爆薬の威力は凄まじく、建物も、逃げようとしたタッツェルベルムも、ノートンも、ロックウェルもすべて一瞬で炎の中に消えた。キングスレーも、爆風で林の中に吹き戻された。しかし、炎は次の瞬間には消え、煙の量も比較的少なかった。煙が辺りから消えると、研究所のあった場所には、粉々になった建物の残骸だけが残っていた。