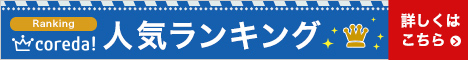入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二十二章 ジョンの逃亡
獣医のベン・ウィリアムは、1月10日を過ぎてもメグ・ブラウンから電話連絡がないので、やきもきしていた。ブラウン家の電話は留守番電話になっていて、メッセージを残しても何故か返信はなかった。
彼がやきもきしているのは、単にジョンを検査できないと言う理由だけではなかった。生物学・遺伝学の権威ジョージ・オーウェル博士から、一昨日電話があったのだ。ベンが送った(正確にはベンの友人が送った)血液サンプルに非常に興味があり、可能なら博士自身がベンの元を訪れ、その珍しい動物を見たいと言うのだった。ベンは、博士にその動物は自分の所にはいない事を告げた。すると、博士は来週なら都合が付けられるので、一緒にその動物を飼っている家を訪問しようと言うことになった。ベンは、十三日にブラウン家を訪れる約束をオーウェル博士と交わして、電話を切った。
家の中、たいていはメグの部屋の中で過ごすジョンにとって、外の世界は正にワンダーランドだった。ジョンは、窓から外を眺めるのが大好きだった。通り過ぎていく車、通りを歩く人、散歩させられている犬、郵便配達車から降りて手紙を家々のポストに入れる配達員、自転車に乗るメグぐらいの子供、時折降って路面を濡らす冷たい雨、風で吹き飛ばされる木々の葉、そう言う光景を眺めるのが好きだった。
ジョンは自分の能力が、メグと随分違っている事にも気が付いていた。ある日、窓から外を見ていると、上空を鳥が飛んでいるのが見えた。それをメグに告げると、彼女にはその鳥が見えないと言う。しかし、ジョンには見えたばかりでなく、鳥の種類まで特定できたほどだ。メグの図鑑を調べてみると、それは山鳩だった。また、冬にしては暖かいとある日の午後に窓を開いていた時、焼いた肉の匂いが外から漂ってきた。何軒か向こうの家で鳥か何かを料理しているに違いない。メグにそれを伝えると、彼女は何も匂わないと言う。他にも、似たようなことが山ほどあった。一階で冷蔵庫が閉まる音がジョンにははっきり聞こえたのに、メグにはまったく聞こえないと言う。そんな出来事が続いたので、ジョンは彼の持つ能力がメグの能力より遥かに高いことを悟った。メグの能力が彼の能力よりも劣るからといって、メグに対する愛情は変わらなかった。今日も、早くメグが帰ってくることを心から待ちわびていた。
ある日、メグが帰ってくるにはまだ小一時間ある時刻に、ブラウン家に来客があった。家政婦が、玄関先でその応対をしていた。家政婦では話しが通らないらしく、リビングからゆっくりとエリー婦人が玄関まで歩いてきた。
二階の奥の部屋にいるのだから、通常の人間だったら一階の玄関の会話など聞こえようはずがないのだが、ジョンの聴覚は異常に研ぎ澄まされていて、はっきりと聞き取ることができた。まず、エリーが言うのが聞こえた。
「どちら様でしょうか。」
「初めまして。獣医のベン・ウィリアムスと申します。昨年、12月にお宅のワンちゃんを診察させていただきました。そして、こちらが有名な生物学者のジョージ・オーウェル博士です。」
と、ベンが丁寧に挨拶した。
「そうですか・・・。獣医の先生と有名な学者先生が、わざわざこんな遠くまで・・・。うちのジョンに、何か問題でもあるのでしょうか?病気とか?」
エリーがそう言うと、ベンが笑って打ち消した。
「いえいえ、病気の心配はありません。むしろ元気なくらいです。」
ベンの後を継いで、オーウェル博士が言った。
「実は、お宅のジョン君は犬ではありません。と言うより、何の種に属するのかすら、まだ特定できないのです。もしかしたら、未発見の未知の生物の可能性すらあります。」
それを聞いて、エリーは驚きを隠さなかった。
「未発見の生物?ジョンが!」
ベンは、それを改めて肯定した。
「はい、そうです。」
二階のジョンは、その会話の一言一言をしっかり聞き取り、その意味を咀嚼していた。彼は動揺した。ジョンの特異性が、外の人々に知られてしまった。メグは、かつてこう言った。
「ジョンが見つかっちゃうと、メグとジョンはさよならしなくちゃならないの。」
"メグと、さよならしなくちゃいけない!"この考えは、ジョンを最高に動揺させた。
一階の玄関では、会話が続けられていた。オーウェル博士は、エリーに言った。
「奥方様のお許しが頂ければ、ぜひともジョン君を預かって、大学の研究施設でより詳しく検査させていただきたいと思うのですが・・・。」
ジョンは、パニックに陥った。"ジョン君を預かって"・・・この言葉が、ジョンの頭の中を何度も駆け巡った。メグは、確かにこう言った。
「ジョンがとてもお利口さんだから、ジョンをもっと知りたいって言う人が来て、ジョンを連れて行っちゃうの。そしたら、ジョンとメグは一緒に暮らせなくなるの。」
ジョンは必死に考えた。メグは、こうも言った。
「それに、誰かがジョンを捕まえようとしたら、逃げなくちゃ駄目よ。分かった?」
絶対に捕まりたくない!メグと離れるのは嫌だ!逃げなくては!逃げろ!逃げろ!逃げろ!その言葉が、頭の中を駆け巡った。ジョンは部屋の窓を開けると、速やかにそこから飛び出して、裏通りに消え去った。彼が初めて体験する外界だった。
玄関の一同は、ジョンが二階から逃げ出した事にはまったく気が付かなかった。それほどまでに、ジョンの行動は静かで迅速だった。エリーは、彼らに言った。
「ジョンは、娘が買っているペットですので、私の一存では決められませんわ。娘がそろそろ幼稚園から帰りますから、それまで家の中でお待ちいただけますか?」
メグの乗った幼稚園の黄色いスクールバスが、家から一ブロック先の交差点の手前で止まった。そこでメグは降りて、家へと歩いた。自分の家を見上げると、自分の部屋の窓が開いていて、カーテンがたなびいていた。
家の中に入ると、リビングには獣医のベン先生と見たことのない白い髭を生やした小太りの男性が、ソファーに座っていた。メグは挨拶も済ませず、階段を駆け上がって二階の自分の部屋へ向かった。
勢いよくドアを開け、ジョンを呼んだ。
「ジョン!ジョン!」
いつもなら、喜び勇んで飛びついてくるジョンはそこにはいなかった。タンスの中、ベッドの下も覗き込んだが、ジョンはいない。頭の回転の速いメグは、"下にいる獣医"、"開いている窓"、"部屋にいないジョン"を関連付けて考え、全てを理解した。ジョンは、逃げ出したのだ。