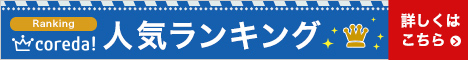入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二十章 ジョンの自我
新しい年、2028年1月が到来してからも、メグはジョンにかかりきりだった。
幼稚園が冬休みと言うこともあって、母親の手伝いをする以外は時間が取れた。年末と年始に、祖父母や親戚が訪れたが、メグはジョンを一同にほんのちょっと紹介しただけで、彼を部屋へすぐに連れ戻した。と言うのも、ジョンが二本足で立ったりしないか、言葉をしゃべったりしないか、と常にヒヤヒヤしていたのである。一同の注目を浴びれば浴びるほど、ジョンの特異性が際立ってしまう。
ジョンは、どんどんと言葉を覚えていった。しかも、オウムのようにフレーズを覚えて繰り返しているだけではなく、意味を"理解"しているようであった。メグに始終付きまとい、
「コレ、ナニ」
「ドウシテ?」
と、頻繁に質問を発した。
なんでこんなにも成長が早いのか、メグには理解できないでいたが、二足歩行も今やしっかりしてきた。二足歩行がしっかりすると、前足も手のように物をつかんだりできるようになってきた。体もどんどん大きくなり、立ち上がると一メートルを超えるまでになった。発音も次第にしっかりしてきて、人間の子供の発音とほぼ同程度までに発達している。
「もっと、ご本を読んで。」とか、「ミルク、もっと欲しい」などと、はっきり欲求を伝えるようになった。
しかし、人間の子供のようにむずがったり、子犬のようにキャンキャンと鳴いたりはしなかった。ジョンはメグにたいへん従順で、メグの言うことにはきちんと従った。
1月7日、ベンの医院の年始の開業日が到来したが、メグはジョンを連れて行かないことにした。今、ジョンの事を他人に知られてはいけない気がしていた。正直なところ、いつまでジョンを世間から隠しておけるのか自信がなかった。最初に母親がジョンをおかしいと思うのか、家政婦がジョンが犬でないことに気づくのか、それとも父が帰ってきてすべてが灰塵に帰すのか。
冬休みも終わりに近づいたある日、ジョンはいつものように前足をメグの膝に乗せて、はっきりとこうメグに質問した。
「どうして、僕はお外に出られないの?」
メグは、予想外の質問にギクッとした。メグは、ジョンの頭を撫でながら言った。
「それはね、ジョンが特別だからなのよ。」
「特別?」
「そう、特別。」
間をおいて、ジョンがゆっくり言った。
「特別って何?」
「ジョンは、凄く可愛くて、とてもお利口さんなの。だからね、ジョンが見つかっちゃうと、メグとジョンは"さよなら"をしなくちゃならないの。」
「なんでさよならするの?」
その目は、じっとメグの目を見つめていた。
「ジョンがとてもお利口さんだから、ジョンをもっと知りたいって言う人が来て、ジョンを連れて行っちゃうの。そしたら、ジョンとメグは一緒に暮らせなくなるの。」
「メグとさよならするの、嫌だ。」
「私もよ、ジョン。だから今はね、まだお部屋の中にいなくちゃならないの。分かった?」
「分かった・・・。」
「それに、誰かがジョンを捕まえようとしたら、逃げなくちゃ駄目よ。分かった?」
「分かった・・・。」
ジョンは、顔をメグの膝に埋めて、その内に寝入ってしまった。
メグの幼稚園が始まると、ジョンは日中、メグの部屋の中で過ごした。家政婦の掃除機の音が近づくと、ベッドの下に隠れた。家政婦の気配が周囲からなくなるとベッドから這い出て、本棚のメグの本を引っ張り出して、片っ端から読んだ。最初は絵本が主流だったが絵本は残らず読み尽くしてしまい、そのうち絵のない"文字だけ"の本にも手をのばすようになった。
メグが幼稚園に行っている間は時間がたくさんあったので、考え事もするようになった。一番の問題は、自分が何者かと言うことだった。姿形は、メグには似ていない。メグの持っている図鑑もよく眺めたが、図鑑に乗っている犬や猿に似ているようでもあるが、犬や猿などの動物は人間のように話したりしない。
ジョンは、いったいどこから来て、これからいったいどこへ行くのだろう・・・。ジョンは、幼いが天才的な頭で、短期間に詰め込んだわずかな知識を基にしてあれこれと考え、午前中の半分を思索で過ごした。そして、メグが帰ってきて家のドアが開く音がすると、ワクワクして部屋のドアの前で待つのだった。部屋のドアが開く瞬間、それがジョンの至福の時だった。