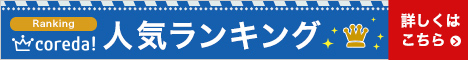入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第十八章 ジョンの謎
獣医のベン・ウィリアムは、仕事の傍ら、小さな女の子メグが連れてきた"ジョン"と名づけられた不思議な生物について調べ続けていた。医院の休日には国立図書館に行き、絶滅寸前の生物や希少生物を中心に様々な文献に当たっていた。しかし、該当するような生物の記述はどこにもなかった。
ジョンは突然変異種か、さもなくば未知の未発見生物の可能性があった。そう考えて、ベンの心は躍った。田舎町の一介の獣医が、世紀の大発見をするかもしれないのだ。
ベンは、ジョンの骨格から判断して、犬ではなく、猿か猿に近い種ではないかと見当を付けていた。大学の友人に送っておいた血液サンプルからは、何も分からなかった。電話での会話で、その友人はベンに言った。
「血液に、病原菌やウィルスは発見されなかったから、病気の心配はないと思うよ。ただしね、ちょっと不可解な点がある。あれは、一体何の動物の血液なんだい?今までの臨床動物実験でも、見たことないぞ・・・。」
ベンは答えた。
「実はね、君だけに言うが、僕にも分からないんだ。一度も見たことのない動物で、どの文献にもその記述はないんだよ。突然変異種や、未発見生物の可能性がある。もしそうなら、世紀の大発見かもしれない。」
「そいつは凄いな、ベン!レントゲン写真は、撮ったか?」
「いや、まだなんだ。ケガで来院した訳じゃなかったし、レントゲン写真を撮る口実がなかったんだ。」
「ぜひ撮らなきゃ駄目だ!僕も、君が送ってきた血液サンプルを、恩師の生物学と遺伝学の権威、ジョージ・オーウェル博士に送ってみよう!」
クリスマス・イブの日に、ベンはメグ・ブラウンの家に電話した。
「もしもし、ブラウンです。」
電話に出たのは、メグだった。母親のエリーの目が悪いので、電話に出るのはメグの役割なのである。
「ああ、こんちには。獣医のベン・ウィリアムです。メグちゃんかな?」
「はい、そうです、ベン先生。」
「そうか、たいへんだね。ところで、ジョン君のことだけど、元気にしているかな?」
「はい、とっても元気です。この間もらった検査の通知では、問題なしって書いてありましたけど・・・。何か、問題があるんですか?」
「いや、病気とかではないよ。ただ、ちょっと気になる点があってね。もう一度、ジョン君を診察してみたいと思ってるんだ。そのうち、また連れてきてもらえるかな?」
メグは、少し考えてから言った。
「今年はもうすぐ終わっちゃうから、来年になってからでもいいですか?」
ベンは答えた。
「ああ、全然構わないよ。1月は7日からやっているから。それじゃ、また。さよなら。」
「さよなら、先生。」
電話を切った後、メグは考え込んだ。ジョンを医者に連れて行ったことは…母の薦めとは言え…まずかったかもしれない。父が蟹の中に入れて送ってきた動物は、特別なのかもしれない。
実は、そう思わせる徴候がジョンに現れ始めていた。6日にジョンが家に来てから、既に二週間以上経っていた。ジョンの体は、驚くべき成長速度で大きくなっていた。そして四本足でよちよち歩きを始めたかと思うと、しばらくして不完全ながらも時々二足歩行をし始めたのだ。そればかりではない。三日前に、メグがジョンに、
「ハロー。」
と声をかけると、ジョンがこう言ったのだ。
「ア~ロー。」
メグは驚いて、聞き違いかと思い、もう一度言った。
「ハロー。」
ジョンは答えた。
「アロー。」
間違いなく、ジョンははっきりそう言った。メグは、驚き戸惑った。彼女は、父の研究材料に取り返しのつかない事をしてしまったのかもしれない。しかし、今さらジョンを冷凍室に戻すわけにもいかない。
ジョンは、メグを母親でもあるかのように慕って、家にいる時にはいつもメグの後ろを付いて歩いていた。母親のエリーもジョンを可愛がったので、エリーにもなついた。ただし、家政婦に対しては、彼女が大きな音のする掃除機で家の中を掃除するのでとても怖がり、家政婦には近づかないようになった。
クリスマスが過ぎ、年末が日一日と近づいてくる頃、ジョンはメグの絵本に興味を持ったようだった。ジョンは、いろんな動物の絵が書かれた表紙の、"ペットたちの冒険"と言うタイトルの絵本を特に好んで、毎日口にくわえてメグの所に持って来た。メグは、それを毎日ジョンに読んで聞かせた。もちろん、ジョンがそれを理解できるなどとは思っていなかった。
「・・・こうして、犬と猫と九官鳥は無事家の主人の所に帰りました。」
メグは、読み終えて絵本を閉じた。ジョンは、前足をメグの膝に掛けて、じっと彼女の声に聞き入っていた。その顔付きは、メグには犬よりは猿に近いように感じられた。
メグが絵本を読み終わると、ジョンがメグの顔を見た。そして、
「イヌト、ネコト、キュゥカンチョウハ、ブジ、イエノ、シュジンノトコロニ、カエリマシタ。」
とジョンが言った。メグは、驚き呆れて、開いた口が塞がらなかった。ジョンは、間違いなく人間の言葉をしゃべるのだ。オウムや九官鳥のように、物真似で単にフレーズを繰り返しているだけかもしれないが・・・。
メグの心は、ワクワクした。ジョンは、天才動物かもしれない!子供心に、この秘密は誰にも知られていけないと思った。さあ、これからどうしたら良いのだろう。メグは小さな頭を目一杯駆使して、色々と考えを巡らした。