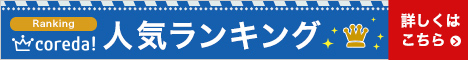入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第十六章 ジョン
メグが部屋に連れ帰った子犬は、急激に元気を取り戻していた。ミルクをどんどん飲み、快活になっていった。問題は、鳴き声だった。最初は小さくか細かった声も、三日も経つ頃には次第に大きな鳴き声になりつつあった。母の部屋とメグの部屋は二部屋分離れていたが、もう一週間もすればごまかしきれなくなるだろう。その前に、家政婦に気づかれるかもしれない。今は幼稚園に行っている間は、タンスの中にミルク・ボールと共に隠しているが、よちよち歩きを始めればそれも難しくなるだろう。
メグは、決断しなければならなかった。天才的な優秀な祖父母、そして両親を持つ彼女は、六歳でありながら、類稀なる思考力、判断力、実行力を持っていた。彼女は大きく頷くと、子犬を抱えて自分の部屋のドアを開き、階段を下りて母のいるリビングへと向かった。
メグは、ソファーに座っている母親のエリーの前に行き、こう切り出した。
「あのね、ママ・・・。大事なお話しがあるの・・・。」
「なあに、メグ?」
「実は、今日幼稚園の帰り道で、子犬を拾ったの。捨てられたみたいで、首輪も無くて、とても可哀相なの・・・。お腹を空かせていて、死んじゃいそうだったから、おうちに持って帰ってきたの。お世話は私がするから、飼わせてほしいの・・・。ママ、お願い。」
エリーはそう言われて、しばらく考えた。お父さんはずっと留守にしているし、娘も寂しいのかもしれない。娘は、日頃あまりわがままも言わないし、小さいながらも一生懸命家事の手伝いをしている。エリーは、そんな娘の小さな願いを一つくらいかなえて上げても良い気がした。
エリーは、よく見えない目を娘の声の方に向けて微笑んで言った。
「いいわ。でも、一つ約束してね。一生懸命、大事に育てること。それからもう一つ。病気を持っているといけないから、明日の午後にでも獣医さんに連れて行って一度みてもらって。一緒に行ってくれるように、家政婦さんには私から頼んでおくわ。」
「ありがとう、ママ!」
メグは大喜びした。エリーは言った。
「そのワンちゃん、私にも抱っこさせてくれない?」
そう言われて、メグは抱えていた子犬をエリーにそっと手渡した。そして、フサフサの毛をなでながら言った。エリーは、目が不自由な分、手触りで子犬の感触を感じとった。
「かわいいわね。このワンちゃんの顔が見られないのが、残念だけれど。」
「お顔も、すごく可愛いのよ!」
「飼うのだったら、名前も付けなくてはいけないわね。」
メグはすぐに反応した。
「ジョンが良いわ!ジョン!」
「ジョンね…いい名前だわ。じゃあ、この子の名前は、ジョンに決定ね!」
こうして、メグの大胆な計画はうまく成功した。
翌日、メグは幼稚園から帰ってから、家政婦に付き添われて地元の獣医を訪れた。そこは小さな医院で、たった一人の獣医ベン・ウィリアムが切り盛りしていた。スタッフの女性が、メグに診察室に入るよう声を掛けた。メグは子犬を連れて中に入った。
獣医のベンは、メグと子犬を見て言った。
「そのワンちゃん、どんな症状かな?」
メグは、きっぱり言った。
「ジョンって言うのよ!とっても元気よ。ただ、変なお病気を持っているといけないから、ママが念のためにお医者さんに調べてもらいなさいって。」
「そうかい。それじゃ、ジョン君をちょっと見せてくれるかな?」
メグは、ベンに子犬を渡した。ベンは、一目でジョンが犬にしてはかなり風変わりにことに気づいた。と言うより、それは犬の骨格ではなかった。しかし、ベンはそれがどんな種類の動物かは判別できなかった。彼が始めて目にする動物だった。しかも、その動物が雌雄の区別すらできないのにも気が付いた。
「とっても珍しいワンちゃんだね、ジョン君は!どうやって手に入れたの?」
ベンは、小さな女の子に動揺を与えないように、穏やかに尋ねた。しかし、その質問と獣医の語感に、メグは不安なものを感じた。そこで、即座に虚偽の受け答えをした。
「パパは今外国にいるんだけど、そこでパパが飼っていた地元の犬の子供だって。ちょっと早いクリスマスプレゼントに、パパが贈ってくれたの。」
ベンは、その答えに一応頷いて見せた。
「それじゃあね、悪い病気の菌がいるかどうか調べるから、ジョン君の血を採ろうね。それから、写真も何枚か撮るからね。」
ベンは、ジョンの血液を採取し、その後カメラで撮影した。それから、彼はメグに言った。
「結果は数日で出るから、結果は郵送で送ろう。悪い菌がいたら、お注射しなくちゃいけないから、また連れて来ることになるよ。でも、問題がなくても、メグちゃんとジョン君にはまた会いたいな。」
メグは、にっこりと笑って言った。
「分かったわ。必ずまた連れてくるわ。」
こう言って、メグはジョンを連れて医院を出た。
医院が営業を終えてから、獣医はジョンの血液のサンプルの一部を、大学の研究室の友人に送る手配をした。その後、ベンは手元にあるありとあらゆる動物図鑑や学術書を取り出してきて、机の上に開いた。ワシントン条約で規制されている動物種や、レッドデータ・ブックの動物種はもちろん、学術書に記載されている珍しい動物種まで調べた。しかし、そこにはジョンのような骨格の動物の記載はなかった。もしかすると、未知の種の発見かもしれない。彼は週末の医院の休日に、国会図書館に行く決意をした。