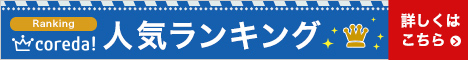入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第十四章 冷凍蟹
ユナイテッド・エアサービスの宅配ワゴン車が、ペンシルバニア州のヨーク市にある一軒の家の前で停車したのは、12月6日の午後一時を回った頃だった。緯度四十度に位置するこの街では、既に厳しい冬が到来していた。宅配車両から厚めのジャンパーを着込んだ宅配員二人が降りてきて、通りに面した庭を横切り、ドア横のチャイムのボタンを押した。
家の中からは、一人の婦人が足元を確認するかのように、ゆっくりとドアの方に歩いてきた。その後ろから、すぐに小さな女の子が付いて来た。婦人は、透明ガラスのあるドア越しに表を見た。
「どちら様ですか?」。
明らかに宅配便のユニフォーム・ジャンパーを着ている二人に向かって、婦人はそう尋ねた。宅配員の一人が答えた。
「ユナイテッド・エアサービスのデリバリーです。」
婦人が、それを聞いて小さな子供の方を向いた。子供が、大きく頭を振って頷いた。
「間違いないわ、ママ。宅配便のお洋服を着ているもの。」
それを聞いて、婦人は再びドアの方に向き直った。
「すみませんね。目がたいへん悪いものですから。で、何でしょう?」
宅配員が答えた。
「フィリピンから、冷凍の"蟹"が届いています。発送人は、アルバート・ブラウン氏です。特別料金をいただいていて、必ずエリー・ブラウンさんに手渡しし、すぐに研究室の冷蔵庫の冷凍室に保管するよう伝えるようにとの指示を受けています。」
婦人はドアをそっと開けて、体を半分外に出して言った。
「私がエリーよ。」
宅配員は、伝票とペンを差し出した。
「では、こちらにサインをお願いします。」
婦人は差し出された伝票に気が付かなかったので、宅配員は彼女の手に伝票とペンを渡した。彼女がどこにサインをして良いのか戸惑っている様子だったので、宅配員は伝票の署名欄を指で教えた。婦人は、伝票から五センチの距離まで目を近づけて、ゆっくりと署名欄にサインした。書き終えると、彼女は伝票を宅配員に返した。宅配員はサインを確認し、梱包された包みを婦人にしっかりと手渡した。
「くれぐれも研究室の冷蔵庫の冷凍室に入れるのを、忘れないで下さいね。発送人の強い指示ですから。では、失礼します。」
こう言って、二人の宅配員はワゴンの方へ去って行った。婦人は荷物を抱えて家の中に入り、ドアを閉めた。
婦人の名前は、エリー。アルバート・ブラウンの妻である。原因不明の病気で、視力がどんどん低下していて、今はほとんど目が見えなくなりつつあった。その後ろに付いて歩く女の子は、メグ。アルバートとエリーの一人娘で、現在六歳。来年からは、小学生になる予定だった。幼稚園から帰ると、目の不自由な母親の家事を手伝った。もっとも午前中に家政婦がやってきて、重要な家事はすべて済ませてあったのだが。
エリーは、娘に言った。
「その包みを開けてくれるかしら?」
「はい。」
そう言って、メグは包みの梱包をはがし始めた。茶色の包み紙を剥がすと、中から白い発泡スチロールの箱が出てきた。スチロールの箱には、手紙が貼り付けてあった。
「手紙が貼り付けてあるわ。」
「そう・・・。メグちゃんは、お手紙読めるかしら?」
「メグ、読んでみるわ。」
メグは、箱から手紙の封筒を剥がして、中の手紙を取り出した。
「え~と・・・。『エリーへ。目の具合はどうかな?こちらの研究はかなり進展していて、目の治療に役立ちそうな研究成果も、かなり出てきている。希望を失わないように。さて、今回"蟹"を送ったが、これは研究用なので、必ず研究室の冷蔵庫の、冷凍庫の方に入れておいてくれ。間違って食べないでくれよ』。・・・ここで、"かっこ笑い"って書いてあるわ・・・。それから、『娘のメグにもよろしく伝えてくれ。一月には、帰宅できると思う』。これで、全部よ・・・。"蟹"って、な~に?」
メグは、まだ蟹を見たことがなかった。エリーは、答えた。
「海の中に住んでいて、足がいっぱい生えているのよ。八本だったかしら?それとも十本だったかしら?川に住んでいるのもいるわ。後で一緒に図鑑で調べてみましょうね。さあ、この箱をパパの部屋の冷蔵庫に入れてしまいましょう。」
メグは大きな箱を抱えて立ち上がり、エリーと一緒に一階奥の父の研究室に向かった。アルバート・ブラウン博士の研究用の部屋は、他の部屋の作りとは大きく違っていて、壁や床や天井が耐震構造で分厚くできているだけでなく、床下は免震構造になっていった。窓は一切なく、代わりに換気装置が備えられていた。充電式自動電源装置も設けられていて、停電時には一定期間電気を供給することができた。普段はドアには鍵が掛けられていて、家族も滅多に中には入らない。
研究室の隅には、大きなステンレス製の冷蔵庫が備え付けてあり、ブーンと言う低い音を立てていた。エリーはドアの鍵を開け、娘のメグと一緒に部屋に入り、冷蔵庫の冷凍室に発泡スチロール・ボックスを入れて、しっかりと扉を閉めた。
その日の夜、メグは母が寝た後に、そっと父の研究部屋にやって来た。ドアの鍵の保管場所は、母が隠す所を始終見ているので知っていた。メグは、音を立てないように静かに父の部屋のドアを開き、中に入った。彼女は、父が送ってくれた蟹を見たくて仕方なかったのである。父に会ったのは去年のクリスマスが最後で、父恋しさからか、または単に蟹に興味があるだけなのか、とにかく蟹が見たかった。
冷蔵庫の前にじっと立ち、考え続けた。六歳の児童の頭で、精一杯考えを巡らしていた。
「本当に危険なものなら、パパが宅急便なんかで送る分けがないわ。危なすぎるもの・・・。だとすれば、ここに入っている蟹が、危ない分けがないわ。単なる研究用の蟹よ。見るくらいなら、大丈夫よ。きっと・・・」。
そう判断して、彼女はそっと冷凍室の扉を開き、発泡スチロールの箱を取り出した。箱を取り出すと床に置いて、蓋についたテープを剥がして、ゆっくりと蓋を取った。中には、日中に母親と一緒に図鑑で見たのと同じ本物の "蟹"が入っていた。周りには保冷剤が敷き詰められ、蟹は冷たく凍っているように見えた。メグは安堵したと同時に、ちょっと残念でもあった。中身が、本当に単なる "蟹"だったからである。メグは、そのグロテスクな蟹の姿をしばらく見つめていた。母は、世の中には蟹を食べる人々がいると言っていたが、信じられなかった。こんな不気味な生き物を食べるなんて、どんな人たちなのだろう・・・と訝しがった。
メグが箱の前でそんなことを考えていると、突然蟹の甲羅が動いた。彼女は驚いて叫び声をあげそうになったが、なんとか声を出さないように自分を抑えた。こんなことで、怒られたくない。箱の中の蟹は、胴体も足も動かず、ただ甲羅だけが蠢いていた。メグは、恐ろしさ半分、興味半分で、蟹に手を伸ばそうかどうか悩んでいたが、勇気を振り絞って甲羅に手を伸ばした。甲羅に触ってみると、それは左右にずれた。ただ胴体に乗っかっているだけのようだったので、そっとその甲羅を持ち上げてみた。彼女が二度驚いたことに、甲羅の下にあったものは、なんと小さな子犬のような生き物だった。寒さに震えているように見えたが、明らかにまだ生きていた。温かい空気に触れて仮死状態から蘇生したタッツェルベルムの幼体であることなど知る由もないし、六歳の女の子には予想すらできる分けがなかった。
メグは、その死に瀕しているように見える子犬を助けなければ、と言う思いに捕らわれた。両親に怒られることは、後で心配しよう・・・今は、この子犬を助けよう。彼女はパジャマの上着を脱いで、箱から出した子犬をその上にそっと乗せた。それから甲羅を蟹の胴体に戻して、箱の蓋を閉め、剥がしたテープを蓋と箱に巻き直して冷凍室にしまい直した。冷蔵庫の扉を閉め、パジャマに包んだ子犬を抱えて父の研究室を出て鍵を掛けた。
メグは食堂に行って、冷蔵庫からミルクパックを取り出してボールに注いだ。ミルクの入ったボールを左手に、パジャマに包んだ子犬を右手に抱えて、静かに階段を上がり、二階の自分の部屋へ戻った。