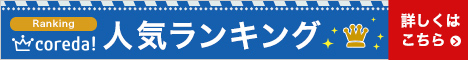入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第十三章 タッツェルベルム達の成長
十月にはよちよち歩きだったタッツェルベルム達も、十二月に入る頃にはしっかりと歩き、体もかなり大きくなっていた。中でも、"ノッポ"と呼ばれていた個体は体長180センチ近くまで大きくなっていた。一番小さい"チビ"と呼ばれている個体ですら、150センチに達していた。
研究体育成チームのチーフであるカレン・ホワイト博士は、予想されていたとは言え、彼等の成長スピードには驚いていた。九月には小さな子犬のような幼体だった彼らが、たった三ヶ月間にここまで大きくなるとは・・・カレンにとっては、信じがたい日々の連続である。
しかもこれだけ大きくても彼らはまだ成体ではなく、成体になる頃には二メートルないしそれ以上の体長になると予想されていた。彼等の新陳代謝は激しく、細胞分裂の速度も従来の哺乳動物と比較すると遥かに速かった。遊んでいる最中に仲間に噛まれて怪我をしても、一晩と立たないうちに傷口はほとんど塞がってしまうのである。新陳代謝が激しい分、食欲も旺盛だった。
しかしその代償は高くつき、彼らの寿命は人間の半分以下と予想されていた。寿命は35年から40年、長く生きたとしても50年は上回らないだろうと考えられている。何故なら、彼等の体内の細胞の総入れ替えは三年から四年毎に起こり、細胞分裂の度に二本のDNA螺旋の鎖を繋ぎ止めるキャップは短くなり、分裂が十回を超える頃には二本のDNA鎖を繋ぎ止めて置けなくなり、そこで細胞の寿命は尽きる。寿命因子の関係する遺伝子機能の遺伝子発現のアルゴリズムは、解明されていなかった。鉄かぶと島の優れた研究者の頭脳でも、寿命因子と有限の分裂寿命の問題を解決することはできなかったのである。三十億もの遺伝子配列の解明は、まだまだ長い年月を必要とするテーマなのだ。
タッツェルベルム達の驚くべき点は、成長だけではなかった。成長と同様、学習能力も異様に高かった。ホワイトは、頭の良い子犬が学習する過程を、二倍速ないし三倍速で早送りして見ているように感じていた。彼らは見た目は恐ろしげだが、決して暴力的な性格ではなく、社会性を持っていた。一番荒々しい"暴れん坊"と呼ばれる個体ですら、一度群れのリーダーとしての地位を確立してしまうと、群れの仲間を襲うことはせず、むしろ守ろうとさえする行動を取った。脳自体が犬の脳の遺伝子をベースとしているせいかもしれないが、狼の集団に近い社会性を帯びていた。しかも群れのリーダーたる暴れん坊も、ホワイトに対しては高い忠誠心を抱いていた。彼らに餌を与える彼女とスタッフに対しては、忠誠心溢れる態度を取っていて、頭の良い犬のようである。ただし、ホワイトのチーム以外の人間が飼育部屋のガラスの前に来ると、敵意を剥き出しにして唸り声を上げた。男性スタッフがホワイトの肩に手を掛けようものなら、ガラスを思い切り叩いたりして暴れた。
暴れん坊は、背丈こそノッポより低くて170センチほどであったが、その体つきはがっしりとしていた。キャッチ細胞で覆われた外皮はまるでヒトデのように不気味だが、足は野生の虎の足のように引き締まり、胸から腕にかけてはゴリラのように力強い筋肉が付いている。彼を一言で言い表せば、"美しい新時代の生物"と言うことにでもなろうか。それほどまでに、美しいボディラインを持っていた。それは、あたかもドーベルマンが、近寄りがたい恐ろしさをもっている一方で、美しいボディラインを持っているのに似ている。
暴れん坊だけでなく、彼の仲間すべてが、多かれ少なかれ彼と同じような美しさを持っていた。ホワイトは彼らと毎日接し続けていくうちに、彼らに対して愛しい感情が湧いてくるのが分かった。恐ろしげな見た目と裏腹に、彼等の中に優しい一面、何か美しい一面があるのを感じ取っていた。彼らが戦場での殺戮のみを目的に生み出された生物兵器であることを思い起こすたびに、彼女は複雑な思いに満たされた。理性を重んずる研究者とは言え、人間としての感情を否定することはできない。
ホワイトは、数ヶ月前の晩にシュルツ博士と交わした会話を思い出していた。誰もフランケンシュタイン博士になどなりたくないし、ましてモンスターを生み出したいなどとは望んでいないのだ。今は無邪気に遊んでいるタッツェルベルム達ではあるが、彼等の前途に横たわる暗い陰を思うと、ホワイトは悲しい思いに捕らわれるのであった。