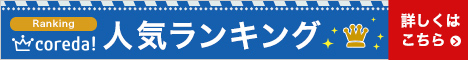入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第十二章 スチュアートとブラウンの決断
十月、十一月と、時間が過ぎ去っていった。
アルバート・ブラウン博士は、自分の部屋のカレンダーをめくった。十一月のカレンダーを切り取ってそれを丸めてごみ箱に放り込み、新たに現れた十二月のカレンダーをじっと眺めた。
次に、彼は壁の時計を見た。太陽が、そろそろ真上に昇ろうかと言う時刻。それから、彼はゆっくりと部屋を出た。ブラウンは、デビッド・スチュアート所長の部屋の前まで来ると、ドアをノックした。
「ブラウンです。」
「開いているよ。入りたまえ。」
ブラウンは、ドアを開いて部屋へ入った。所長のスチュアートが言った。
「急に呼びたててすまない。まあ、座ってくれ。」
ブラウンは、いつもの椅子に座った。
「アルマニャックで、良かったかな?」
「はい。」
ブラウンがそう答えると、スチュアートが机上のグラスに、2フィンガー分のアルマニャックを注いだ。
「で、君に九月に話した件だが、クリスマス前には陸軍の上層部の結論が出ることになった。結論はほぼ内定しているらしいが、正式な通達はまだ三週間も先だ。実は、軍上層部の友人に禁を破って、情報を漏らしてもらった。」
スチュアートは、そこで言葉を止めブラウンの目をじっと見た。所長の表情が暗いことから、ブラウンは軍が出した結論のだいたいの予想が付いた。スチュアートは続けて言った。
「以前、君に話したように、軍の案は三つあった。一つは、カムフラージュして研究を続ける。二つ目は、一時的に研究を休止して、ほとぼりが冷めたら研究を再開する。三つ目は、ここでの研究所を完全に閉鎖して設備も人員も本国へ戻す・・・だった。今回、決定されたのは、最悪の三つ目の策で、ここの閉鎖だ。軍の上層部は、現在はほとんどが自己保身派が占めていて、臭い物に蓋をすることに決定したらしい。」
ブラウンは、それを聞いてゆっくりと応える。
「残念です、所長。」
スチュアートも、同意するように頷く。
「同感だ、ブラウン博士。クリスマス前にはこの通達が正式に出されて、一月前半には、諸設備が運び出され、一月中旬には研究施設等のすべての建築物はきれいに取り壊される。」
そう言う彼の目線は、今やブラウンから逸らされてしばらく宙を舞っていた。それから、再びブラウンを見やった。
「九月に、君に頼んでおいたことの進捗状況はどうだね?」
「研究データの取りまとめは、ほぼ終わっています。それから、所長が命じられた"タッツェルベルムの最高の個体の生体サンプル"も順調に培養され、ほぼ完全な幼体に成長しています。」
とブラウンは言ったが、新タッツェルベルムの遺伝子に、人間の脳の遺伝子、他ならぬブラウン自身の脳遺伝子を使用したことは黙っていた。
「それは良かった・・・。軍の正式な通達があると、ここから一切の研究サンプルが持ち出せなくなる。本国へ送られる設備などは、一切合財、軍の厳重な管理下に置かれて、綿密な検査の後に、陸軍の輸送機で本国へ送られる。研究に関するもので本国へ持ち出せるのはデータだけで、生体や、細胞、遺伝子等のサンプルは、すべてここで破棄しなければならない。しかし、今なら持ち出せるチャンスがある。ただし持ち出すことは可能でも、問題は送り先だ。送る物の内容が内容だけに、大学や民間の友人の研究機関に送るわけにもいかないし、軍関係の研究施設に送るのはもちろん論外だ。君に、何か名案はないかな?」
そう言われて、ブラウンは以前から自分が考えていた案を語り始めた。
「タッツェムベルムの幼体は、過酷な環境に耐えるほどまでに成長しています。ご存知のように、タッツェルベルムは過酷な条件下、例えば極度の低温下では、自己を仮死状態にして数ヶ月以上生き伸びる能力を持っています。私は、あの幼体を冷凍便で本国の自宅に送ったらどうだろうかと考えています。ペンシルバニアの自宅の私の部屋には、研究用の特殊な冷蔵庫がありますから、妻にそこに研究用の素材と言う事で保存して置くように命じます。」
「危険はないかな?」
「タッツェルベルムと雖も、低温下では活動できませんし、搬送中に例え何らかの事故で低温下から抜け脱しても、幼体の段階では危険はありません。一月には私も自宅に戻るわけですし、一ヶ月ちょっとの間なら自宅の冷蔵庫でも保管できるでしょう。むしろ心配なのは、搬送中に幼体が低温状況に耐えられなくなったり、気圧や環境の変化で、仮死状態中に、本当に死んでしまうことの方です。」
所長は、しばらく考えた。その間に、ブラウンは一口アルマニャックの入ったグラスに口を付けた。そしてスチュアート所長は、一つの決断を下した。
「君の案をすぐに実行に移してくれ。」
「分かりました。」
ブラウン博士はそう言ってから、アルマニャックを飲み干し、静かに部屋を出た。
午後半ば、ブラウンは食堂内の厨房を訪れた。厨房には、五名の料理人が忙しく働いている。夕食の仕込みの最中だった。
「やあ、料理長。調子は、どうだい?」
料理長が、驚いた様子で言った。
「これは、ブラウン博士。キッチンにおいでになるなんて、珍しいですね。何か御用ですか?」
ブラウンは、厨房内をざっと見回して言った。
「いやぁ、用というほどのものでもないのだけどね。実は、本国を離れてかなり長いのでね、たまにはうちの女房に南洋の珍しい魚でも送ってやろうと思ってね・・・。冷蔵庫に、何かおいしくて変わった物はあるかな?」
「魚は、まあ一般的なものしかないですね。珍しいものと言ったら、大型の海老か蟹くらいでしょうか。全部、地元で取れたものですよ。」
ブラウンは、顎に手を当てて考えた。
「うん、蟹なんて良いかなぁ…。一つ分けてもらえないかね?もちろん、代金はきちんと払うよ。」
料理長は、笑って応えた。
いや、たくさんありますから、一つや二つ差し上げますよ。他ならぬ、ブラウン博士のご依頼ですから。」
ブラウンは、ニッコリと微笑んで言った。
「すまないな。ありがとう。保冷ボックスと保冷剤も、分けてもらえるかな?」
「もちろんです。」
「それじゃ、明日の朝取りに来るよ。」
そう言って、ブラウンは手を軽く振って厨房を出た。
厨房を出ると、ブラウンはすぐにビンセント博士のチームの研究室へ向かった。部屋の中にはビンセントの他にはスタッフは二人しかいなかったが、ビンセントはブラウンをチーフ専用部屋に案内した。
「培養の状態は、順調なようだね。」
と、ブラウンが言うと、
「ええ、おかげさまで。」
と、ビンセントが返した。
「ところで、例のD5番のタッツェルベルムだが、いよいよ軍が本国に送るように命じてきた。明日、私が休暇を装って島を出て、軍の輸送便に載せる予定になった。」
ブラウンがこう言うと、ビンセントは答えた。
「そうですか。分かりました。明日、Dの5を搬出できるようにしましょう。うちのスタッフや他のチームには、D5番幼体は成育器の故障で死亡したことにしておきます。」
そう言ってから、ビンセントは初めて彼の持っている疑問をブラウンにぶつけた。
「ところで、博士。D5番の幼体について、どうしても解せない点があります。」
「何かね?」
「D5番は、水際作戦用の水掻きのあるタイプと言うことでしたが、他の幼体と同様、成育過程で手足の指から水掻きが消えてしまいました。現在、水掻きの痕跡すらもないのです。これは、遺伝子設計段階での失敗なのではないでしょうか?」
ブラウンは、慌てずに答えた。
「それなら心配はいらないだろう・・・。おそらく一旦消えた後に、成体に成長する時に、改めて水掻きが形成されるのだと思う。」
ビンセントは、一応頷いて見せた。しかし、逆にビンセントのこの件に対する疑惑は一層深まった。まるで、ブラウン博士が彼の質問を予想していたかのようにスラスラと答えたからだ。ブラウンにしても、ビンセントと同様、"水掻きのあるタイプ"を見るのも接するのも初めてのはずだ。どういう風に育つかなど、知っていようはずがない。軍が必要としているはずの ”水掻き”が無いと知って、慌てふかめかないのはおかしい・・・ビンセントは、そう感じた。しかし、軍の最高機密事項である以上、他人に相談することはできず、彼の胸に内にしまっておいた。
ビンセントの部屋を出た後、ブラウンは自分のチームの部屋に行き、明日から七日間の休暇を取ることをスタッフに告げ、形式上の休暇申請書類を書いて、事務方のスタッフに渡した。
翌日、ブラウンは料理長からもらった蟹の甲羅を外して中身をくり貫き、その中に脱脂綿を敷き詰め、その上にタッツェルベルムのD5番幼体を載せ、再び甲羅で蓋をした。その蟹を保冷ボックス内に入れ、蟹の周りを保冷剤で敷き詰めた。保冷ボックスの蓋をして、厳重に梱包し、注意書きの紙を貼り付け、彼の旅行バッグに入れた。
その後すぐにキーファー一等兵の操縦するボートで鉄かぶと島を出て、サンボアンガの港に行った。そこから予約済みの運転手付きの車をチャーターして、ミンダナオ島の主都ダバオへ向かうのだ。ダバオの信頼のおける航空輸送業者を手配済みで、冷凍便で"蟹"を本国へ送ってもらうのだ。