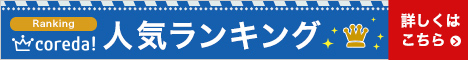入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第三章 バーでの会話
シュルツ博士とホワイト博士が浜辺を歩いているちょうど同じ時刻に、研究所の食堂に隣接して造られた小さなバーには、アルバート・ブラウン博士とロビン・ウォーカー博士、マイケル・ビンセント博士、そして陸軍のジョシュア・キングスレー少尉の四人が、半円形のカウンターに並んで飲んでいた。
鉄かぶと島の研究所棟のすぐ側に居住棟があって、ちょうどその二つをつなぐように、真中に食堂と娯楽施設棟が造られていた。食堂が真中にあるのは、勤務時間の者も、非番の者も共に食事ができるように配慮したためだ。そして、食堂に隣接して、ジム、ゲームコーナー、ビデオ上映ブース、図書室、バーが、それぞれ小さいながらも設営されていた。
ジムには、身体を鍛えるための各種運動機器が設置されている。ゲームコーナーでは、ダーツ、エアーホッケー、ビリヤードなどを楽しむことができ、ビデオ上映ブースでは、プロジェクターと八十インチのスクリーンで映画などを楽しむことができた。図書室では、一般の蔵書の他に、定期的に物資輸送ボートで運ばれてくる週刊誌等も読むことができた。バーは、十五、六名も入ればいっぱいになってしまう小さなスペース。バーテンはいないので、自分でグラスに酒や氷を注ぐのであるが、酒はかなりの種類が揃えられていた。これらの施設は、他に娯楽もない孤島で生活する研究者達に対する、精一杯の軍の配慮であった。
しかし実際のところ、研究員達は、自分の部屋で夜を過ごすことが多かった。自分のパソコンで本国の家族や友人とメールしたり、ゲームをしたり、音楽や映像ソフトを個人的に楽しんでいる者が大半だった。気分転換のための島の散歩(とは言っても徒歩三十分ほどで島の主要部分の散策は終わってしまうのだが)や、昼間の海岸でのマリン・スポーツなども、人気の余暇の過ごし方であった。
バーで集まって飲むのは、定期的な会議の後や、チームでの研究に進展が見られた時などの機会が多い。余程の酒好きでない限り、ここで一人で飲む事はしなかった。警備のために島に駐留している兵士達は、あまり研究員達と交流を持たなかったし、一緒に飲むことも稀だった。双方の話題があまりにかけ離れているためでもあるが、小隊を率いているジョシュア・キングスレー少尉だけは、好んで研究者達と話をした。理由は、警備や機密漏洩防止の都合上、研究者個々人のことを把握しておく必要性があったのと、彼自身が学問的な会話が個人的に好きだったこともある。事実、キングスレー少尉は大学で政治学の学位を取った後に軍隊に入隊したのであるが、今でも政治に限らず様々な分野の本を読んでいた。現在三十五歳。この研究者のチーフ達と飲むのは、彼にとってこの孤島での楽しみの一つだった。キングスレー少尉は、アフリカ系、メキシコ系、中国系、アイルランド系、それぞれの血をきっちり四分の一ずつ引き継ぐと言う、珍しい出自を持っていた。それが、彼が物の見方を多面的に捕らえる要因となっているだけでなく、国籍不明的な魅力のある容姿を形づくる要因ともなっていた。
キングスレー少尉は、今日は聞き役に回っていた。と言うのも、DNA組替技術部門のチーフである、ロビン・ウォーカー博士が愚痴っていたからである。しかし、これは毎度のことで、皆、ウォーカー博士を半分からかいながら飲んでいた。四人しかいないバーは、ウォーカー博士の独演会場と化していた。ウォーカーは、ウィスキーをロックで飲みながら、声を荒げていた。
「考えても見てくれ。今回の研究では、それぞれが重要な役割を果たしている。シュルツのチームが遺伝子配列の設計図を作り、我々のチームが実際にその組み替えを行う。で、君のチームが・・・」
と言って、ウォーカー博士はビンセント博士を指差した。
「組織の培養や、人工授精などを行う。で、最終的にホワイト博士のチームが、それを育てるわけだ。しかし、研究者の間では、どうしたってシュルツ博士が一目も二目もおかれてしまう!言うなれば、彼はスポーツカーのデザイナーであり、設計者なんだ。それに引き換え、俺はそれを自動車工場で組み立てる工場労働者か職人ぐらいにしか、見られていない!遺伝子組み替えが、どれだけ知識と経験を要する繊細な技術か、誰にも分かっていない!」
現在三十七歳のロビン・ウォーカーは、他の博士たちと違い、苦学してボストン大学に入学し、奨学生として大学院まで出たと言う経緯があり、プライドは人一倍高い。人から彼に相応しい敬意を払われているかどうか、彼は始終気にするような男だった。いつも第一印象を気にしていて、髪はいつもきっちりと整えられ、服装も染み一つないものを着ていた。チームのスタッフに対する細かい配慮も忘れなかったが、それはやはり周りからの評価を気にしてのものだった。母方の祖父はフランス人で、彼自身もユーモアやウィットを解したが、酒を飲むと愚痴っぽくなる傾向があり、この夜はそれが最高潮に達していた。ブラウン博士は、年代物のポートワインを飲みながらウォーカーの話しを聞いていたが、淡々としゃべり始めた。
「ご存知の通り、私はドイツ移民の三世だが、よく爺様が言っていたよ。かつてドイツでは、子供の時に、学業へ進むか、職人の道に進むか決めなきゃならなかった。まあ、子供にそんな事を決めさせるのは酷ってもので、大抵が親の意向が反映されててね。爺様も、親の意見に従ってカバン職人の道を歩んだのだよ。ただ、爺様はカバン作りが嫌で嫌で仕方なかったらしい。」
ウォーカーが、絡むように言った。
「で、一体何が言いたい?」
「まあ、最後まで聞いてくれ。ドイツでは、優れた職人が尊敬を受けるのが当然でね。爺様が、一杯引っ掛けにパブに行くと、常連の客が爺様のいつも座っている席を空けてくれたそうだ。暗黙の指定席って奴でね、それくらい敬意を払われていたそうだ。ところが、ある日爺様がそのパブに行くと、よそ者がたまたま爺様のその指定席に座っていたそうだ。よそ者だから、その席が爺様の指定席だなんて知るはずがない。爺様が入り口で突っ立っていると、パブの店長が、そのよそ者に爺様に席を譲るようそっと耳打ちしたそうだ。しかし、よそ者は酔っていたから、爺様を他に座らせりゃいいだろとか何とか言ったらしい。そしたら、どうなったと思う?」
ビンセントが、ビールを飲みながら答えた。
「分からないな?ケンカにでもなった?」
ブラウンは、正解を告げた。
「いや。パブにいた他の常連客達が一斉に立ち上がり、そのよそ者を担ぎ上げ、さっさと店の外に放り出したそうだ。常連客たちは、何事も無かったかのように静かに席に戻り、また飲み始めたそうだ。それで、うちの爺様は、空いたいつもの席に座ったそうだ。その時、爺様は初めて、カバン職人も悪くないかな・・・と思ったそうだ。」
ウォーカーが、返した。
「それって、説教話か?カバン職人の爺様と同様、俺に遺伝子組み替え職人に甘んじていろと?」
テキーラ入ったのグラスをテーブルに置いて、キングスレー少尉がここで初めて口を挟んだ。
「いや、そう言う意味じゃないと思うよ、ウォーカー博士。どんな職種だって、優れた仕事を行えば、尊敬を受けるに値するって言う意味だと思うな。」
ウォーカーの絡み酒は、止まらなかった。
「考えても見てくれ!」
この"考えても見てくれ"と言うフレーズが、彼の口癖だった。
「シュルツの研究は、いつかノーベル賞を取るかもしれない。しかし、少なくとも俺のやっていることは、ノーベル賞の"ノ"の字にも引っかからないことは確かだ!ビンセント!君のやっている仕事や、ホワイト博士の仕事だって俺の仕事と大同小異だぞ!」
そう言われて、マイケル・ビンセント博士が返答した。しかし、ウォーカーをたしなめる様子はまったくなく、楽しんでいる様子ですらあった。
「別に、ノーベル賞を取ることが研究者としての僕の目標ではないよ、ウォーカー。自分で納得の行く研究ができるかどうかが大事な点で、他の人の評価や結果は後から着いて来るものじゃないかな。」
マイケル・ビンセントは、極めて温厚な正確で知られていた。温厚と言うより、自分の世界に入って空想するタイプと言ったほうがより正しいかもしれない。彼はカリフォルニア生まれだが、小さい頃ハワイに移り、その後の人生の大半をハワイで過ごし、大学も地元のハワイ大学を卒業した。すでに四十歳を過ぎた彼が、生き馬の目を抜くような熾烈な科学界の競争の中でも、のんびりとした性格を保っていられるのは、ハワイと言う温暖な気候風土の中で彼が育くまれたせいかもしれない。また、やはりハワイ生まれの妻と三人の子の存在が、より一層彼を家庭的な暖かい人間にしているのかもしれない・・・彼の家族は、今ハワイに住んでいる。学生時代、同級生がフットボールやサーフィンで青春をエンジョイする中、彼は一人思索に耽りながら、時折キャンバスに絵筆を走らせたり、詩を読んだりしていた。理工系の人間でありながら、絵画や詩などの文化系的な方面にも大きな興味を持っていた。彼は、競争や賞レースと言うものとは無縁で、世事から超然としているところがあった。
ウォーカーが、彼に言った。
「君ならそう言うと思ったよ、ビンセント!しかし、俺は人から認められたいし、ノーベル賞だって欲しい!ついでに言ってしまえば、金も欲しい!俺は人生の成功者になりたいんだ!」
こうした明け透けなウォーカーの性格が、好かれる理由だった。普通なら、打算者っぽくて、かつ愚痴っぽい性格は嫌われるが、周りの人間がウォーカーを嫌わずに一緒に飲みたがるのは、彼には裏表がなく、ストレートで分かりやすいからである。そうでなければ、研究チームのリーダーには到底なり得なかっただろう。殻になったグラスに再びポートワインを注ぎながら、ブラウンが言った。
「一つ言えることは、ここでの研究は陸軍の機密事項に属する事であり、決して外に知られることがないと言う事だ。シュルツ博士がここで如何に優れた研究をしようと、ウォーカー君と同様、ノーベル賞を取ることはあり得ないな。ここで研究している者は、天才であろうとなかろうと、皆等しく日陰者と言うわけだ。"陽のあたる場所"を歩きたければ、明日早起きして海岸を歩くことだな。」
キングスレー少尉が、続けて言った。
「それは、私と私の部下にも言えることだな・・・。この平和な島にいる限りは、戦争も内乱もない。と言うことは、武勲の立てようがまったくない。勲章ももらえないし、昇級も遅い・・・。もっとも我々の場合は、武勲を立てたければ、危険な戦場で命のやり取りをしなくちゃならんがね。少なくとも、ここには金メダルと引き換えに命を差し出そうと言う者はいないだろ?」
キングスレーの言葉には重みがあった。彼は、アフリカでの実戦経験があったからだ。三年前、平和維持軍として、アフリカの小国の三国が接する国境地帯に派遣された時、彼の所属していた部隊は、反政府ゲリラの襲撃を受けた。部隊の移動中に受けた突然の攻撃だったので、反撃に手間取った。当時、彼はまだ若い伍長だったが、彼の小隊の二等兵二名が死亡し、彼自身も足に銃弾を受けた。他の小隊の兵士も含めると、全部で五名が死亡し、七名が重傷を負った。キングスレーはその後本国へ移送され、銃創が癒えてから後、この鉄かぶと島へ配属されたのである。この島の警備に配属されていた彼の部下達は、伍長のビル・ノートンを除いて、全員が二十代前半の若い兵士で誰も実戦経験がなかった。実戦経験のあるキングスレー少尉とノートン伍長は、若い兵士達から尊敬の眼差しを受けている。キングスレーにとっては、国が与えるブリキの勲章よりも忠実な部下の信頼の方が、遥かに意義あるものと感じていた。彼の部下は現在わずか八名だが、ローマの百人隊長の気概を持って任務に当っている・・・平穏な島の警備であっても。
ブラウンが壁の時計を見ると、針はそろそろ十二時に差しかかろうとしていた。彼は、皆に告げた。
「さあ、明日からもハードな仕事が続くぞ。話しはこのぐらいにして、今日はここらあたりで引き上げるとしよう。」
なんだかんだ言っても、ウォーカーもブラウンに対し尊敬の念を持っていたのでその言葉に従い、グラスのウィスキーを飲み干した。他の面々も、それぞれのグラスの中身を飲み干し、それぞれ居住棟の自分の部屋へ戻っていった。