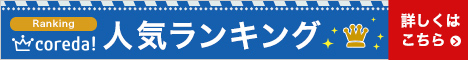入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第二章 ビーチでの会話
会議があった日の夜、鉄かぶと島の砂浜をカレン・ホワイト博士とサム・シュルツ博士の二人が歩いていた。この島はほぼ全体が木々で覆われ、工事で切り拓かれた研究所周辺の広場と道以外で、木々が茂っていないのはこの砂浜だけだった。空は晴れていて、空には星が輝いている。彼らは、それぞれ生物学界と生化学界の第一人者ではあったが、星に関しての知識は子供並だった。事実、どの星がどの星座に相当するのか、まったく分からなかった。
ホワイト博士が、最初に口を開いた。
「私はね、酷い不安に苛まれることがあるわ・・・。夜、悪夢で飛び起きることもしばしば。」
シュルツ博士は、そう言った相談事にはなれていなかった。研究一筋の人生で、MITでの博士論文"DNA配列における機能塩基配置の特定及び相関する塩基配置の予測"は、学会でもセンセーションを巻き起きした。一方、人間関係については、四十歳を越えた今でも、同年代の同僚達と比べるとかなり経験が浅かった。決して、人間嫌いと言うわけではないのだが。時折おかしな受け答えをしてしまい、同僚達から敬愛をこめて笑いの種となつていた。そんなわけで、未だに結婚相手に巡り会っていない。シュルツ博士は、言葉を選んで言った。
「悪夢って、どんな?」
ホワイト博士が、ゆっくりと答える。
「去年亡くなったタッツェルベルムの夢なの。ブラウン博士は、"足の生えた虫"なんて言うけど、彼の本質はむしろ犬やイルカに近いのよ。ずっと身近で育てた私や、私のスタッフなら良く分かっていることだけど・・・。確かに見かけは不恰好だけど、慣れると可愛いのよ。私達のチームは、親しみをこめて彼を"ジョン"って呼んでいたの。私が昔飼っていたビーグル犬の名前よ。夢の中でね、ジョンが人間の言葉で私に語りかけるの・・・僕は何のために生まれてきたの?って・・・。彼は、子供のように涙を流して泣いていたわ。そこで、私は起きるの。しばらくして、それが夢だったと悟るわけ。」
シュルツは、ホワイトの言ったことを頭の中で反芻した。
「それは夢だよ、ホワイト博士・・・。僕らは、みんな四六時中研究だけに没頭して生活しているから、実験体への感情移入の度合いも激しいのだよ・・・。」
「分かっているわ、シュルツ。私はね、ふとアインシュタインの事を考える事があるの。」
「アインシュタイン?」
「そう、アインシュタイン。物質は、巨大なエネルギーを持っていると言う彼の理論が、原子爆弾を作ったわよね。実際に原爆が使用されると、アインシュタインは心から悩み苦しんだわ。彼の研究が、結果的にモンスターを生み出したから。大好きだった日本人を、大勢焼き尽くしたから。彼は、その後死ぬまで原爆廃絶のための運動をしたのよ。私達がやっていることも、遺伝子界の原爆を造リ出すことではないのかしら・・・。そう思うと、不安でたまらないのよ」。
波が寄せては引いていく音だけが、辺りを包んでいる。ホワイトとシュルツの足元を、波が覆った。シュルツが、口を開いた。
「それは、君だけじゃないよ。この研究に携わる研究員全員が、心に抱いている不安でもあるんだから。だから、この研究に参加するためは、詳細な心理学的な調査と分析をされたんだ。ここに集められた研究者は、その重圧に耐えられると判断されてここへ送られたんだよ。僕も、そして君もね・・・。それに、この研究は僕らがやらなくても、他の人が成し遂げたに違いないよ。」
「そうね・・・。でも、不安は消えそうにないわ。今までに、ジョンの前にも何百と言う実験体が、培養や生育の過程で死んでいるのよ。若い時に、動物実験用のモルモットで同じような経験をしたけれど、今回はもっと辛いわ。時々感じるの・・・私達は、自然界の崇高な領域を侵しているのではないかって・・・。私達は、DNAを組み替えることはできるけど、命そのものを生み出すことはできないわ。私達は、命をもてあそんでいるとまでは言わないけれど、触れてはいけない領域に足を踏み込んでいるのではないかって・・・。」
鉄かぶと島の砂浜のビーチはとても短く、二人は既にビーチの真中まで来ていた。シュルツは、夜空を見上げて言った。
「今日の会議で、ブラウン博士が、僕の方を見てマッド・サイエンティストとかなんとか言ったでしょ。もちろん、博士独特のジョークなんだとすぐに分かったけど、一瞬ドキッとしたよ。研究に没頭するあまり、僕はDNAを単なる塩基配列の鎖にしか見られなくなっていたからね。そこに生命の神秘が存在しているなんて、考えることすらしなくなっていたよ。毎日研究に終われていると、成果ばかり気にして感覚が麻痺してしまうのかもしれない・・・。確かに、僕らがしていることは、罪の大きさを感じるには十分な事かもしれないな。」
カレン・ホワイトは、サム・シュルツの横顔を見た。研究者に有り勝ちな、ファッションとは無関係な服装と、適度にボサボサの髪型。そして、痩せこけた頬。もしこれで眼鏡をかけていたら、正にマッド・サイエンティストに見えるわ、と思ってホワイトは可笑しくなった。ここの研究者なら皆知っていることだが、シュルツほど愛すべきキャラクターの人間はなかなかいない。何事も一生懸命になり過ぎて、周りの人にはそれが可笑しく感じられてしまうのだ。
「今日は、つまらない愚痴を聞いてくれてどうもありがとう。」
とホワイトが言うと、シュルツが応えた。
「どういたしまして。僕なんかでよかったら、いつでもどうぞ。」
孤島に打ち寄せる波の音は、いつまでも心地よく響いていた。