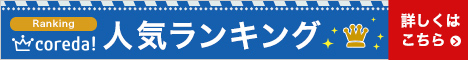入口 >トップメニュー >ネット小説 >ベルム達の夜明け >現ページ
第一章 鉄かぶと島の研究所
フィリピンの首都マニラから千キロ南、スールー海とセレベス海に挟まれたスールー諸島。その中の数ある無人島の一つに研究所が建てられたのは、二十世紀も終わりに差し迫った1999年のことだった。建てられた当時の研究所の大きさは、床面積にして三百平米と言う小さなものだったが、それから二十年以上の月日の間に建て増しされて、2027年3月の現在、三倍以上の大きさの建築物になっていた。 研究所は、表向きはフィリピンの民間財団の海洋研究センターの一施設と言うことになっていたが、その実はアメリカ合衆国陸軍の技術研究所であった。アメリカがフィリピンから軍事基地を撤収して久しいが、フィリピン政府の官僚や政治家のそこかしこに依然と太いパイプが残っており、アメリカ陸軍が秘密裏に無人島の一つを借り受けることは難しいことではなかった。それも、それなりの大金が流れるとなるとなおさらであった。
島自体は、歩いて三十分以内で一周できてしまうほど小さい島だったが、逆にこの小ささが軍の警備には都合が良かった。少ない警備兵の数で、島全体を監視できるからだ。実際、この島には変則的な小隊の九名の兵士が配属されているだけで、上官を除く八名が交替で島と研究施設の警備に当っていた。研究所の研究員の数は、職員の数も含めて約四十名。時折、交替によって祖国に帰る者があったり、新たに派遣されて来る者があったりして、人数は若干変動する。
アメリカ人達は、この島を「鉄かぶと島」と呼んだ。沿岸から見たこの島の輪郭が、正に旧ナチス・ドイツ軍のヘルメットのようだったからだ。地元人が島をどう呼ぶかは、アメリカ人である彼らにはどうでも良いことだった。一生涯ここで過ごす分けでもないし、地元との人との交流はまったく無いのだから。彼らは少し長い休暇には、ミンダナオ島のダバオにサンボアンガ経由で出かけることもあるが、ダバオですら島から五百キロ以上も離れているのだ。研究者達は、普通の週末は島から出ずに、ビーチや娯楽室などで過ごすのが普通だった。彼らの刺激的な研究内容に比べると、実に刺激のない退屈な日常生活だった。島には簡単な船着場の桟橋が造設され、小型のボートが二艘接岸することができた。物資は、すべてここから運び込まれる。
島の東側の水深の深い場所に桟橋が作られ、島の反対の西側には砂浜の海岸があった。研究棟や居住棟の建物は、島の中央よりやや東側桟橋寄りの切り拓いた広場に建てられていた。島のもっとも標高の高い場所は海抜五十メートルほどだったが、研究棟は標高三十メートルの所に建てられていた。桟橋から研究棟のある広場まで道が切り拓かれ、徒歩と車での移動が可能になっている。研究棟から砂浜までは、人が通れるほどの狭い道が切り拓かれていた。島の南北は、五メートルから十メートルの切り立った崖になっていて、外からの侵入が難しくなっていた。
何故アメリカ合衆国の陸軍が、祖国から遠く離れた地元の猟師すら立ち寄ることのないアジアの孤島に、わざわざ研究所を造ったのか。それは、国内のマスコミや、軍自体からも隠しておかなければならない重大な秘密があるからである。国内では、ひょんなことから秘密が漏れてしまうことがある。それだけではない。この施設を本国から最も離れた場所に置くことによって、緊急事態が起こった際のハザードとしているのだ。研究所の所長、デビッド・スチュアートの心労の大半は、それらの重責によるものである。しかも、近日中にはそれに輪をかけるような重大な発表を、研究員達にしなければならないかもしれないのだ。しかし、それはまだ彼の胸の内にしまっておかねばならない。それが、一層デビッドの心労を増した。デビッドの髪の毛は最近めっきりと白くなり、それが彼を一層老けさせて見せた。実際、彼はもう六十五歳に手が届こうとしていた。
所長のデビッドは、研究所の各部門のチーフ達五名が集まる会議に向かっているところだった。今、二十年以上に渡る研究の成果が、いよいよその実を生み出そうとしている。今日の会議は定例の会議ではあるが、特に重要な会議になる予定であった。しかし、前途には暗雲が垂れ込め始めている。さて、どうしたものだろうか・・・。
彼が、研究所の会議室に着くと、すでに各部門のチーフ達は全員集合していた。部屋の中のエアコンはフル回転で稼動し、ブンブンと音を立てながら、この南海の暑い空気を懸命に冷やしている。テーブルの上には、缶のコーラやマグカップに注いだアイス・コーヒーなど、各自の好みに応じた飲み物が並べられていた。
デビッド所長は、会議室の面々を見渡した。DNA設計・解析部門のチーフ、サム・シュルツ博士、DNA組替技術部門のチーフ、ロビン・ウォーカー博士、生体培養技術部門のチーフ、マイケル・ビンセント博士、研究体管理・育成部門のチーフ、カレン・ホワイト博士、そして研究統括支援部門のチーフ、アルバート・ブラウン博士の五名だった。所長のデビッドは、この中でも特にブラウン博士に最も高い信頼を置いていた。頭脳明晰にして、各部門の内容にも精通し、スタッフからの人望も厚い。この研究がここまでやってこられたのも、表に裏にと彼の尽力があったればこそ、とデビッドは思っている。
アルバート・ブラウン博士は、ドイツ移民の三世で、父親は有名な生物学者、母親は臨床医師でガンの研究を行っていた。息子であるアルバートがこの道に進んだのは、多少なりとも両親の影響があったのは間違いない。彼は十年ほど前に結婚し、ペンシルバニア州のヨーク市の郊外に家を購入した。その後娘が生まれ、その娘も現在六歳になっている。妻は原因が特定できない病気で視力が低下しつつあり、数年以内には視力が完全に失われるかも知れないと診断されている。ブラウン博士がDNA研究にこれほど没頭しているのは、DNAの解析が迅速に進めば、妻の失明を防げるかもしれないと言う切実な思いもあるに違いない。彼が同僚からこれほどまでに信頼されるのは、家族に対する強い思いやりと愛情を、研究者達の多くが感じているせいもあるだろう。
デビッドがテーブルに着くと、定例の会議が始まった。今回、会議の議長を努めるのは、カレン・ホワイト博士。議長の役は持ち回りで、五回に一回は必ず廻ってくるのだった。ホワイト博士は、現在のチーフ・メンバーの中で唯一の紅一点である。誰も年齢に着いては尋ねないが、暗に四十歳代であることは知られていた。しかし、三十歳代と言っても通りそうな若々しい容貌をしている。茶色の髪を後ろに束ね、研究の邪魔にならないようにしている。研究中や会議中以外は、眼鏡を外している。一見優しそうな表情とは裏腹に、こと真剣な議論となったら力強い論理で、他者を駆逐しそうなほどグイグイと押し捲ることもある。そのホワイト博士が、会議の口火を切った。
「では、全員揃ったので始めましょう。本日の会議は定例会議ではありますが、皆さんもご存知の通り、記念すべき特別な会議でもあります。最初に、ブラウン博士からここまでの経緯の報告があります。」
ブラウン博士は、分厚い資料が配られるのを待った。もっとも、それらの資料が実際には必要のないことを良く分かっていた。この優秀な研究者達の頭の中には、資料以上のことがぎっしりと詰っているに違いないのだ。ブラウン博士は、資料が各自の手元に配られるのを待ってしゃべり始めた。
「さて、この研究所では、1999年からDNA研究をしていますが、それから28年もの月日が経ちました。最初の十年程度は、ほとんど基礎研究の域を出ませんでした。研究は遅々として進まず、一進一退を繰り返していました。しかし、現在の所長であるデビッド・スチュアート・・・とは言っても当時はまだ一研究員でしたが・・が研究に加わってからは、研究は急激な展開を見せ始めました。」
こで彼は一度言葉を止めて、敬意を込めて所長の方に目をやった。一同も所長の方に向き直り、所長に短い拍手を送った。所長は、照れながら「よせよ」と言う仕草を両手でした。彼らは全員すでに親しい間柄になっていたので、所長がそう言うことを嫌がることを良く知っていて、冗談で拍手をしたのだった。ブラウン博士は、続けた。
「さて、皆さんはこの島を鉄かぶと島と呼んでいますが、本国の陸軍の上層部は、この島をドクター・モローの島と呼んでいるそうです。」 一同から、笑い声が漏れた。「それは、この島での研究が、DNAの組み替えによる優れた生物を生み出すことを目的としているからです。当然、陸軍としては、戦争に有効な生物兵器を期待しているのでありましょうが、残念ながら我々はマッド・サイエンティストの集団ではありません。一部、怪しい人がいますが。」
と言いながらシュルツ博士を見ると、笑い声が起こった。もちろん、ブラウンの冗談である。
「我々は、ここでの研究が、将来・・・と言ってもそんなに遠い未来ではなく・・・極近い将来、遺伝子治療などに役立つことを確信しています。ここでの研究は、民間では許されないようなDNAの解析や組み替えも許されています。資金も、民間よりは贅沢な方だと思います。これらは、陸軍が研究の資金源であり親元だから可能なのであり、我々はその陸軍に対して、それなりの研究成果を示さなければなりません。そして、ようやくその成果を示せる日が近づいています。」
そう言って、資料の中から一枚の写真を取り出して、ホワイトボードに貼った。
「我々のアイドル、タッツェルベルムです。ご存知とは思いますが、一応念のため・・・タッツェルベルムは、ドイツ語で 足の生えた虫と言う意味です。」
その名前は、ドイツ系であるブラウン自身が名づけたものである。写真には、二本足で立ってはいるが、その容姿は類人猿とはかけ離れた生物が写っていた。昆虫のような固そうな黒光りした殻で覆われた体の上に、やはり殻で覆われた頭が乗っている。顔は、殻の間から目をのぞかせ、口には虎のような歯が並んでいた。手足も、殻の間から鋭い爪を持った指が伸びていた。ブラウンは敢えて口にしなかったが、タッツェルベルムが誕生するまで、何百と言う生体が培養中や生育中に死んだ。その事は、研究者全員が知っていることだったから、言う必要もなかった。研究所の裏には、彼らの墓があった。
「残念ながら、タッツェルベルムは昨年死んでしまいましたが、その体の機能は優れたものでした。見た目は恐ろしげですが、イルカや犬と同等の頭の良さをもち、我々の訓練によって人間によくなついていて色々と覚え、またとても優しい生物でした。その辺の事は、育成に関わったホワイト博士が良くご存知でしょう。」
議長席に座っているホワイト博士は、そう言われて頷いた。
「頭の良さだけが、タッツェルベルムの優れた所ではありませんでした。猛禽類のような高い視力、猫科の動物のように夜間でも活動できる目、しかも人間と同様立体視できる目を持っていました。また、ウサギと同程度の高い聴力を持ち、犬と同程度の優れた嗅覚を持っていました。顎の力は、虎と同等かそれ以上と言って良いでしょう。腕力は、ゴリラに匹敵しました。我々は、これらの能力を発揮するDNA番地を特定し、組み替える事に二十年もの月日を費やしてきて、ようやくここまで達成しました。中でも最高の困難は、内骨格と外骨格の両立でした。」
ブラウンは、資料の中からタッツェルベルムの外骨格のアップの写真を取り出し、ホワイトボードの先ほどの写真の横に貼った。カブト虫のような艶やかな表面の外殻だった。
「通常の生物は、内骨格か外骨格のどちらかしか持っていません。昆虫などの小さな生物は外骨格を持ちますが、陸上で生活する大きな生物となると、その構造上内骨格を持たざるを得ません。我々の雇い主である陸軍の要望には、固い皮膚を持った生物と言う項目があります。我々は固い皮膚について、アルマジロのような角質から昆虫のクチクラ質まで色々と研究しました。それぞれに一長一短があります。アルマジロのような外皮ですと、身を守るには都合が良いのですが、柔軟性に欠けかつ非常に重いので、素早く動くことが困難になります。一方、クチクラ質は多糖類のキチンで出来ていて、硬く、乾燥にも強く、水も通さず、しかも軽いと言う長所を持っていますが、大きな欠点もあります。外殻の気管の直径が僅か〇・二ミクロンしかなく皮膚呼吸量が少ないため、組織に酸素が行き渡らず、激しい運動が困難なことです。そして、こちらの方がより重大な欠点なのですが、成長のたびに脱皮しなければならないことです。構造上、クチクラは一旦造られてしまうと成長できませんから、殻を脱がなければならないのです。新たに殻が作られるまで、生命体は無防備になります。これでは、陸軍が求める要件には到底合いません。昨年タッツェルベルムが死んだのも、このクチクラからの脱皮の失敗が原因の一つです。哺乳動物のような大きな生物が脱皮をするには、様々な困難が伴います。DNAの鎖は、お互い微妙に関連し合っています。DNAのある場所を組み替えると、どこか別の所で不具合が生じ、結果として生命体は死にます。我々の過去は、この失敗の連続でした。我々は、クチクラ質の外殻に変わるものを、ずっと研究してきました。」
ブラウン博士は、もう一枚写真を取り出し、ホワイトボードの二枚の横に貼った。そこには、別の外殻が、写っていた。
「この新しい外殻は、シュルツ博士のチームで先月DNA設計図が完成し、ウォーカー博士のチームでDNAの組み替えが行われ、現在ビンセント博士の下で培養が行われている最中の外殻組織です。この、外殻の特徴的なところは・・・」
そう言いながら、ブラウンは写真の一部をペンで指した。
「これをご覧下さい。この部分は、キャッチ結合組織です。その先には、小さな骨片が付いています。ヒトデの細胞からヒントを得たものです。この結合組織は通常は柔らかいのですが、非常事態時には瞬時に硬くなって骨片を硬く閉じます。これはたいへんな強度があり、小型の拳銃の弾程度では貫通できないほどです。またとても軽いので機動性も高く、皮膚呼吸も可能なので激しい運動も可能です。キャッチ結合組織細胞は母体の成長と同様に成長できますので、脱皮の必要もありません。正に、我々の理想とする外殻構造なのです。これが完成すれば、内骨格と外骨格を両方持った、とても頑丈な生物が誕生することになります。」
彼は一呼吸をおき、最後の結論の報告を述べ始めた。
「この他の陸軍の要望として、単体での無性生殖・・・単為生殖 や過酷な生存状況での生命維持などがありますが、これらについてはほぼ見通しがついています。生物の優れた所をビックアップし、かつとても強い生命力と繁殖力を持った史上最強の生物の誕生は、すぐ目前に迫っています。DNA設計はほぼ完了しているので、今月中にはDNAの組み替えに入れるでしょう。組み替えが完了次第、人工授精と組織の培養を始め、おそらく半年以内には新しいタッツェルベルムの幼生体を誕生させられると思います。」
こうして彼は、これまでの経緯を簡潔に話し終えた。カレン・ホワイト博士が、その後の会議の進行を引き継いだ。誰もが、研究の成功までもう一歩であることを確信し喜んでいて、所長のデビッドが瞳の奥に悲しみをたたえながら会議を見守っていることに気がついた者は、一人としていなかった。