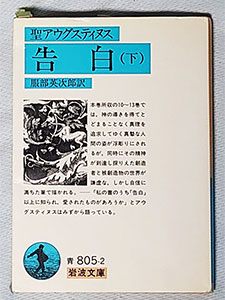クリスチャンのための哲学講座
入口 >トップメニュー >キリスト教研究 >諸宗教 >哲学入門 >現ページ
5.人間の生きる終極の目的/アウグスティヌス

僕がアウグスティヌスの「告白(上・下巻)」を読んだのは、今(※2010年)から17年も前のことである。アウグスティヌスはローマ時代末期の最大の神学者にして思想家である。彼の思想は、前期中世哲学だけでなく、その後のキリスト教神学にも多大な影響を与えた。と言う訳で、アウグスティヌスの思想は、哲学を考える上で避けては通れない。
彼の主要な主張は「告白」を読んだ時に理解したつもりだが、枝葉末節の記憶が薄くなってしまったので、今一度、この600ページの書物を読み返してみた。この「告白」の内容に移る前に、アウグスティヌスその人の人生、ならびに彼の生きた時代の背景について軽く触れておこう。
コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認したのが313年で、アウレリウス・アウグスティヌスが誕生したのはそれより40年ばかり下った354年11月13日である。彼は、当時のローマ領北アフリカのヌミディア州の農林地帯の中心地であるタガステ(※現在のチュニジアの首都チュニスに近い地域)で、ぶどう園や農地を持つ中産者の父パトリキウスと、信心深いカトリック信者の母モニカの間に生まれた。
キリスト教は誕生後に残酷な迫害の道も辿ったが、ローマ帝国内で広く普及しだし信徒数が増え、彼らを敵としてはローマ帝国の統一は不可能と言うところまで行きつき、前述のキリスト教公認へと至った。しかし、キリスト教の信仰が当時の全時代に渡って一枚岩だったわけではない。例えば、325年のニケーア(orニカイヤ)公会議によって、イエス・キリストの神性を否定する"アリウス派"は異端とされ、アタナシウスの"三位一体説"を正統教義とした。
また、従来の哲学と、キリスト教信仰の間の問題も争われていた。(科学では説明できない)"非合理な要素"を含むキリスト教を、ギリシャ哲学の"合理性"と、どう折り合いを付けるかと言う争いは、"知"と"信"のどちらを優先するかと言う問題となった。グノーシス派は「神の存在を確かめなければ信仰は不可能」とし、テルトゥリアヌス(160~220年頃)は「非合理だからこそ私は信じる」と述べた。前者は人間の"知"を絶対的に重視し、後者は"意志(信仰)"を重視した。こうした論争の中、キリスト教の教義を確立したのがアウグスティヌスである。アウグスティヌスの思想には、知性の重視と意志の重視が混在している。
アウグスティヌスによれば、神の存在について疑いが可能なのは、疑いえぬ真理(永久真理)があるからである。疑い得ぬ"真理"と言う基準があってこそ、初めてそこからズレたものが疑いの対象になる。しかし、有限の存在である人間に永久真理を作り出すことなどできないのだ。永久真理を作り出す永遠の知性を持つ存在、それが神であると彼は言う。とてもプラトン的な知性主義の影響が伺える。
しかし、信仰については、非合理的な意志が重要な役割を果たす。最初の人間アダムが自分の意志で罪を犯し、その結果、世界に(人類に)罪が及んだ。所謂"原罪"である。この罪を救えるのはイエス・キリストだけなので、罪から救われるには彼を信じるしかない、とアウグスティヌスは言う。余談だが、アダムの罪が全人類の原罪となると言う思想は、普遍的本質をめぐる"普遍論争"へと発展するが、このページの趣旨からやや逸れるのでここでは触れない。
アウグスティヌスとその時代の背景をざっと見たところで、マニ教徒であったアウグスティヌスがいかにしてキリスト教徒になったと言う、魂の遍歴を「告白」から簡潔に見てみよう。アウグスティヌスの育った家庭は決して裕福ではなかった(※"タガステの貧しい市民"/本文の記述より)ようだが、教育には厳しい家庭であったようだ。しっかり勉強しないと教師に鞭打たれるので、仕方なく小難しい科目も勉強していたが、本当は芝居を観たり、面白い物語を読みふけったりする方が好きだったと語る。勉強そのものはその後の人生で大切であることは認識しているものの、やはり多くの点でおかしな面があることも感じていた。一例をあげると、人間は文法家の規則に反する事は恐れているのに、神の掟は平気で無視する…おかしなことだ。彼も少年時代、そのような学問上の規則を学ぶ上で教師や周囲に誹りや鞭打ちを受けないよう狡猾に学び、数々の嘘もついたことを告白する。青年時代に至っては、仲間から一目置かれたいという理由で、盗みや数々の非行を行ったことを正直に語る。16歳から19歳までのカルタゴでの学校では首席もしめたが、その名誉の学問とは"裁判"の法廷論争で"人を欺く"弁論術であった。首席の彼は得意になり、虚栄心で膨れ上がっていた。その頃、肉の情欲に溺れたことも包み隠さずに語る。19歳から28歳に至る9年間は弁論術を教えていたが、情欲による女性との関係を結び、マニ教の迷妄に溺れ、また占星家を信じたこともあった。彼は、医術に優れ名声のある地方総督と知り合いになった。総督はアウグスティヌスに占星術の迷信から離れよと説得したが、彼はそれを受け入れなかった。ちょうど、その頃、彼は親しい友人を病気によって失った。しかし、彼は悲しむばかりで、どこにも安息を見出さなかった。
彼は、幼年時代、少年時代、青年時代、いずれの頃も、神に背いて生きていた、その罪を告白する。子供だから"罪"がないと言うことはない。ただ成長するにつれて、"学校教師や家庭教師、球や雀"から"知事や国王、黄金や領地"に対象などが変化するだけで、人間の本質に変化はないのである。
さて、アウグスティヌスは若き日よりマニ教(※1)の教徒であった。母はキリスト教徒であったのでこれを嘆き、日々、息子のために涙をもって祈っていた。アウグスティヌスが29歳の時、マニ教の有名な司教であるファウストゥスの話を聞く機会を得た。ファウストゥスはその弁舌によって評判を得ていたが、アウグストゥスは、彼が未知の事実だけでなく虚偽の事実をも虚妄の傲慢さで語り、自分の主張をあたかも神自身の言葉であるかのように美辞麗句を並べているのを聞き、自由人に相応しい学問に通じていないことを看破した。アウグスティヌスは、雄弁だかと言ってその内容が正しいわけでもなく、一方で訥弁(とつべん=たどたどしい弁舌)だからと言って内容が虚偽であるわけでもない、つまり弁舌の優劣と内容の真偽は関係ないのだ…と語る。ファウストゥスに失望したアウグスティヌスは、次第にマニ教から離れていった。
※1:マニ教=マニによって開始された宗教。両親はユダヤ教の流れをくむ新興教団に属していたが、マニは啓示を受けてユダヤ教から独立して開教されたとする。ユダヤ教の影響以外に、ゾロアスター教からは"善悪二元論"、キリスト教からは"福音主義"に影響を受けて戒律主義を否定し、グノーシス主義からは"智慧と認識"重視の影響を受けた。アウグスティヌスも、この「告白」にてマニ教の教義について言及しているが、(善悪二元論の立場で)人間の肉体は闇に汚されていて、植物は光を有していると見なし、肉体を"悪"、霊魂を"善"の住家とした。マニ教は、地域ごとに教義を柔軟に変えて発展したが、結局は各地で異端とされたり逆に多宗教に吸収されたりと独自性を保てずに消滅した。しかし、マニ教の宗教形式は、イスラム教の成立に影響を与えたとされる。
その後アウグスティヌスは、母の"留まってほしい"と言う願いを振り払って、大都会のローマへ赴く。ローマで弁論術の教師となり、それから同じく弁論術の教師としてミラノへ赴く。彼は、ミラノでキリスト教の司教アンブロシウスにまみえた。彼の説教は、あの雄弁なファウストゥスのように爽快で魅力あるものではなかった。アウグスティヌスが興味のある対象は"弁論"であり、その内容に関しては無関心な、否、嘲笑的な傍観者であったが、アンブロシウスは健全な救いを教えていて、アウグスティヌスは知らず知らずに救いに近づいていた。
しかしアウグスティヌスは、マニ教の荒唐無稽な教えからは脱していたものの、カトリック教会の信者となったわけでもなかった。それは、彼の言葉を借りれば「悪い医者にかかった人はそれにこりて、良い医者にも身を委ねることを恐れる」のと同様なことが魂の健康にも起こっていたのである。そんな中途半端な日々が続く。"聖書がどうして神の霊によって人類に与えられたと言う事を君は知るのか?"、"善であられる神がこの万物を善として造られたのに、悪はどこから起こるのか?"など、様々な疑問が彼にはあった。
だが、アウグスティヌスは、アンブロシウスの説教によって次第にカトリックの教えを理解していく。彼は、マニ教、占星術、古代ギリシャ哲学、様々な人間的知恵に興味をもって臨んでいたが、マニ教の荒唐無稽な教えを脱し、占星家の虚偽の占いを退けた。プラトン派の書物には、永遠な御言葉の神性はみられるが、そこにキリストの受肉や救いは見いだされなかった。人間が作り出した傲慢によっては神に至ることはできない、ただキリストのみが救いにいたる道である、と言うことを知る。その他、紆余曲折を経ながら、アウグスティヌスは聖書の教えを受け入れる。そして、ミラノにおいて実子アデオダトゥスと共に洗礼を受けた。涙の祈りを持って息子の救いを望んだ母の願いは、こうして遂に実現した。アウグスティヌスが主に使えるため、若者エウォディウスと共にアフリカに行く準備をして、ティベル河口のオスティアまで来た時に、彼の母は熱病のため亡くなった。ここまでが上巻(原書の1~9巻に相当)300ページの大よその内容である。
"告白"の下巻300ページ(原書の10~13巻に相当)において、アウグスティヌスは哲学的智慧を駆使しながら、しかも人知を超えた神の愛、キリスト教の教義の本質について述べる。
10巻目において、アウグスティヌスは、まず人の記憶について述べる。五感の感覚にによって知り得た記憶、五感に寄らない観念的な記憶、また記憶の忘却について述べた後、まだ達成しない人間の幸福はどのように人間に知られているのかを問う。人間の幸福は、神を求めそれを喜ぶことによってしか得られないことを彼は述べる。人の魂は、すべての真理の根源である真理そのものによって喜びを得る時、初めて幸福となると述べる。
続いて、アウグスティヌスは、誘惑を3つの欲に分ける。一つ目は肉の欲であり、人間の5感(味覚、嗅覚、聴覚、視覚など)に基づく欲で様々な快楽の欲があることを述べる。二つ目は好奇心であり(彼はこれを5感の視覚="目の欲"に関連付けている)、(本来はわざわざ見る必要のない)"惨殺死体を見る"ような物珍しい演劇を劇場に見に行く事を例として挙げている。人生の深い探究心と言うようなものではなく、何の利益もなくただ知ることだけが目的なのである。イエスの時代の人々が、ただ"それを見たい"、"経験したい"と言う理由だけで、イエス・キリストに「奇蹟を見せろ」と要望したようなものである。三つ目の欲は高慢であり、人々から受ける称賛を求めることである。称賛を求める心が極まったものが、虚栄心である。この高慢な欲求は、私たち自身の優越を確立しようとして他人の賛成を請い求めるように誘惑するのである。彼は、この"虚栄"と"自惚れ"は最大の危険であると述べる。これは、神の善を受ける事を自分の功績によるものと考え、またその善を他人が受けることを妬むのである。
アウグスティヌスは、3種の欲望のうちに現れている自分の罪深い病を考察した後、彼は自己が救われるための神の右手を求めた。それはキリストのみが可能な救いであった。神と人との仲保者は、神であると同時に人、人であると同時に神でなければならないが、それがイエス・キリストである。
さて、アウグスティヌスの論述は、11巻目に入る。彼は、この巻で「はじめに神は天地を創造された」に象徴される創世記の解釈にとりかかる。天地創造以前の問題についても、彼は敢えて考察に挑む。被造物は神によって造られた者であり、神のように永遠ではないことを考察していく。それは"時間"も同様である。時間と言う概念は天地の他の被造物と比べて人間には分かりにくいが、時間すら永遠ではなく神によって造られたのであり"永遠ではない"ことを述べる。天地創造以前には、天地も時間もなかったのである。
天地創造に関する論述は、12巻、13巻へと続く。アウグスティヌスは天地創造の業を霊的な意味も含めて一つ一つ丁寧に紐解いていくのであるが、すべてを述べるととてもこのページに収まりきらないので、彼の主張の要点を記す。神は絶対的存在、絶対的善であり、一方の被造物は相対的な存在であり、無から創造されたのであり、存在と善を欠いている。彼がこの下巻(10~13巻)で神の天地の創造に思いを巡らせるのは、私たち人間の世界や人生の目的が神に向かうのでなければ虚しい…と言うことを論証するためであると言って良いだろう。人間の欲求を終局的に満たすものはただ神のみである、と言う事をアウグスティヌスは天地創造の聖書の言葉から述べているのである。
1巻から9巻までのアウグスティヌスの人生の告白、そして10巻から13巻までの天地創造に関する論考は、一見別々の書物にも思えるが、そこには一本の思想が貫かれている。つまり、神によって神に似せて造られた被造物である人間は、終極的には神によってしか"救い"、"幸せ"が得られないと言う思想である。
これが、告白全13巻の概要である。この「告白」に見られる思想は、その後のヨーロッパの中世哲学、キリスト教神学に大きな影響を与えただけでなく、宗教改革者のルターやカルヴァンにも影響を与え、そして今日に至るまでキリスト教会に影響を与えているのである。
アウグスティヌスは、晩年、故郷のヌミディアのヒッポにおいて司教の職に就いていた。しかし、ローマ領に対する蛮族の脅威は年々増していて、南スペインからヌミディアに上陸したヴァンダル族がヒッポを包囲した。アウグスティヌスは、司教として最後まで市に留まって祈り続けていたが、熱病にかかり430年5月に没した。
現代に生きる我々とアウグスティヌスの哲学の適用について
現代の自叙伝と言うのは、たいてい"自分の自慢"…つまり高慢や自己顕示…であることが多いと思う。「これこれをして、商売で大きな成果を収めました」とか「こんな努力をして、このような賞を得ました」のような自伝が多いと思う。実際に、電車内の雑誌や本の中吊り広告を見回すと「成功のための○○の法則」とか「○○大学から名誉博士号を授与」のようなコピーが踊っている。しかし、アウグスティヌスの「告白」はそういった類の本とは一線を隔している。
この「告白」は彼の自慢ではなく、彼の罪の懺悔であり、同時にその罪の中にある彼を救われた神に対する感謝と賛美である。彼は立身出世を目指し、当時の慣習に従って法廷弁論術を身に付ける道を歩んでいく。世俗的栄誉を目指して勉学に励み、またマニ教に傾倒して自らもマニ教を宣伝していた。そんなアウグスティヌスだったが、母モニカの祈りや、アンブロシウスの説教などによって、聖書の教えを受け入れていく。そして、自分の罪深さを悔い改めると共に、同時に神に対する感謝と賛美を捧げるのである。そこに見られるのは"高慢"や"自己顕示欲"とは反対の、"謙虚"な人間の姿である。
望むと望まざるとに関わらず、現代人は貪欲な社会で生きられることを強いられている。「営業成績を上げろ!」、「他社(他者)を出し抜け!」、「もっと効率を上げて収益を上げろ!」…そう言う社会で生きている。その中で生き残るために、世俗的な冨や栄誉を獲得すべく奔走する毎日を送らざるを得ない。若き日のアウグスティヌスも、そう言う道を正に"トップランナー"として走っていた。しかし彼は、"人間が本当に究極的な幸せ"を得るには、そう言う世の"金"や"宝石"や"物"と言った富や、世俗的な虚しい栄光では得られないことを悟る。それらは所詮、人間より下位の被造物でしかないのだ、と彼は語る。この忙しさと貪欲に追われる現代社会に生きる我々こそ、このアウグスティヌスの主張に耳を傾けるべきではないだろうか。
クリスチャンである私とアウグスティヌス哲学の関連について
知者と自ら信じている人々(="いわゆる高尚な学問の長靴をはいて威張る連中"とアウグスティヌスは例える)は、「神を知っていながら、これを神として崇拝もせず、感謝もせず、むなしい思いにふけり、愚かな心は暗くなる。みずから知者といいながら、じつは愚かとなる」、そうアウグスティヌスは言う。人の知恵で作った"虚しい思想"に対し、彼はそう断言する。なぜなら人の作った知恵では、人は幸福になれないからである。
彼が"告白"で述べたのは、人間の本当の幸福とは、人(被造物)を作った絶対的存在、絶対的善なる神に満足を求める事である。被造物たる人間が、その存在の欠如を満たそうとすれば、その欠けた部分は被造物を作られた神によってしか満たすことはできない。ピースの欠けたパズルに、いかにたくさんの異なるピースを寄せ集めてもパズルが完成しないように、被造物たる"金銀"や"宝石"や"虚栄"をどんなにたくさん寄せ集めたところで、人の欠けたところを埋め合わせることはできない。この世において休息を見い出せない心(=それは神に向けて作られた心である)は、神の天地創造における第七日目の永遠の休息において、初めて休息を見い出すことができるのである。アウグスティヌスの著述がその後の多くの時代のキリスト教徒を含め、多くの哲学者や人々に影響を与えたのは、その事を気づかせてくれるからだと思うのである。
クリスチャンは、その夕方の未だ到来していない(=未だ完結していない)創造の第七日目を生きているのであり、目に見える世俗的には不正が多く忙しく貪欲な時代ではあるが、目には見えないが既に到来している神の国において"本当の休息"を見い出して生きるのである。
(2010年12月19日記載)
新品価格
¥1,944から
(2014/11/18 15:46時点)
新品価格
¥2,160から
(2014/11/18 15:46時点)
中古価格
¥1,593から
(2014/11/18 15:45時点)
中古価格
¥642から
(2014/11/18 15:45時点)