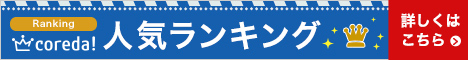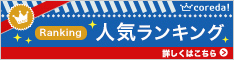入口 >トップメニュー >隠れた名映画 >現ページ
「スヌーピーとチャーリー」 (記:2000年1月)
新品価格
¥1,000から
(2014/11/14 17:41時点)
さて2000年が始まったばかりなのに、僕にはとても悲しいニュースがある。ピーナツシリーズを描き続けてきたチャールズ・M・シュルツが引退を表明したのだ。 "ピーナッツ"と言ってピンとこない人も、スヌーピーと言えばご存知でしょう。1950年10月2日に新聞の連載をはじめて以来、ちょうど50年。1999年中にすべての原稿を描き終え、2000年1月4日の新聞掲載が最終回。僕がこのピーナッツシリーズを初めて読んだのが、小学校2年の時。今から27年も前。その頃でさえ、連載から23年も経っていたのである。以来、鶴書房時代の第1巻からニュー角川版の21巻までの百冊以上を読み続け、未だにその百冊以上のピーナツコミックスを時おり読み返している。僕はピーナツに関してはややカルト的なファンで、知識だけでなくグッズも揃えている。ワークシャツ、灰皿、コップ、エプロン、ゴルフボールを初め色々と…。朝食のシリアルも、ケロッグではなく絶対ブラウン・シュガーと決めている。また、僕がイラストを書くとき、自然とピーナツをお手本にしてしまう。
COLLECTION by JOLLYBOY
そんな訳で、2000年最初に取り上げる映画は"スヌーピーとチャーリー"("スヌーピーの大冒険"も良いのだが、より素朴な味わいのある"スヌーピーとチャーリー"を取り上げたい)。「えっ、スヌーピーの映画なんてあったの?」と首を傾げる方も多いと思う。そのぐらい日本ではマイナーな映画で、ディズニーとは対照的な存在である。この映画の凄いところは、実はその地味さにある。ディズニーアニメの様な高度な技術を使っているわけでも、派手な見せ場があるわけでも、ジャパニメーションの様な物凄い動きがあるわけでもなく、淡々とストーリーが進行していく。日本では、企画段階で消えてしまうような内容だ。子供向けというより、本来は大人向けの要素の強い世界なので、スヌーピーのかわいらしさで子供にターゲットを絞った日本の戦略は裏目にでたと思う。しかしこうしたピーナッツの住人たちは欧米ではとても愛されていて、ビジネスマンの会話にも時おり登場し、なんと登場人物の名前が宇宙船の名前になってしまうことさえあった。
ピーナッツには子供しか登場しないが、その世界は大人の世界の縮図として描かれている。登場人物は、超わがままだったり、何気ない会話の中で哲学を語ってみたりと、一筋縄ではいかない連中なのだ。犬のスヌーピーでさえ (見た目のかわいさと裏腹に)、たいへんな皮肉屋なのだ。ピーナッツの世界はみんなが主人公だが、中でも主人公格と言えるのは"チャーリー・ブラウン"。彼は、作者チャールズ・シュルツの分身である。チャーリー(ペパーミント・パティ達が時折チャールズと呼ぶ)という名前はもとより、何をやっても失敗、赤毛の女の子に気づいてももらえない、というのは作者の人生経験の投影であることが知られている。
この映画でも、チャーリー・ブラウンの駄目ぶりが、冒頭から徹底的に描かれる。凧上げでは失敗し、野球では負けてしまう。いつもの通り、落ち込むチャーリー。そんな彼が、一念発起してクラスのスペリング・コンテストに出る。みんなに「俺はできるぞ!」と思わせたいのだ。誰でも人生の中で、そんな経験があるはず。好きな女の子に、少しでもかっこいいところを見せたいとか…。チャーリーも、がんばるのだ。そしてクラスで優勝!すると、なんと全校のコンテストに出場することに。みんなはチャーリーが失敗すると思っているが、スヌーピーやライナスの応援もあって懸命に勉強し優勝してしまう!喜んでいるチャーリーだったが、今度は学校の代表として全国大会出場する羽目に!ルーシーやバイオレットたちが、必要以上にプレッシャーをかける。もう、かっこいいところは充分見せたはずなのに、とんだことになってしまったぞ…と思うチャーリー。大勢に見送られて、本意ではないのに全国大会へ出発するチャーリー。
彼は、コンテスト会場のホテルでもフラフラになって勉強を続ける。しかし、ここでライナスから預かった大切な毛布を無くしてしまう(チャーリーが成功や名声と引き換えに、友達との絆を軽んじてしまったことが何気なく描かれている)。チャーリーは、決勝まで行くが大事なところで失敗して負けてしまう。テレビの前で泣きわめくルーシーたち。負けたチャーリーに対して、町ではみんなの出迎えすらない。そして家で落ち込むチャーリーを、ライナスが励ます。ライナスに励まされようやく外へ出たチャーリーに、ルーシーがいたずらを仕掛けチャーリーは転んでしまう。そしてルーシーは言う。「お帰りなさい。チャーリー・ブラウン」。たったこの一言が、さりげない感動を与える。説教くささは微塵もなく、「大切なもの」の意味ををさりげなくそっと差し出してくれるのだ。
こういう物語だが、音楽も効果的に使われている。シュローダーがベートーベンのピアノ・ソナタ「悲愴」のアダージョ・カンタビーレ(だと思うのだけど…)を弾くのだが、その時のイメージ映像がシュールでとても素晴らしく感動すら覚える。ストーリーとは何の関係もないし、見ている子供にはまったく意味不明だろうが、素敵なのだ。この映画には、いくつかそういうシーンがある。アニメと言うより、アートに近いのだと思う。スタッフの感性を取り入れてしまうところに、アメリカ映画の懐の深さが感じられる。
音楽全般を担当したのが、テレビ版と同じく"ヴィンス・ガラルディ"である。彼の作った曲はアメリカでは有名で、"ライナス&ルーシー"は多くの人が愛するスタンダード・ナンバーとなっている。しかし、ヴィンスは、1976年に47歳で亡くなってしまった。彼はピーナッツのテレビシリーズ・15本と、この1本の映画の音楽を担当しただけだった。後のテレビアニメの中でルーシーがチャーリー・ブラウンに、歴史上一番好きな曲は何かと尋ねる。するとチャーリーは、「それはヴィンス・ガラルディさ。」と答え、"ライナス&ルーシー"をハミングし始める。これはプロデューサーの粋な演出なのだが、当のプロデューサーはこの場面で泣いてしまったという…。
話題はちょっと映画からそれてしまったが、読者に愛され、視聴者からも愛され、制作スタッフからも愛され、世界中の人々から愛された "ピーナツ"シリーズ。チャールズ・M・シュルツ殿、半世紀の間ご苦労様でした。そしてありがとうございました。